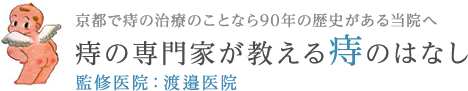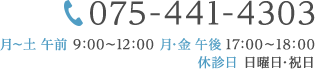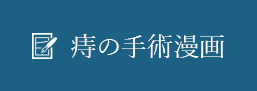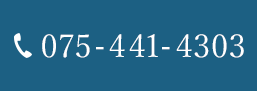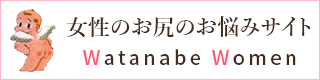「ぶりのバターポン酢焼き」のレシピを紹介します。

今回は「ぶりのバターポン酢焼き」のレシピを紹介します。
今日は、診療が終って母の家で一緒にいるとチャイムがなりました。誰かなあと玄関を開けると、母の家の小学校区の社会福祉協議会の民生委員の方が、母に敬老の日の記念品を持ってきてくださいました。母の住んでいる学区には80歳以上の方が850余名住んでおられるとのことでした。
母は認知症が進んでいますが、まだまだ元気です。先日母をデイサービスに迎えに行ったとき、母はいつも笑顔で私を迎えてくれるのですが、帰り道に私が「元気でしたか?」と聞くと、「私は元気ですよ。」と。私が「元気でよかった!」というと「そうですか。」と。
3~4年前でしたか、母と一緒に歩いているとき、ふと母が「私がいない方が、あなたは楽よね。」と。私はドキッとしました。そんなことを母が考えていたとは。なぜそのようなことを考えたのかわかりません。でもそんなことはありません。いつも母は笑顔でいてくれます。時にはこんなに笑うかと思うほど、顔をクチャクチャにして笑うこともあります。私はそんな笑顔が大好きです。そんな母をみているだけで日々の仕事を頑張ることが出来ます。いつまでも母の笑顔をみていたいと思います。
同じ小学校区に住んでおられる80歳以上の方々も同じだと思います。その方が元気でいることがまわりの人に生きる力を与えるのだと思います。
敬老の日を迎えるにあたって、皆さん元気でお過ごしください。
さて、今回はぶりのバターポン酢焼きです。ぶりと言えばすぐに頭に浮かぶのは、ぶりの照り焼きです。バターポン酢焼き、バターのこくとポン酢のさっぱり感。美味しそうです。管理栄養士さんから、鯖、鱈、鮭でも可能ということです。きっと白ご飯と会いますよ。前回紹介した、ところてんとワカメのスープと一緒に楽しんで下さいね。
ではレシピを紹介しますね。
「ぶりのバターポン酢焼き」

1人分 約380kcal たんぱく質 25g 食物繊維 2.5g
材料(2人分)
ぶり 2切れ
鯖、鱈、鮭でも可
塩 少々
小麦粉 適宜
油 小さじ2
★バター 大さじ1
★ポン酢 大さじ2
ピーマン 1袋
舞茸 1袋
作り方
- ①ぶりは軽く塩をし10分置いて、出てきた水気をふき取る。
- ②①に小麦粉を薄くまぶし、油をしいたフライパンで両面焼く。一緒にピーマン・舞茸も焼く。
*ピーマンは大きければ半分に、小さければそのまま焼く。
③付け合わせを取り出し、バター・ポン酢を入れてぶりに絡ませる。
④うつわに盛る。
管理栄養士さんから一言
ぶり
ぶりはたんぱく質が豊富で、脳の活性化や生活習慣病予防効果の期待できるDHAやEPA、骨の形成に重要なビタミンD、貧血予防の鉄、疲労回復の
ビタミンB1、脂質代謝に係るビタミンB2なども多く含みます。
魚油が流れ落ちない調理法が効果的です。
「青梗菜とえのきの生姜醤油和え」と「ところてんとワカメのスープ」のレシピを紹介します。

今日は、「青梗菜とえのきの生姜醤油和え」と「ところてんとワカメのスープ」のレシピを紹介します。
今日も日曜日ですが、入院の患者さんや手術をしたばかりの患者さんの診察に診療所に行ってきました。患者さんからは「先生、お休みなしですね。」とねぎらいの言葉をいただきますが、この生活がリズムになっているのであまり気にはなりません。
祖父も父も同じように診療していました。特に祖父の時はもっと頑張って診療をしていたようです。休みはお正月の三が日だけだったようです。土曜日は夕方まで、日曜日も午前中の診療をしていたようです。父が少しずつ休みを増やしていて、今の診療体制になりました。ですから今は随分診療時間も短くなって、楽をさせてもらっています。
ただ休みの日も、何か患者さんの具合が悪くなったりした場合は、直ぐに連絡がとれ、診察できる体制は24時間常にとっています。ですから泊りがけの旅行には行ったりすることはできません。
私が子供の頃は、父と一緒の旅行はなく旅行は母と妹の3人でした。なかなか入院の患者さんや手術をした患者さんがいるので、泊りがけの旅行はいけません。学会や年末年始の休みの時は、休み中に何も起きないように、そっして休み中は安心して患者さんが過ごしてもらえるように、休みの前はある程度手術を制限しています。こんな感じで日々を過ごしています。
さて話は変わりますが、今回のレシピ。便秘の方にはとても良いレシピだと思います。
具合よく便が出るには便の中に程よく水分が含まれ、そして便の量を増やす食物繊維があり、そして大腸が具合よく動く。この三つが揃って気持ちよく便が出ます。どれ一つ欠けてもダメです。ただ大腸の動きは便の量があると便そのものが大腸を刺激して動きを良くしてくれます。
この中の便の量を増やすということで、今回のレシピは有効です。十分な食物繊維が必要ですが、生野菜は量があってもそれほど繊維の量は摂れません。どちらかというと、キノコ類や海藻類の方が繊維の量は増やせます。ですから便の量を増やすということだけを考えると、生野菜のサラダよりは海藻とキノコのサラダの方が繊維の量は摂れます。そういったことを考えると今回のレシピ「青梗菜とえのきの生姜醤油和え」と「ところてんとワカメのスープ」はいずれも便の量を増やしてくれます。便秘の方は特に試して下さいね。
ではレシピを紹介しますね。
「青梗菜とえのきの生姜醤油和え」

1人分 約75kcal、たんぱく質 5g、食物繊維 3g
材料(2人分)
青梗菜 1株
えのき 1袋
うす揚げ(小) 1枚
生姜(すりおろし)1かけ
粉末だし 少々
醤油 小さじ1/2
作り方
- ①青梗菜・えのきは3cmの長さに切ってゆでる
- ②うす揚げは焼いて短冊に切る
- ③調味料で混ぜる
- 「ところてんとワカメのスープ」
-

-
1人分 約40kcal、たんぱく質 1g、食物繊維 1g
材料(1人分)
ところてん 小1パック
わかめ 大さじ1
ごま 小さじ1
めんつゆ 適宜
ごま油 小さじ1
*めんつゆの代わりに中華スープで作ってもおいしいです。作り方
①器にところてん以外を入れ熱湯を注ぐ。
②水切りしたところてんを入れる。
「長芋の柚子胡椒サラダ」と「長芋とミートボールのグラタン」のレシピを紹介します。

今日は、長芋2品ということで、「長芋の柚子胡椒サラダ」と「長芋とミートボールのグラタン」のレシピを紹介します。
9月になって、特に今週に入って少し涼しくなり、秋の気配を感じるようになってきました。でも何か、天気は安定せず、今も辺りは暗くなって、いかにも雨が降り出しそうな気配です。日の沈むのも早くなって、6時半ともなれば辺りは暗くなっています。
さて、今回紹介するレシピのなかにあるグラタンですが、私は小さいころからマカロニグラタンが好きでした。表面のカリッと少し焦げた感じや、中のホワイトソースが好きです。マカロニグラタンをおかずに白ご飯も食べれます。
グラタンと聞くといつも思い出すことがあります。それはまだ私が小学生のころ甲府に住んでいたのですが、生まれたのは長野県の松本。松本には小さいころよく遊んでくれたご近所の方がいて、お兄さんのような存在でした。「かつみ」というお名前で(漢字があいまいなのでひらがなで)いつも「かっちゃん、かっちゃん。」と言って遊んでもらっていました。その「かっちゃん」の家に小学生の頃初めて一人で汽車に乗っていったときのことです。
家族の方と食事を食べに行ったとき、「なんでも好きなものを頼んでいいよ。」と言われて、メニューを見ると「グラタン」がありました。私はてっきり「マカロニグラタン」だと思いこんで頼んでみると、マカロニが入っていませんでした。すごくショックでしたが、そんなことは言えません。でも美味しく頂きました。次の日、「昨日は物足りなかったろうから、今日はかつ丼ね。」と。グラタンと聞くと必ずこのことを思い出します。
また、自宅に近くに、こちらは正真正銘のマカロニグラタンをメニューにおいてあるお店がありました。このお店に行ったときは必ず「エビのマカロニグラタン」を頼んでいました。お店の方からも、時々、「今日はマカロニグラタンはよろしいんですか?」と聞かれるぐらいです。またそのお店には「牛筋肉の小さなカレー」というメニューもあって、最後の絞めに頼んでました。残念ながら、そのお店は別のお店に変わってしまい、食べることが出来なくなってしまいました。
ということで、そろそろレシピを紹介しますね。
「長芋の柚子胡椒サラダ」

全体量 約110kcal、たんぱく質 3g、食物繊維 1.2g
材料(4人分)
長芋 8cm
ウインナー 50g
玉ねぎ 1/8個
マヨネーズ 大さじ2
柚子胡椒 小さじ1/2
*長芋は火を通し過ぎない方が表面はほくほく・中はシャキシャキと食感がいいです。
作り方
- ①長芋は5cm角、ウインナーは小口、玉ねぎは薄切りにしてフライパンで炒める。
- ②全ての材料を混ぜる。
「長芋とミートボールのグラタン」
-

全体量 約400kcal、たんぱく質 21g、食物繊維 5g
-
材料(作りやすい分量)
長芋 8cm
茄子 1本
ミートボール 1袋
チーズ 40g
*長芋がホワイトソース替わりになります。 - 作り方
- ①器に乱切りした茄子とミートボールを入れ電子レンジで温める。
- ②①に長芋をすりおろし、軽く混ぜて、チーズをかけオーブントースターで焼く。
「かぼちゃとクリームチーズの大福」のレシピを紹介します。

10月のレシピが管理栄養士さんから届きました。こんなメールをいただきました。
「この夏はコロナ・大雨・猛暑といつもと違う夏でした。まだ台風が来るかもしれません。この暑さもやっと終わりが見えてきたように思いますが、夏を乗り切ってほっとし、今までの疲れが出て体調を崩しやすい時期になります。まずはしっかり食べて、ちゃんと睡眠をとり、味覚の秋・スポーツの秋・芸術の秋と不自由な中でも楽しい秋が過ごせますよう、秋の食材の力を借りたいと思います。
10月1日は中秋の名月。小さなかぼちゃ大福でお月見もいかがでしょう?」
ということで10月のレシピを紹介していこうと思います。
さて、今週になって、今までの暑さとは違って少し涼しくなって、過ごしやすくなってきました。秋の気配を感じるようになりました。
秋の気配を感じると、少し感傷的になってしまいます。最近チョット感じたことをお話します。
今週の火曜日、いつも診療が終って母をデイサービスに迎えに行きます。迎えに行くといつも母は笑顔で私を迎えてくれます。母の家に行き、着替えをしてもらった後、母と私の親子二人の一時を過ごします。母を寝かした後、自宅に帰宅します。
その帰り道、涼しくなり秋の気配がする夜の空に、まだ満月ではありませんが、大きな月が空に浮かんでいました。そんな月を見ながら、「大切な人を守ること。それはいつも一緒にいることなのか?いつも寄り添っていることなのか?また大切な人の近くにいなければ守ることができないのか?遠くにいては守れないのか?」とフッと頭に浮かびました。秋の気配の影響なのでしょうか?
今、新型コロナウイルス感染の収束がまだまだ見えない中、私たち一人ひとり、自分の本質、そして生き方が問われているのだと思います。良きにしろ悪しきにしろ、本質が見え隠れします。
この新型コロナ禍においても、私は相手のことを思いやり、優しさを忘れずにこれからも生きていきたいと思います。
国や京都府、京都市などの自治体も同じだと思います。新型コロナウイルスの感染によって、とても大変であることわわかります。でもそういった状況であるからこそ、国や自治体の本質が問われ、見えてくるのだと思います。社会保障の充実に向けての政策に舵を切って、国民、府民そして市民の命や健康、そして生活を守るそういった本来あるべき姿勢を見せて欲しいと思います。
今日は10月のレシピに中の「かぼちゃとクリームチーズの大福」のレシピをまず最初に紹介したいと思います。
これからの秋の夜長、月見をしながら自分で作った大福を食べる。どうでしょう?作ってみて下さいね。
「かぼちゃとクリームチーズの大福」

1個 約100kcal たんぱく質 3g 食物繊維 1.5g
材料(6つ分)
★白玉粉 40g
★上新粉 20g
★砂糖 20g
★水 約110cc
片栗粉 適宜
かぼちゃ 150g
砂糖 大さじ2
クリームチーズ 50g
(作り方)
- ①耐熱容器に★を入れよく混ぜて、電子レンジで2分チン。一度取り出し混ぜて1分チン。なめらかになるまで2~3回繰り返し、片栗粉にとる。
- ②かぼちゃを一口大に切ってチンし、中身だけ取り出し、砂糖と混ぜる。
鍋に入れぽったりするまで練る。
③クリームチーズを6等分して丸め、②で包む。
④①を片栗粉をつけながら広げ③を包む。
〈ハロウィーン風ラッピング〉

〈中をさつまいもあん+栗の渋皮煮〉

<第4次提言>新型コロナ感染症から京都府民の命と健康を守るために

9月も第1週が終りました。台風10号の影響がとても心配です。大きな被害が出ないことを祈るばかりです。
さて、8月17日に京都府保険医協会は「<第4次提言>新型コロナ感染症から京都府民の生命と健康を守るために」という提言を出しました。今回はその内容を少し長いですが紹介したいと思います。
<第4次提言>
新型コロナ感染症から京都府⺠の⽣命と健康を守るために
- 1.今後のさらなる感染拡大を見据えた外来医療体制の整備と支援を
新型コロナウイルス感染症の感染拡大傾向が続いている。今後のさらなる拡大を見据え、府内の 医療提供体制の強化が求められる。
とりわけ秋冬には市中では季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症が同時流行し、地域の医療機関における感染リスクが一層高まることが危惧される。COVID-19 の流行がみられる場合には、インフルエンザが強く疑われる場合を除いて、可及的に両方の検査(検体同時採取)を行うことが推奨される(日本感染症学会提言)。しかしインフルエンザウイルス抗原定性は鼻腔咽頭拭 い液採取により行うため、医療機関の新型コロナウイルス感染リスクが高まってしまう。
以上のことから、府民の生命と健康、地域の医療機関を守るため、帰国者・接触者外来、京都府・ 医師会京都検査センター、京都府と京都府医師会による「行政検査として唾液を検体とする新型コロナウイルス感染症に係る検査(PCR 検査)」の集合契約に参加する医療機関のみならず、公的な発 熱外来を設置し、SARS-CoVⅡ核酸検出、抗原検査並びにインフルエンザウイルス抗原定性の検査も可能な体制を整備すべきである。
①公的発熱外来は各市町村に最低限1カ所以上を、都道府県保健所並びに市町村保健センターの敷地内あるいは近接地域に設置し、責任・運営主体は保健所が担う。
②京都市内においては全行政区に複数設置が望ましく、設置場所は区役所近隣の公立施設や統廃合校跡地等も活用する。また府内、京都市内ともに、公立・公的病院、民間病院の協力も得て、当該病院の敷地内の設置も推進する。
③設置にかかる経費は全額、京都府と各市町村の負担とし、国に対して財政補償を求める。設置した公的発熱外来は、365 日の稼働とし、地区医師会へ当番制による出務を依頼する。出務にかかる費用は全額、公的財政で負担すべく、国に対して財政補償を求める。
④京都府と京都府医師会の集合契約に参加した医療機関も含め、万全の感染拡大対策が可能となるよう、医療資機材の支給、出務する医療スタッフの危険手当支給が可能な財政補償等に取り組むよう求める。
2.インフルエンザ予防接種に対する公費負担の拡充を
新型コロナウイルス感染症が拡大する中、例年以上に季節性インフルエンザの予防に努めることが重要となる。既に京都府内各市町村において主に高齢者を対象としたインフルエンザ予防接種に対する公費助成が行われているところであるが、新型コロナウイルス感染症の収束に至るまでの間、 希望するすべての府民を対象にインフルエンザ予防接種の公費負担を拡大するよう求める。
3.京都府における特別警戒基準到達を踏まえた方針について
(1) 厚生労働省の第4回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(7月 30 日)を受け、京都府における感染状況、検査や医療体制状況などを府民にわかりやく説明すること。特に、マイクロ飛沫感染防止の強調、関西の実効再生産指数に基づく警戒呼びかけ、クラスター事例の例示等を補強するよう求める。
(2) 関西の実効再生産指数を踏まえれば、東京はじめ関東圏と比べ、より厳しい感染防止策が必要であることを明確に示すよう求める。
4.感染拡大防止のためにPCR 検査の拡充を求める 社会経済活動と感染制御の両立のためには無症状陽性者の早期発見が重要になっている。
感染リスクを有し、社会経済活動の維持と感染拡大の抑止のために検査が必要な人を対象にし、 保健所あるいは医師の判断によってPCR 検査が実施できるようにすることが重要である。
厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対策推進本部8月7日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に関するPCR等の検査体制の更なる強化について」を踏まえ、積極的な対応を求めたい。
(1) 上記観点から実施するPCR 検査については公費負担で実施する。
(2) 対象は京都府の検査体制と医療体制を踏まえて決定し公表する。府民に対しては PCR 検査の方針を説明するとともに、相談窓口を設けて丁寧に対応する。
(3) 地域医療の資源、検査協力医療機関、帰国者・接触者外来、京都府医師会 PCR 検査センター、 民間の検査機関などが連携する多様な検査体制を整備する。
(4) 有病率の低い集団に検査を拡大することで懸念される偽陽性に対しては、必要な再検査を行って確定する。
(5) 検査件数、検査結果、検査精度のモニタリングや改善状況などの情報システムを整備し、公表することも重要である。
5.新型コロナウイルス感染症患者とそれ以外の患者も受け止める医療提供体制を 厚生労働省による6月19 日付の事務連絡「今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提 供体制整備について」を受け、府としても新たな患者推計に基づく入院医療提供体制の確保に尽力されているものと敬意を表する。
(1) 医療機関参加型で提供体制の強化を
地域医療構想調整会議の枠組みも活用し、すべての入院医療機関の理解と納得に基づく対策が早 期にとられるよう期待する。特に感染症病床を持つ基幹病院であっても、院内感染・クラスター発 生が起こり得る前提での対策が必要である。私たちが提案(2020 年3月 25 日)してきた「COVID-19 ネット」のような、病院群ネットワークを立ち上げ、情報の共有、医療提供体制上の役割分担の推 進等を、医療機関参加型で組織的に行えるようにする必要がある。
(2) 新型コロナウイルス感染症以外の患者も含めたトータルなビジョンを
6月1日に厚生労働省が発表した救急医療提供体制アンケート結果によると、「新型コロナウイ ルス感染症が疑われる症状を有している救急患者を、まず受入れる医療機関を設定しているか」との問いに対し、京都府は「未設定」であるとされている。一方で、京都市では救急たらい回しが6倍増との報道もあった。予防、検査、入院の治療・療養先、救急時の受け入れ態勢も含めたトータ ルなビジョンを求めたい。
また、今後感染が拡大すれば新型コロナウイルス感染症以外の患者受け入れ先が課題となることは明らかである。
新型コロナウイルス感染症ではない患者に対する入院医療の確保についても、あらかじめ想定し た病床確保が必要であり、基準病床数をはじめ病床新設のハードルを下げることも必要と考える。
6.リスクコミュニケーション策の改善を
WHOのガイダンスは「公衆衛生上の対応において最も重要かつ効果的な介入の1つは、予見的かつ積極的に情報を伝達することである」と述べ、そのことが「インフォデミックを防ぐことに役立ち、適切な行動への信頼を構築し、健康に関する助言に従う割合を高める」と述べている。未曽有のパンデミックの渦中にあって、府民の誰しもが感染拡大予防に努め、なおかつ生きるための日常生活を人間らしく営むためには、常に行政が正しい情報を公開し、対話することで少しでも不安 を低減させることが肝要である。
(1) 保健所の本来機能としてのリスクコミュニケーション策を求める
とりわけ、感染者(医療関係者を含む)に対する偏見が社会問題化することがないよう啓発に努 めることも重要な課題である。そのためには保健所が本来機能を取り戻すことが必要である。
保健所は地区医師会と連携して保健所医師・保健師はじめスタッフが分担する地域の感染防止策、 住民の心構え、感染した場合の医療へのアクセス、濃厚接触者となった場合の生活面も含めたフォロー等、正しい情報を提供し、不安な状態に置かれている府民の心情に寄り添った取組を求める。
(2) 帰国者・接触者外来、京都府との集合契約に参加する医療機関、患者受入入院医療機関が公開できるよう、対策を求める
現在、帰国者・接触者外来、京都府との集合契約に参加する医療機関、患者受入入院医療機関が 非公開とされている。これは風評被害や医療従事者に対する差別事案の発生、あるいは PCR 検査を実施する医療機関へ府民が殺到するといったパニック状態を危惧してのことと考える。だが、そうした状態が想定されること自体、国・地方自治体と住民の間のリスクコミュニケーションが不全な 状況にあることを示している。
メディアが洪水のように新型コロナウイルス感染症についての情報を垂れ流し、何が正しいのか、 間違っているのか、専門家でない人たちには判断のしようがない。一方で、メディアから疎外され、何ら情報を得ることもできない人たちも存在するはずである。
行政職、とりわけ保健師等専門職が地域を担当し、地域住民に対する時時刻刻の情報発信、予防 策の啓発等、もしもの時の対応についてアウトリーチによって理解してもらう取組が必要と考える。 地域の開業医も保健所スタッフと一体となり、その役割を果たすことも可能と考える。そうした取 組が行えれば、どこで PCR 検査が受けられるのか、入院できるのかという情報もすべて公開できる のではないか。
7. すべての医療機関に対する経営支援策の実施を国に求めること
本年5月、6月、7月請求分(4月、5月、6月診療分について、保険医療機関からの申請に基づき、昨年同月実績との報酬差額を公費にて助成するよう、国に求めていただきたい。
*保険医療機関は、申請にあたって本年4月、5月、6月提出の診療報酬請求明細書の写しと、 8 昨年の同月分の支払い確定額(患者負担分は除かれるが確認できる書類の写し、その双方を添付し、各都道府県に対し提出するものとする。その後、各都道府県において受理された申請分については、 国保連合会、または社会保険診療報酬支払基金を通じて申請のあった保険医療機関の診療報酬振込 指定口座あてに振り込むものとする。
昨年分の実績のない、開業から日の浅い医療機関については、開業後の実績額と比較して一定割 合の減収がみられる場合、持続化給付金に準ずる制度を厚労省において創設いただき、特例給付いただくなど、別途対策をご検討いただきたい。
また、「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」における補助対象について、2020年4月1日から2021年3月31日までにかかる費用とされているが、それ以前に各医療機関の講じた感染 防止策にかかる経費も対象とすることを求める。
以上のような提言を出しました。
手術に関しての窓口負担の計算の仕方。実際の点数を示して。

前回は、外来と入院の窓口負担額の計算の方法を実際の点数を示してお話しました。今回は肛門の手術の点数などを紹介したいと思います。
今回お話する手術の点数は日本全国皆同じで、どの医療機関を受診しても同じ点数です。病院や診療所等、医療機関の規模が違っても手術に関わる点数は同じ点数です。時々病院では手術の点数が高いと勘違いしている患者さんもいますが、そんなことは有りません。病院でも診療所でも、どんな医療機関を受診しても全国一律同じ点数です。このことはとても大事なことです。
肛門科の医療機関の中には、自費診療をされている医療機関があります。この場合はこの保険点数は適応されず、その自費診療をされている医療機関それぞれで違ってきます。今回お話するのは保険診療をしている医療機関でのことです。
今回は肛門の病気で多い、内痔核、外痔核、痔瘻、肛門周囲膿瘍、裂肛などについてその点数を紹介します。また、時々生命保険屋さんから、「手術の番号を聞いてきてくださいと言われた。」という患者さんがいます。手術は「K」という番号で全ての手術に番号が付いています。この番号も一緒に紹介します。
まずは内痔核、外痔核に対しての手術です。痔核硬化療法も手術に入ります。そして痔核硬化療法にはパオスクレーという痔核硬化剤とジオンという痔核硬化剤で行う四段階注射法での痔核硬化療法の二つがあります。
- ①パオスクレーによる痔核硬化療法(K743-1) :1660点
- ②ジオンによる痔核硬化療法(四段階注射法)(K743-2 ):4010点
- ③痔核手術・血栓摘出術・輪ゴム結紮法等(K743-3 ) :1390点
- ④痔核根治術(K743-4) :5190点
- ⑤痔核根治術+ジオンによる痔核硬化療法(K743-5) :6520点
内痔核や外痔核に関する点数はこの五つです。
例えば、痔核根治術の窓口負担は3割負担で5190点×10円×30%=15570円となります。
ただ、これは痔核根治術だけの点数なので、これに麻酔薬の点数や痛み止めなどの内服薬の点数、そして入院でしたら入院基本料の776点を足すことになります。
ちなみに渡邉医院では1%塩酸プロカインの局所麻酔で手術をします。術後消炎鎮痛剤の座薬を2個使います。これらの麻酔剤と消炎鎮痛剤を足すと65点になります。
また、ジオンによる痔核硬化療法(四段階注射法)ではジオンの薬剤費が追加になります。ジオン1Vは455点、2Vで910点となります。ですからジオン2Vを使って四段階注射法で痔核硬化療法をすると、
(4010点+910点)×10円×30%=14760円となります。これも麻酔料などのほかの点数は入っていません。
次は痔瘻です。
痔瘻には単純な痔瘻と複雑な痔瘻との二つに分かれています。
- ①痔瘻根治術・単純なもの(K746-1):3750点
- ②痔瘻根治術・複雑なもの(K746=2) :7470点
となります。これも内痔核と同様に計算すると窓口負担分がわかります。
次は裂肛です。
裂肛には、裂肛又は肛門潰瘍根治術と裂肛などが原因で肛門狭窄を起こすことがあり、肛門狭窄形成術の二つがあります。
- ①裂肛又は肛門潰瘍根治術(K744) :3110点
- ②肛門狭窄形成術(K752-1) :5210点
となります。
また肛門の病気には肛門ポリープや尖圭コンジロームなどがあります。これらはK747 で1250点です。
また肛門の近くにも粉瘤が出来ることがあります。粉瘤を摘出する場合は、粉瘤の大きさで点数が違ってきますが、長径が3㎝未満の粉瘤の場合は1280点になります。
高齢の女性に多いのですが、直腸脱と言って直腸の粘膜が出てくる病気があります、これに対して直腸脱手術をしますが、それはK742 (1・イ)で8410点になります。
このように手術にはそれぞれKの番号が付き点数が決められています。
では一つだけ具体例をしましますね。
1泊2日の入院で痔核根治術をした場合を例に挙げます。
①入院2日間:776点×2日間=1552点
②痔核根治術:5190点
③麻酔などの薬剤費:65点
④消炎鎮痛剤、抗生剤、胃薬などの内服薬:108点
⑤術後1日目の術後の創処置:52点
⑥術後1日目の消炎鎮痛剤の座薬:4点
これらを全て足すと、6971点になります。3割負担ですと、
6971点×10円×30%=20913円。四捨五入で20910円となります。ですから手術代、入院費等を合わせて、退院時に窓口で支払う窓口負担金の合計は20910円になります。入院費1552点と痔核根治術5190点のみを足すと1552点+5190点=6742点。6742点×10円×30%=20226円です。すべてを合計したときの窓口負担金とほぼ同じです。ですから大まかな入院して手術をする際の必要な窓口負担の金額は776点の入院基本料×入院日数に手術点数を足したものと考えてもらったらいいと思います。
こんな感じで計算していきます。参考になればと思います。
外来、入院での窓口負担の計算の仕方。実際の点数を示して。

前回、窓口負担がどのように決まっていくのかについてお話しました。
診療報酬の1点が10円で、それぞれの自己負担割合が1割、2割、3割であれば、診療報酬の点数×10円×自己負担割合(3割負担であれば、×30%)ということもお話しました。
そこで、今回は渡邉医院の例を挙げて、外来診療での点数や入院、手術の点数の一覧表を作ってみました。それぞれ該当する点数を足していって、それに10円と自己負担割合を掛け合わせると外来窓口負担が出ます。
ではまずは外来診療に関しての点数を紹介します。
初診料・再診料
初診料: 288点(6歳未満 +75点)
時間外 + 85点(288+85=373点) (6歳未満 +200点)
休日 +250点(288+250=538点) (6歳未満 +365点)
深夜 +480点(288+480=768点) (6歳未満 +695点)
再診料: 73点(6歳未満 +38点)
時間外 + 65点(73+65=138点) (6歳未満 +38点)
休日 +190点(73+190=263点) (6歳未満 +260点)
深夜 +420点(73+420=493点) (6歳未満 +590点)
外来管理加算: 52点
調剤料:内服薬 11点
外用薬 8点
処方料:42点
外来での肛門の処置としてはパオスクレーによる痔核硬化療法があります。
パオスクレーによる痔核硬化療法は1660点です。そして痔核硬化剤のパオスクレーは1回に5mlは使うので128点になります。
肛門鏡検査:200点
外来はこのようになります。
初診だけの場合は、3割負担の患者さんの場合は、
288点×10円×30%=864円で四捨五入で864円の窓口負担になります。
酸化マグネシウム(1点)という緩下剤を7日間分処方された場合は、
{288点+(1×7日分)+11点(調剤料)+42点(処方料)}×10円×30%=1044円。四捨五入で窓口負担は1040円になります。
初診でパオスクレーによる痔核硬化療法を受けた場合は、
(288点+1660点+128点)×10点×30%=6228円。四捨五入で6230円になります。
こんな感じで窓口負担は決まっていきます。
後は、外来で手術をしたり、痔核硬化療法をした場合は、この手術料や痔核硬化療法料などを足していきます。手術点数などは後で紹介しますね。
さて、渡邉医院は19床の有床診療所です。入院する患者さんもいます。
渡邉医院での入院の点数を紹介します。
有床診療所の入院基本料は看護職員などの配置人数で決まります。渡邉医院の場合は、有床診療所入院基本料5という施設基準で届け出をしています。この基本点数に地域加算、夜間緊急体制確保加算、看護補助配置加算2の三つの加算を足したものが1日の入院基本料になります。
地域加算は京都市は5級地:9点
夜間緊急体制確保加算 :15点
看護補助配置加算2 :15点
有床診療所入院基本料5 :737点(入院14日以内)
これらを全て足すと、渡邉医院の1日の入院基本料は776点となります。
ですから1日の入院料3割負担の患者さんでは776×10円×30%=2328円。四捨五入で2330円となります。
入院中の調剤料は入院調剤料7点です。入院中に薬が出ると調剤料として7点ついてきます。
このように入院の窓内負担は決まってきます。
渡邉医院では肛門の手術をした後の入院の患者さんなので、手術料がかかってきます。そこで次回は、主な肛門の手術の点数を紹介しますね。
痔瘻や肛門周囲膿瘍によく似た肛門の病気

今回は肛門周囲膿瘍に似た症状が出る病気についてお話したいと思います。
肛門周囲膿瘍は肛門と直腸との境目にある肛門腺に細菌感染を起こして炎症を起こし膿瘍を形成して膿が広がっていく病気です。炎症を起こし、膿が溜まっていくので、とても痛い病気です。痛みはどんどん強くなっていき、場合によっては38℃以上の熱が出ることもあります。肛門周囲膿瘍は直ぐに切開して膿を出す必要があり、膿が出ることで痛みはスッと楽になります。ただ、その後約30%の人が痔瘻になっていきます。
今回はこの肛門周囲膿瘍に似たような症状が出る病気についてお話します。
肛門部の粉瘤
一つ目は、肛門部の粉瘤です。
肛門部にできた粉瘤に細菌感染を起こすと赤く腫れてきて、場合によっては化膿することがあります。この場合も肛門周囲膿瘍と同じように切開して膿を出すことがあります。
粉瘤の原因はなかなか難しいですが、毛の生え際の部分が狭くなったり詰まってしまうことで、皮膚の下に袋状のものが出来て、その袋の中に皮膚から剥がれ落ちる垢や皮脂が溜まることでできてきます。粉瘤は肛門部だけでなく、背中や頬、また耳たぶなどにできることがあります。感じとしてはニキビの大きなものと言った具合です。
粉瘤は特に悪性の病気ではないので、そのまま放置していてもかまいません。ただ、段々大きくなって気になるようでしたら手術をしてとることもできます。また細菌感染が起こして炎症を起こしたときは、早期のうちですと抗生剤の内服で治っていきますが、先ほどお話したように化膿してきた場合は切開して膿を出す必要があります。手術で取り除く場合は、袋を残さないように粉瘤を摘出します。局所麻酔での手術で入院の必要はありません。
肛門部の毛嚢炎
二つ目は肛門周囲の毛嚢炎です。
肛門の周囲にも毛穴があります。この皮膚の毛根を包んでいる毛嚢に細菌感染を起こして炎症を起こしたり化膿する病気です。これもニキビに似ています。毛嚢炎は抗生剤の内服で治っていきます。痔瘻の二次口(出口)と似ています。
膿皮症
三つめは膿皮症です。
膿皮症は、アポクリン汗腺という汗が出る腺や毛包の機能の具合が悪くなって細菌感染を起こし炎症を起こす病気です。細菌感染を繰り返すことによって、毛包と毛包との間に痔瘻のような瘻管を作ったり、皮膚の下に膿瘍腔を形成することがあります。症状としては痔瘻と似た症状ですが、痔瘻の二次口のような瘻孔があちこちに多数できることがあります。また慢性の炎症を起こすので、肛門の皮膚全体が硬くなってしまうこともあります。治療としては膿瘍腔を形成した場合には切開排膿を行う必要があります。痔瘻と同じようにスッキリ治すには手術をして瘻管や膿瘍腔を切除することが必要になります。渡邉医院では局所麻酔で手術をしますが、1泊は入院したほうがいいと思います。
毛巣洞
四つ目は毛巣洞です。
毛巣洞は、体毛が皮膚の外に生えてこず、皮膚の下に潜り込んだように生えてしまい、その体毛に細菌感染を起こし炎症を起こし場合によっては膿が溜まる病気です。できる場所は肛門から少し離れた背中側、尾てい骨や仙骨のちょうど真ん中に起きやすいです。
化膿した場合は肛門周囲膿瘍と同様に切開して膿を出すのですが、その膿瘍腔の中に体毛がたくさん埋まりこんでいることがあります。症状は痔瘻と同じで、瘻孔から膿が出たり治まったりします。また炎症が強いと化膿して肛門周囲膿瘍と同じような症状が出ます。毛巣洞もスッキリ治すには手術が必要になります。
局所麻酔の手術ですが、毛巣洞の場合も1泊は入院したほうがいいと思います。
このように肛門周囲膿瘍や痔瘻に似たような病気が色々あります。肛門周囲が腫れてきて痛みが出る場合は、早く肛門科を受診して治療をしてもらって下さいね。
診療後、窓口負担ってどうやって決まるの?

今日、診察が終って会計をする際に、「再診料と処置料等を合計すると134点。1点が10円なので、1340円。その30%負担なので、今日は400円ですよ。」と言って会計すると。「そんな風な仕組みになっているんですね。初めて知りました。」と。そして医療機関で払う金額が違うのは?」ときかれたので、「渡邉医院では、手術や痔核硬化療法。軟膏や飲み薬など、自分が受けている医療行為と点数が一致するのでわかりやすいんですよ。内科などでは、管理料や指導料など実感がない医療行為に点数が付いていて、その管理料や指導料は、その医療機関の施設基準など、施設施設でとれる点数や取れない点数があるからですよ。」とお話すると。「そうなんですね。今度、明細書もらった時はみてみます。」と言って帰られました。
医療機関を受けて窓口で会計をする。その時の料金がどうなっているのかを十分に理解している患者さんは少ないのかなあと思い、今回はどんな仕組みで窓口で支払う料金が決まるかを少しお話したいと思います。
様々な医療行為に対してすべて点数がついています。そしてその点数は2年に1回づつ見直され、改定されます。今年の4月に改訂がありました。次は2年後です。
一つ一つの医療行為に点数が付いているのですが、例えば初診料というのがあります。初めて医療機関を受診した時につく点数です。今は、この初診料は288点です。ですから初診料だけですと288×10円=2880円となります。そして自己負担が3割の人は、2880×30%=864円。四捨五入で860円の窓口負担になります。2回目以降医療機関を受診する際の再診料は73点です。73×10円=730円。3割負担の方は730×30%=219円。ですから220円の窓口負担になります。こんな風にして計算して窓口負担が決まります。
少し詳しく例を挙げて説明しますね。
渡邉医院を始めて受診して、内痔核があったとします。出血も多いのでパオスクレーという痔核硬化剤で痔核硬化療法をして。軟膏も処方されたとします。その時はどうなるかです。
初診料:288点 痔核硬化療法:1660点 パオスクレー5ml:128点 軟膏:13点 調剤料:8点 処方料:42点
となります。これを全部足すと。288+1660+128+13+8+42=2139点となります。
2139×10円=21390円。3割負担の方だと21390×30%=6417円。四捨五入で6417円の窓口負担となります。こんな感じで決まっていきます。
渡邉医院の場合は、指導料や管理料などの実感のない点数が無いので、点数と窓口負担がわかりやすいと思います。ただ、内科系などの医療機関ですと、その管理料や指導料などが点数に加わってきます。この管理料や指導料が患者さんにとってはとても解り難いのだと思います。でも、この管理料や指導料は、患者さんにとっては解り難いのですが、とても大切な点数でもあります。例えば糖尿病や高血圧症の患者さんにどういったことに気を付けて生活をしたらいいか、どのような食事をしたらいいか。また、血液の検査などを行った結果を見ながら内服薬の調整をした理、次にいつ検査をしたらいいか、またどんな検査が必要なのかを考え、管理していく。そして指導していく。目に見えない医療行為ですがとても大切だと思います。またこの管理料や指導料が各医療機関の施設基準で変わってきます。また、初診料や再診料なども診療所と病院では違ってきます。
ただ、手術料などは日本全国どこの医療機関に言っても同じ点数です。例えば痔核根治術は5190点、痔瘻根治術は3750点、裂肛根治術は3110点と、この点数はどこの医療機関でも変わりません。
渡邉医院は有床診療所です。入院の施設があります。この入院の際にかかる入院基本料は各医療機関の人員配置(看護師の人数等)等、施設の規模や医師や看護師などの配置人数などで点数が違ってきます。渡邉医院の1日の入院基本料は776点です。
また、手術の点数はどの医療機関でも、診療所でも病院でも同じです。でも手術の際の麻酔の仕方で手術にかかる点数が変わってきます。渡邉医院は局所麻酔で手術をします。ですから手術の際にかかる麻酔量は麻酔薬の薬剤費だけです。これが腰椎麻酔や硬膜外麻酔、また全身麻酔等麻酔の仕方で点数がちがってきます。また麻酔の際の麻酔管理料なども加算されます。局所麻酔だけですと麻酔薬の薬剤費だけで、麻酔の管理料はありません。
このようにいろんな点数を足したものに10円をかけて、各自の負担割合(1割負担、2割負担、3割負担など)で窓口で払う費用が決まってきます。
今度医療機関にかかられた際には、一度明細書を見て確認してみて下さいね。
公衆衛生行政の充実を求めて。

もうすぐ9月になります。まだまだ厳しい残暑が続いています。でももう9月。残すところ今年も4か月。早いものです。
今年は新型コロナウイルスの感染拡大から始まって、新型コロナウイルスで終わる。まだまだ今年で収束知るかどうかもわからない状況です。
さて、新型コロナウイルスの感染拡大の中、保健所など公衆衛生行政の不十分さ、脆弱さを露呈しました。また、これまで進められてきた公衆衛生行政の縮小の影響が今の現状を反映していると思います。
公衆衛生行政の充実を求める京都市実行委員会が発足して、特に京都市の公衆衛生行政の充実を求めるためのシンポジウムの開催や、財源論を含めての提言を出すために委員会を開催しています。今回は第2回で議論された内容を紹介しますね。
「見せかけの人員増では乗り切れない」
公衆衛生行政の充実を求める京都市実行 委員会第2回を8月 26 日に開催しました。 冒頭、保健所・公衆衛生政策をめぐる京 都市の現状について意見を交換。
市が7月 29 日に開催した新型コロナウイルス感染症対策本部会議で、8月1日付で保健師の 体制見直しを発表し、翌日には「8人増加 で体制強化」などと京都新聞で報道されました。しかし実態は、20 年3月末まで新型 コロナの対応を行ってきた部署を、4月の 機構改革で別所属に。兼職をかけたうえで 実質的にはコロナ対応を行っていました。 それを8月に再び同じ所属に戻したという もの。
報告した出席者は「これは増員とは 言わず、体制強化には程遠い」と強く批判 しました。 また別の出席者は、保健師らの時間外労働について、5月以降、職員の大半が月 100 時間を超え、月 200 時間超の職員も複数人いると報告。
現在、PCR検査を受けてから結果が出 るまでの間、患者さんに重篤な症状があれば医師の判断で入院もあり得えますが、無症状の場合はいったん帰宅し、結果がでるまでは自宅待機。結果が出るのは早くても検査日翌日で、陽性の場合はそこから保健師らが調査に入ります。感染症を広げないという観点から時間外労働になってしまいますが、そうした業務を少ない人員で回すために、これだけの過重労働が強いられて います。いつ誰が倒れてもおかしくない状況の中、出席者から体制崩壊に対する強い危機感が示されました。
この問題に対しては、人員増を図ることでしか解決しないと 意見が一致。
毎年見直される定数条例の縛 りや人員増に対する総務省からのプレッシャーをどう跳ね返すかが課題となるとした うえで、実行委員会として人員増の要求を行うことを確認しました。
一方で、ドライブスルー形式のPCR検 査における車の誘導までも、最近まで保健師が担っていました。ようやくアルバイト が雇い入れられましたが、全体的な仕事の中にまだまだ事務的な作業があります。どこまでを事務職、どこまでを専門職が担当するのか、業務スキームの見直しも過重労働解消に向けた課題です。
また、実行委員会では「保健所の抜本的な体制強化を要請するにあたり、市民サー ビス、あるいは市民の新型コロナへの不安にどう応えられるようになるのかなどを打ち出さないと市民の協力は得られないのではないか」といった意見も出されました。
そもそも新型コロナの行政対応においては、市民の殺到やパニックを懸念して帰国者・接触者外来は非公表。感染した場合の治療スキームも不明瞭で、市民に情報が十分に伝わっているとは言えません。これでは市民の不安が解消されるわけがなく、地域住民に対する時時刻刻の情報発信、予防策の啓発等、もしもの時の対応についてア ウトリーチによって理解してもらう取り組 みが必要だと確認しました。
さらに、京都市衛生環境研究所への問題 にも言及。脆弱な体制などと報道されていますが、保健所と一体となって新興感染症対策が行えるよう、予算措置も含めた要求を行うことを確認しました。
今後は京都市の保健師らに対する聞き取り調査、並行して市民アンケートを実施し詳細な実態把握に努めるとともに、11 月1 日に開催するシンポジウムで調査結果の発表を行う予定です。
以上が第2回目の実行委員会の内容です。今後も委員会での議論の内容などを紹介していきたいと思います。
私たちにとってとても大事な保健所をはじめとした公衆衛生行政。その充実こそが、今の新型コロナウイルス感染拡大に対抗できる手段です。さらに今後も発生するであろう新興感染症に対して、十分な備えを今からでも整えていかなければなりません。