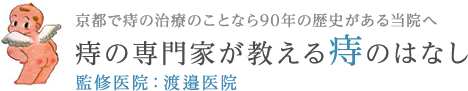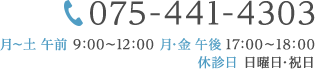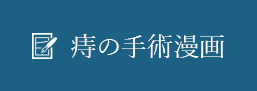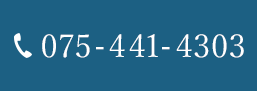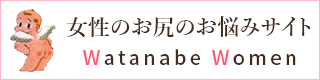肛門の病気以外でも肛門は痛くなることがある。

あちらこちらの桜がたくさん咲き誇ってきています。桜の花の見ごろかなあと思います。

明日の日曜日は残念ながら雨の予報。桜の花を散らしてしまわなければいいなあと思います。もう少し美しい桜の花を楽しんでいたいなあと思います。やはり桜の花を見ると、心ウキウキしてきます。先日、夜桜を見に行きました。今年は、いつもなら大勢の人でにぎわう桜の木の下もひっそり。私たちだけでした。静かに花見。これもまたいいなあと思います。
さて、今回は肛門の痛みに関してお話したいと思います。
外来診療をしていると、「肛門が痛い。」という症状で受診される患者さんが最近多いかなあと思います。肛門が痛い病気には、血栓性外痔核などのように血栓が詰まって晴れていたくなる病気や、肛門周囲膿瘍のように化膿して腫れていたくなる病気もあります。また裂肛のように排便時に便が硬かったり、反対に下痢などで肛門上皮に傷がついたりして痛みがでる病気もあります。でもこれらの病気は痛みの原因がはっきりわかっている病気です。
血栓が詰まって腫れていたい場合は、消炎鎮痛剤の座薬などを使って、腫れをとることで痛みは軽減します。そして血栓は時間とともに溶けて、吸収して治っていきます。場合によっては痛みが強いときは、血栓を手術で摘出すれば痛みは楽になります。肛門周囲膿瘍のように膿がたまった場合は、切開して溜まっている膿を出すことでスッと痛みは楽になります。裂肛は言ってみればけがと一緒です。傷がついた肛門上皮は軟膏などをつけて手当てをして、傷がついてしまう排便の状態を良くすれば治っていきます。
ただ、肛門に痛みを感じる原因はこういった明らかにわかる病気があるだけではありません。ここが肛門の痛みを診察する難しいところです。
肛門に何の病気がなくても、肛門が痛くなることがあります。
その一つは、直腸に便が残ったままになっていたり、便が詰まっていたりする場合です。直腸は便があってはいけないところです。直腸と肛門とで便を出すところです。ですから、直腸に便が残っていたり、詰まったりしてしまっている場合、肛門が痛くなってしまいます。この場合は、スッキリ便を出して、緩下剤などで排便の状態を良くしていくと痛みで悩むことがなくなります。でもこれもある意味、肛門の病気です。
また、肛門の括約筋が強く締まる場合も痛みがでることがあります。
寒い時期に洗浄便座の洗浄を温水で洗うと何ともないのですが、冷たい水で洗うと、痛みが出ます。これは冷たい水が肛門にあたることで、括約筋が収縮して、この収縮が痛く感じたり、冷たい水が当たることで肛門の血液の流れが悪くなったり、肛門が収縮することでもさらに血流が悪くなります。このことが肛門の痛みの原因になります。
人間は寝ているとき以外は、常に肛門は心臓より下にあります。そうするとどうしても夜になると肛門の鬱血が起きてしまいます。このことは避けることはできません。人間が二足歩行をするようになった宿命です。こうした一日の鬱血を解消しようと肛門が収縮することがあります。この収縮が強いときに痛みが出ます。肛門の動きを痛みとして感じることとなります。そしてこの痛みはたいていが夜中、寝ているときにおきます。突然夜中に肛門の痛みを感じて起きてしまうことがあるという患者さんがいます。その原因はこの肛門の収縮です。温めてあげたり、軟膏をつけながら肛門の緊張をとるとよくなります。
さて、肛門とは全く関係なく、肛門が痛くなることがあります。例えば腰の具合が悪いと肛門に痛みが出ることがあります。腰の具合が悪いと、足がしびれたり、歩いていると足が痛くなったりすることがあります。これは腰から足へ行く神経が圧迫されたりすることが原因です。これと同じ理由で、肛門の神経もこしから来ます。腰の具合が悪く、肛門へ行く神経が圧迫されたりすると、痛みが出ます。この場合、立っているときよりも座っているときに肛門に痛みが出ます。これは立っているときよりも、座っているときのほうが腰への負担が大きいからです。こういったことが原因での痛みは、肛門の治療ではなく、腰の治療が必要になってきます。
さらにこれだけでなく、精神的なストレスが強いときも肛門が痛くなることがあるようです。ある肛門科の先生が、肛門が痛いという症状で受診された患者さんに、ストレステストをした際に、ストレスを強く感じている患者さんが多い傾向にあると言っておられました。日常のストレスを解消することも肛門の痛みをとる方法にもなるんだなあと思います。
このように肛門に痛みを感じる場合は、肛門の病気だけではありません。ですから、痛みを症状として受診された患者さんに関しては、いろんなことを想像しながら診察にあたる必要がありますし、痛みの治療はやはり難しい一面もあります。
医師の方も、肛門の痛みに関してはいろんな原因があることを頭に入れて診察する必要があります。そして患者さんの訴えをしっかり受け止めることも、患者さんの痛みの緩和につながるのだと思います。
第4回日本臨床肛門病学会学術集会を終えて。

桜も大分花が開いてきました。今週末には満開になるかなあという勢いです。
自宅近くの桜もきれいに咲いてきました。今年もゆっくり花見はできないかなあと思いますが、妻と二人で、ぷらっと桜の花を見に行きたいなあと思います。
さて、3月21日に第4回日本臨床肛門病学会学術集会が開催されました。今年もwebのみの開催でした。先生方と生の議論が出来ないのが寂しいですし、学会後の懇親会などでの話題提供もとても勉強になるのですが、webだけの学会だとそういったこともなく残念です。
でも、やはり学会は学会!とても勉強になります。またいろんな先生の発表を聞くことで、とても良い刺激を受けます。
今回のテーマは「複雑痔瘻(坐骨直腸窩痔瘻)の手術」でした。
痔瘻は患者さん一人一人すべて違います。ですから、患者さんの痔瘻の原発口、原発巣がどこなのか?そして二次口までの瘻管がどのように伸びているのかを、しっかり診断する必要があります。特に複雑痔瘻の場合は肛門の6時(後方)にできるのですが、その部分はかなり奥深い部分に瘻管が進み、肛門の左右に瘻管が広がっていくパターンが多いです。また二次口が複数ある場合もあり、原発口、原発巣からどのように瘻管が進んでいるのか?どのように枝分かれしていくのかを見極めなければなりません。
その診断に、大きな病院や肛門専門の病院ではMRIや超音波検査などを用いて瘻管の深さや走行を画像で診断し、それをもとに手術を進めていく施設もあります。ただ、そういった画像診断ができない医療機関の方が多いです。そういった場合は、やはり一番頼りになるのが指診です。
肛門指診でどこに原発口があるのか、また、瘻管がどのように進んでいるのかを触診で診断していきます。その触診の方法として双指診があります。
示指を肛門内に入れ、原発口を触知します。そして肛門の外側から親指をあて、示指と親指とで瘻管の走行を診断していきます。二本の指で硬く触れる瘻管をみていくわけです。また左右に広がる瘻管も触診で硬い索状物として触知することが出来ます。また、渡邉医院では肛門周囲の局所麻酔で手術をしていますが、その局所麻酔をする際の針の刺さり具合、刺した時の抵抗、硬さでも瘻管の走行がわかります。やはり瘻管の部分や炎症を起こした部分は麻酔の針を刺す際に硬く感じます。時々側方に痔瘻だと思っていたら、麻酔の際にその針の刺さり具合で、後方から側方へと瘻管が伸びる瘻管とわかる場合もあります。
このようにMRIや超音波検査が無くても痔瘻の瘻管の走行を診断することが出来ます。
また最終的には、手術の際に丁寧に瘻管を剥離していく際に瘻管の走行は解ります。
複雑痔瘻は、深い部分を瘻管が進んでいきます。しっかりとその走行を見極め、一番大切なところは、原発口、原発巣を的確に処理するところにあります。
6時(後方)の方向に原発口があり、左右のいずれか、または両方に瘻管が広がっていく複雑痔瘻の場合は、瘻管を含めて原発口まですべて開放創にすると、かなり大きな傷が出来てしまします。そのような場合はいろいろ工夫が必要となってきます。
複雑痔瘻の原発口、原発巣は6時の後方にあります。ですから、まずは6時の部分から原発巣、原発口を処理して開放創にする。
そして後方から側方に伸びる瘻管に対しては、瘻管内を掻把して不良肉芽を十分に取り除くだけで留めたり、二次口から6時の部分まで瘻管をくり抜いていく方法であったり、一端すべてを開放創にして、後方だけ開放創にして十分なドレナージをおき、側方のいったん開放創となった創は縫合して閉鎖するなどの方法があります。
傷が大きくなると、やはり治癒までの期間が長くなります。必要な傷はしっかり形よく残し、それ以外は縫合したり瘻管だけをくり抜いたり、掻把するだけにして、できるだけ傷を小さくすることによって治癒までの期間を短縮することが出来ます。その方法の選択にやはり経験が必要になってくると思います。
また、痔瘻の手術に関してお話する際に、いつもお話しているのが痔瘻の手術のジレンマ「機能温存と根治性」という相反する課題をどうするかにあります。
やはりそこに痔瘻の手術の難しさがあると思います。
赤ちゃんも、肛門周囲膿瘍や痔瘻になるの?

あちらこちらに桜が咲き始めました。今年は早く開花しましたね。渡邉医院の近くの千本今出川の交差点にある桜も、だいぶ花が開いてきました。この連休、日曜日は雨のようなので、明日、チョット桜の咲き具合を診てこようかなあと思います。
さて、今日診療所には赤ちゃんと一緒に受診された患者さんが多かったです。授乳できる部屋もあるので、遠慮なく赤ちゃんと一緒に受診して下さいね。
赤ちゃん連れが多かったので、今日は少し赤ちゃんの肛門の病気に関してお話しようと思います。
赤ちゃんも肛門の具合が悪くなることがあります。便が硬かったり、げりで肛門に傷がつく裂肛になったり、外痔核が腫れたりすることも有ります。でもいずれも便の調整をして、具合よく便が出るようになると治っていきます。
さて、赤ちゃんも肛門周囲膿瘍や痔瘻になることがあります。
原因は大人と一緒で、肛門腺に細菌感染を起こして化膿してきます。赤ちゃんの場合も、肛門周囲膿瘍になった場合は、切開して膿を出す必要があります。膿を出した後に痔瘻になっていく場合があります。
赤ちゃんにできる痔瘻を乳児痔瘻と言います。乳児痔瘻は男の子に多いです。そして、大人の場合は肛門の後方にできやすいのですが、乳児痔瘻の場合は、肛門の左右にできることが多いです。ここは大人と違うところです。生後1か月前後から1歳ぐらいの乳児期の赤ちゃんに比較的多くみられます。決して稀な病気ではありません。乳児期の不完全な免疫力が関係しているとも言われています。下痢や軟便が続いた後に、肛門の周囲が赤く腫れてきて膿を持つようになります。このような場合は乳児であっても切開して膿を出す必要があります。そしてその後、痔瘻になる場合があります。
でも大人と違って、痔瘻になっても赤ちゃんの成長と共に、1~2歳になるころには自然に治っていくことが多いです。これは乳児の時に痔瘻になっても成長と共に肛門も成長するとともに瘻管ふさがって、がなくなっていくことがあるからのようです。
赤ちゃんのお尻が腫れあがり、赤ちゃんも不機嫌になる。膿が出て痔瘻になる。お母さんにとってはとても不安になると思います。でも、肛門周囲膿瘍の場合は切開して膿を出す必要がありますが、痔瘻になっても、ほとんどの赤ちゃんは、1~2歳になるころまでには手術をしなくても自然に治っていきます。一部、2歳以上になっても痔瘻が治らない場合があります。でも慌てて手術する必要はありません。お子さんが大きくなってから手術で治しても全然遅くありません。
心配な時は、肛門科を受診して、医師と相談してみて下さいね。
「さくらづくし」の4月の献立を紹介します。

4月は『「さくら」満開』をテーマにレシピを紹介してきました。
あちらこちらで、桜の開花宣言が出るようになりました。非常事態宣言とは全く逆の、心ウキウキ楽しくなる宣言ですよね。京都はまだのようですが、今日のような良い天気だともうすぐかなあと思います。皆での花見はできませんが、それでも桜、楽しみたいなあと思います。

今日は昨日と違って、冷たい風もなく、本当に過ごしやすくなってきました。院長室の窓も開けたままでも、暖房を入れなくても過ごせるぐらいです。
そんな天気にも触発されて、午前中の外来が終って、手術のあと、院長室の掃除をしました。いらないものは捨て、整理して、掃除機をかけると本当にスッキリしました。確定申告のための書類等がありますが、確定申告が終るとこれもスッキリします。
スッキリすると、何時もは廊下に置いてある机をzoomの会議や食事をするときに院長室の中に運び込んで使っています。狭い院長室ですが、小さくていいので、机が欲しくなってしまいます。今度の休みにはチョット探しに行ってこようかなあと思います。
また、いつもお世話になっている飲み屋さんに、レトロな小さな引き出しがあります。診察室の祖父からもらった机の上における程度のレトロな引き出しがあれば、文房具や判子類をしまえるのになあと思い、そんなレトロな引き出しも探しに行きたいなあと思いました。やっぱり春という季節が、そんな思いを引き起こさせるのかなあと思いました。
さて、4月のレシピの取りは、今まで紹介してきたレシピを使っての献立です。
『「さくら」満開』の取りを務めるにもってこいの「さくらづくし」のメニューです。
是非作ってみて下さいね。4月の献立は全7品です。
4月の献立

・桜鯛の塩焼き くず仕立て
・たこの桜煮
・桜肉のレアカツ
・ささみの桜漬け巻き
・桜漬けと枝豆のおにぎり
・桜えびと切干大根の塩昆布和え
・桜ごま豆腐 桜餅風
「「桜えびと千切り大根の塩昆布和え」と「桜ごま豆腐 桜餅風」のレシピを紹介します。

4月のレシピは『さくら』まんかい 」をテーマに紹介しています。
4月第五弾は「桜えびと千切り大根の塩昆布和え」と「桜ごま豆腐 桜餅風」のレシピを紹介します。
「桜えび」の名前の由来には、①干し桜えびの色が桜の花を撒いた様に美しい。②春の時期に収穫されること。③桜色に由来する等様々な説があるようです。

この写真を見ると、桜色した桜えびがたくさんあると、本当に桜の花を撒いたような、そんなイメージを持ちますよね。
桜えびは丸ごと食べることが出来ます。ですから、手軽にカルシウムを沢山摂ることができます。また食物繊維も豊富なんですね。
桜えびのから揚げや、おうどんにトッピングしたり、パスタにも合うようです。
もう一つの「桜ごま豆腐 桜餅風」ですが、「吉野のさくら風ごま豆腐」というのが売っているんですね。吉野のさくら風ごま豆腐を使ったパフェなんかもあるんですね。ごま豆腐ですが、スウィーツになるんですね。私はまだ食べたことは有りません。一度食べてみたいと思います。スーパーなどで、どこにでも売っているんでしょうか?探してみますね。
今回はチョット前置きが短いですが、そろそろレシピを紹介しますね。
「桜えびと千切り大根の塩昆布和え」

1人分 約35kcal 食物繊維 1.3g
材料(2人分)
切干大根 10g
さくらえび 5g
塩昆布 3g
ごま油 小さじ1/2
作り方
①切干大根を洗ってから5分水につけて軽く絞る。
②全ての材料を混ぜる。*少し時間を置いた方がおいしいです。
「桜ごま豆腐 桜餅風」

1人分 約40kcal
材料(4人分)
吉野のさくら風ごま豆腐 1個
粒あん 大さじ2
水 適宜
作り方
①さくら風ごま豆腐を4つに切り器に盛る。
②粒あんを水でのばし①にかける。
「桜鯛の塩焼きくず仕立て」のレシピを紹介します。

4月のレシピは『「さくら」満開』をテーマに紹介しています。
今回、第四弾は「桜鯛の塩焼き くず仕立て」のレシピを紹介します。
今日は昨日と打って変わって、いい天気になりました。上着を着て外を歩いていると熱いぐらいでした。
玄関前には花が咲いていました。春ですね!


またふと空を見てみると、チョット崩れた日本地図のような雲。思わず写真を撮ってみました。

久しぶりに少し散歩。これから段々温かくなってきます。皆で花見はできませんが、お弁当を持って外で食べるのもいいですね。
今回のレシピには、筍を使っています。以前、患者さんがたくさんの筍を持ってきてくださったことを思い出します。筍も焼いたり茹でたり、また筍ご飯も美味しいですよね。そうそう天ぷらも美味しいですね。
今日の主役は桜鯛です。後で管理栄養士さんからの一言で紹介しますが、私も少しだけ、桜鯛のことを調べてみました。
桜鯛と真鯛は同じ魚です。真鯛は今の時期から初夏にかけて産卵を迎えるためにたくさんの餌を3月の初旬ごろから食べるようになります。雄の真鯛は繁殖を控えて、体の色が段々桜色になってきます。ちょうど桜が咲く時期に、体の色が桜色になる。このことから桜咲くころの真鯛を桜鯛と呼ぶようになったという説があるそうです。
この時期にやはり桜鯛を食べるのが一番ですね。
ではそろそろレシピを紹介しますね。
「桜鯛の塩焼きくず仕立て」

(1人分)エネルギー 約100kcal たんぱく質 18g 食物繊維 4g
材料(2人分)
桜鯛 1匹
ゆでたけのこ 1本
わかめ 40g
★出し 約500ml
★酒 大さじ2
★薄口しょうゆ 大さじ1
★みりん 小さじ2
片栗粉 大さじ1~2
作り方
- ①桜鯛は塩をして10分置く。
- ②たけのこは★で煮る。わかめもさっと煮て取り出しておく。
- ③①と②の水気をふき取って焼く。
- ④②の汁に同量の水で溶いた片栗粉でとろみをつける。
- ⑤器にわかめと③を盛り付け④をかける。
- 管理栄養士さんからの一言
-
桜鯛
この時期の小型の真鯛が桜鯛と呼ばれているようです。由来は諸説ありますが、「桜の咲くころに旬を迎えるから」「旬の雄の体に現れる模様が桜の花びらのようだから」「雌の体の色が桜色だから」など桜をこよなく愛する名前だと思います。
鯛は良質のたんぱく質を豊富に含み、脂質が少ないので低エネルギーの魚です。見た目の華やかさと栄養を兼ね備えています。
「たこの桜煮」のレシピを紹介します。

4月のレシピは『「さくら」満開』をテーマに紹介しています。
4月のレシピ第三弾は「たこの桜煮」です。
「たこ」と言えば、一番最初に出てきたのは「たこ焼き」です。私の家にもたこ焼き器があって、まだ子供たちが社会人になる前は、休みの日などに作って食べていました。外がカリッとしていて中はとろとろフワフワが美味しいですよね。今ではもう違うと思いますが、私が大学に入学したころ、40年も前のことになります。東京の下宿していた近くの商店街でたこ焼きを売っていたので買って食べてみると、なんかホットケーキのような食感で、関西と全然違うと感じました。学園祭の時は、大阪から来ていた同級生がいたので、外がカリッとして中はとろとろフワフワのたこ焼きを作って売りました。結構好評だったのを憶えています。
また、私は、たこが好きで、お寿司屋さんに行ったときは必ずたこの握りを注文します。甘いたれがかかっているのも美味しいですよね。
たこ飯もいいですね。たこのコリっとした食感がいいのかもしれません。噛めば噛むほど味が出る。そんなところがいいのかなあと思います。
今回のレシピはたこの桜煮、甘煮とも言うそうです。お酒のつまみにもいいですし、ご飯にも合います。後で管理栄養士さんからの一言でも紹介しますが、たこと小豆は相性がいいそうです。小豆はたこを柔らかくしてくれるそうです。そして「桜煮」とあるように、たこの色も鮮やかな桜色にしてくれます。
イイダコの丸ごと「桜煮」もいいですよね。私は、たこの足のところが好きです。
ではそろそろレシピを紹介しますね。
「たこの桜煮」

材料(作りやすい分量)
ゆでだこ 300g
★大根のしぼり汁 100㏄
★小豆 大さじ2
★酒 大さじ2
◇砂糖 小さじ1/2
◇みりん 小さじ1
◇醤油 少々
作り方
- ①ゆでだこを1本ずつ切りさっとゆでて洗う。
- ②鍋に★と①とかぶるくらいの水を入れ、おとしぶたをして軟らかくなるまで煮 る。一度沸騰したら火を弱めてぐらぐら踊らないように注意する。
- ③◇を入れさらに10分煮る。そのまま冷ます。
*冷ます間に味が染み込みます。
④ 食べやすい大きさに切って盛り付けます。
管理栄養士さんから一言
たこの桜煮
たこを小豆と煮ることできれいな桜色になるのが名前の由来のようです。他にも番茶で煮る方法もあります。また軟らかく煮る方法には、大根でたたく・炭酸を使うなどもあります。
たこはたんぱく質を豊富に含み疲労回復効果のあるタウリン・皮膚の健康や味覚に影響のある亜鉛・ビタミンE・B12も多く含みます。
「ささみの桜漬け巻」と「桜漬けと枝豆のおにぎり」のレシピを紹介します。

4月のレシピのテーマは『「さくら」満開』です。いろんな食材に「桜」の名前の付いたものがあります。
今回は「桜漬け大根」を使ったレシピを紹介します。
「桜漬け」と検索すると、「桜漬け」と「桜漬け大根」が出てきます。
今回使うのは「桜漬け大根」です。「桜漬け大根」は大根を梅酢に漬けたお漬物です。「桜」というよりは「梅」ですね。見た目が桜の花びらに似ているから「桜漬け」とつくのでしょう。
さて、もう一つの「桜漬け」に関して少し調べてみました。

桜漬けを調べてみると、桜漬けは、一般的には八重桜の花びらを摘み取って塩漬けにしたものです。桜漬けは「桜湯」にして飲まれることも有ります。やはり「春」をイメージするものですね。桜漬けの作り方は検索するとすぐに出てきます。今年も皆で花見で宴会が出来ないのであれば、「桜漬け」を作ってみるのもいいかもしれませんね。そして自分で作った「桜漬け」で「桜湯」を作ったり、今日のレシピを作って春を楽しむのもいいなあと思います。
私の生活は、自粛する前から、自宅と母の家そして診療所。この三つを行ったり来たりしているだけで、ほとんど外に出ることは有りません。診療所には朝の7時30分頃にに行って、その後、夕方の6時までずっと診療所にいます。仕事が終わるとそのまま自宅に帰るか、母をデイサービスに迎えに行ったり。本当にコロナ禍以前から、全く外に出る生活ではありませんでした。そんな生活をしていると、たまにはおにぎりを握ってお弁当を持って外の空気を吸ってゆっくりと自然を漢字ながらご飯が食べたい!といった気分になります。
今回のレシピはそんな願いをかなえてくれるレシピだと思います。
まだ外でお弁当を食べるのには寒いです。もう少し温かくなったら、お弁当を持って出かけたいなあと思います。春ってそんな気持ちにしてくれる季節ですよね。
ではそろそろ「桜漬け大根」を使ったレシピを紹介しますね。
「ささみの桜漬け巻」

1人分 約70kcal たんぱく質 12g 食物繊維 1g
材料(2人分)
ささみ 2本
塩胡椒
アスパラ 1本
桜漬け 20g
きゃべつ(千切り)
作り方
- ①ささみは筋をとってラップにはさみ綿棒でたたいて薄くのばす。
- ②アスパラは半分に切ってゆでる。
- ③①に塩胡椒し、②と桜漬けを巻く。
- ④巻き終わりを下にしてフライパンで転がしながら焼く。
- ⑤食べやすく切ってきゃべつの千切りと盛る。
「桜漬けと枝豆のおにぎり」

ご飯180g、枝豆 30g、桜漬け 20g
①ご飯に刻んだ桜漬けと枝豆(冷凍むき身を戻したもの)を混ぜる。
②おにぎりにする。
「桜肉のレアカツ」のレシピを紹介します。

3月ももうすぐ2週間が過ぎます。桜の花がもう開いたというニュースを早くも効く様になりました。今年の桜の開花は早いそうです。

残念ですが、今年も去年同様に皆でお花見、そして宴会はできないと思います。でも綺麗に咲き誇る桜を身近な人と見に行くことはできると思います。少し寂しいですが、でも華やかに咲いた桜を見て、春を感じたいものです。
私の父は11年前の8月9日に他界しました。実家に近くの平野神社の桜が咲くのを楽しみにしながら亡くなりました。桜が咲く時期、父の事、そして東日本大震災のことを思い出しながらの花見になります。今年の桜。私に何を伝えてくれるでしょうか。
4月のレシピのテーマは『「さくら」満開』です。桜をテーマにレシピを作っていただきました。
まずは管理栄養士さんからのメッセージを紹介しますね。
『さて、今回は「さくら」満開です。
今年は桜の開花は早くなりそうですが桜の下でのお花見は難しそうです。せめて食卓だけでも「さくら」をめでて楽しんでいただけたらと、「さくら」のつくものを集めてみました。本当に桜を使っているものはないのに名前にはさくらの入っているものばかりです。古来、ただ好きなだけでなく強いあこがれや期待を持っているのだと改めて感じました。新生活のスタートで体調も崩しやすい時期ですが、まずは「食べること」で生活のリズムを作ることが大切だと思います。「楽しく」「おいしく」食べることで栄養の吸収も違ってくるそうです。』
4月のレシピ第一弾は「桜肉のレアカツ」です。
馬肉のことをどうして桜肉というのか?後で管理栄養士さんからの一言でしょうかいしますが少し追加したいと思います。
江戸時代に、猪肉は「牡丹」、鹿肉は「紅葉」と呼ばれていたそうです。そこに、馬肉を切った際に、桜色の様にみえたところから「桜」の名前が付いたという説があるそうです。馬は、冬場にしっかり餌をを食べて、桜の咲く春には脂がのって美味しくなることから「桜肉」と呼ばれるようになったという説もあるそうです。
ほかにもいろんな説があるようです、一度調べてみて下さいね。
馬肉を勝にしたものは私は食べたことがありません。馬肉というと「馬刺し」、生姜醤油でしか食べたことが無いと思います。今度は馬肉をカツにして食べてみようと思います。
では、レシピを紹介しますね。
「桜肉のレアカツ」

(1人分)エネルギー 約160kcal たんぱく質 13g 鉄 2.7g
材料(2人分)
馬刺し用馬肉 120g
塩胡椒
★小麦粉 大さじ1
★牛乳 大さじ2
パン粉 大さじ2
サラダ油
さくらかいわれ 適宜
生姜(すりおろし)大さじ1
醤油 大さじ1
作り方
- ①馬肉に塩胡椒し水気を取る。
- ②★を混ぜて①の表面につけパン粉をつけて揚げ焼きにする。
*生食用なので衣に火を通す。
③カットし、かいわれをのせ、生姜醤油を添えます。
*マスタードマヨやにんにく醤油もおいしいです。
管理栄養士さんから一言
桜肉(馬肉)
馬肉を「桜肉」とも呼びます。由来は諸説あり、「肉の色が桜色だから」「桜の咲くころは脂がのっておいしいから」「江戸時代は獣肉を食べることが禁止されていたので隠語として桜と呼ばれた」「幕府直轄の牧場が佐倉にあったから」他にもたくさんありそうです。
栄養面では他の肉に比べるとたんぱく質が豊富で脂質が少なく生活習慣病予防に、鉄分を多く含み貧血予防、グリコーゲンも豊富で疲労回復効果が期待できます。
父との想い出。

今日、3月8日は父の命日です。11年前の今日、父はなくなりました。
父の一周忌を行った次の日に東日本大震災が起きました。父の死、東日本大震災、ともに忘れることのできない3月です。また、父は桜が咲くのを楽しみにしながら亡くなっていきました。美しい桜の花の開花と共に、父の死を思い出します。
さて、私にとって父の存在は、なんとなく近づき難い存在でした。話しかけていいものかどうか。父と話しをする際は朝、学校に行く前に「今日、帰ってきたら話を聞いてもらえますか?」とアポを取っていたような記憶があります。
そもそも父は京都に帰ってきて祖父の肛門科を継承するまでは、山梨県の甲府市の市立病院で外科部長をしていました。朝早く出かけて、夜遅く帰ってくる。京都に帰ってくるまでは、私の生活の中には父はあまりいませんでした。母と私と妹の3人の生活だったような気がします。
小学生のころ、小学校に提出する書類の保護者名を書くところに、母は自分の名前を書いたそうです。そうすると学校から「保護者の欄にお母様のお名前が書かれていますが、お父様はどうされているのですか?」と聞かれたそうです。母はその質問に、「私の子供をいつもみて、保護しているのは私です。夫は経済的に私たちの生活を守っているので、子供の保護者は私です。」と。ウーンわかるような気もしますが、学校からは保護者の欄にはお父様の名前を書いて提出してくださいと言われたそうです。こんな感じで、京都に帰ってくるまでは、母と私、そして妹の3人の生活といった感じでした。ですからあまり父とは話すことがありませんでした。
たまに、母のいない日に、学校の帰り道、父が勤務している病院の医局に行って、父と一緒に病院の近くの食堂に行って一緒に食べたことがあります。病院の前のうどん屋さんだったか、そこで牛丼を食べたのを憶えています。たまに休みの日に父がいるときは、キャッチボールや、その時買っていた甲斐犬の散歩に行ったぐらいかなあと思います。一緒に旅行に行ったことも有りません。まあ、これが医者の家庭かなあと思っています。
そんな父と、一番頻回に会話をしてかかわったのが、高校生の時です。
スポーツが大好きだった私が、左の膝を怪我をして、しばらく杖を突いて歩いていた時がありました。その頃はまだまだ若かったので、「スポーツが出来ない足なんかいらない!」と言ってストーブを蹴飛ばしたりして、少し荒れていた時がありました。そんな時、父が一言、「お前の悔しさは解らないが、お前はそんなお前の姿を見ている母親の気持ちがわかるのか!」と。この一言、頭を思いっきりガーンと殴られたような気がしました。自分勝手だった私をしっかり見つめることが出来ました。その言葉の後は、自分の気持ちを抑えることが出来るようになりました。
そのような私を見て、毎週日曜日には嵐山にボートを漕ぎに行くようになりました。少しぐらいの雪の日も行きました。毎週行くので、船頭さんたちにも覚えてもらえるぐらいになりました。
父は海軍兵学校に行っていました。ボートの漕ぎ方は抜群。オールの水への入れ方、かきかた、そして水からの出し方を、しっかり教えてくれました。
私自身もボートの漕ぎ方も上達して、かなり上流へと行くことが出来るようになりました。ところどころ、岩場に入って休憩したり、そこで咲いているのスミレの花を見つけたりしました。そのスミレを母に持って帰ったり。そのスミレの思い出が母に「スミレの便り」というエッセイを書くきっかけになりました。
今でも、渡邉医院の中庭に小さなスミレが咲きます。そんな時はその時のことを思い出します。
ボートを漕ぎ終えた後は、毎回父と二人で昼食を摂りました。何ともない会話をして過ごす。なんとなく、父と近くなった気がしたものです。
こんな風にして、父との繋がりが強くなったのを、今思い返します。