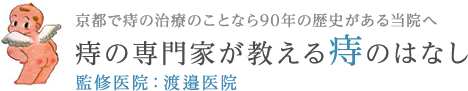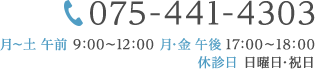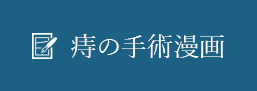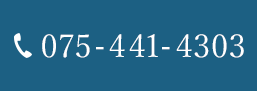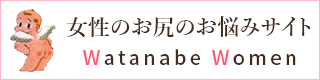第74回日本大腸肛門病学会総会に向けて。

ここ数日グッと冷え込んでますね。そろそろ寒さもピーク、明日からは段々温かくなるようですね。この寒さで、桜もこの週末が満開で見ごろかなと思います。私はまだ、お花見に行っていません。今週どこかで行きたいと思っています。
さて、今年の日本大腸肛門病学会は10月11日から10月12日の二日間、東京のヒルトン東京お台場で開催されます。今回のテーマは「こだわり KODAWARI-Show your originality!」です。今回も参加しようと思います。

今回は例年より1か月早い10月の開催です。そのため、学会での発表内容の抄録の締め切りが3月末でした。
今年も発表しようと思い、抄録をつくり送りました。抄録が採用されるかどうかはまだわかりませんが、今回の発表内容について少し紹介しようと思います。
今回は痔瘻に関しての発表をしようと思い、渡邉医院のデーターを調べ抄録を作りました。
演題名は「痔瘻に対して手術を施行した889例の部位別最大肛門静止圧の比較検討」です。
痔瘻の患者さんは、最大肛門静止圧が高い傾向にあります。最大肛門静止圧が高いということは、内肛門括約筋の緊張が強い、すなわち肛門の締まりが強いということです。こういったこともあって、痔瘻はどちらかというと男性に多く発生します。渡邉医院でも、約7対1の割合で男性に多いです。また年齢的にも若年者に多く発生します。
痔瘻の多くは肛門の後方に発生しますが、側方や前方にも発生することがあります。今回は痔瘻の発生部位で最大肛門静止圧に差があるのか、ないのかを比較検討しました。
検討する前の予測としては、後方に痔瘻が発生した患者さんの方が、側方や前方に痔瘻が発生する患者さんよりも最大肛門静止圧が高いのではないか。したがって、後方の痔瘻の手術をするとき以上に側方や前方の痔瘻の手術をする際には、機能の温存に注意しながら手術をしなければならないのではないかという仮説の元で検討しました。
結果としては後方も側方も前方も、最大肛門静止圧には有意な差はありませんでした。ただやはり男性の患者さんの方が女性と比較して最大肛門静止圧は高い傾向にありました。このことから、女性の痔瘻の手術をする際は男性と比較して機能の温存により注意しながら手術をする必要があります。また、後方、側方、前方とも最大肛門静止圧には差がありませんが、解剖学的に部位によって肛門は状況が違ってきます。こういったことからも側方や前方の痔瘻に対して手術する際には機能面や手術による肛門の形態的な面に注意しながら手術を施行していく必要があると考えます。
まだ採用されるかわかりませんが、抄録を紹介します。また詳しい内容やパワーポイントなどはまた紹介しますね。
抄録
日常の診療を行うにあたって、痔瘻は肛門の締まりが強い患者に多い印象がある。実際、痔瘻において、最大肛門静止圧が高く、若い男性に多く発生するのも、このことに起因すると考える。今回、痔瘻の発生部位によって、最大肛門静止圧に差があるのかについて検討した。【対象】平成10年10月から平成31年2月までに痔瘻の手術をした889例(男性778例、平均年齢41.0歳。女性111例、平均年齢42.4歳)を対象とした。【方法】痔瘻の発生部位を前方(11時、12時、1時)、後方(5時、6時、7時)、側方(2時、3時、4時、8時、9時、10時)に分け、それぞれの最大肛門静止圧について比較検討した。【結果】889例中男性は788例、87.7%。女性は111例、12.3%と圧倒的に男性に多かった。男性において発生部位を比較すると、前方105例、13.3%。後方526例、66.8%。側方157例、19.9%と後方が全体の約70%を占めた。これに対して女性では、前方29例、26.2%。後方55例、49.5%。側方27例、24.3%と男性と比較して後方が全体の約50%を占めるものの、発生率が少なかった。年齢について比較すると、男性では、前方41.0歳、後方42.8歳、側方39.3歳と側方でやや年齢が低い印象はあるが明らかな差は認めなかった。女性では前方42.3歳、後方43.3歳、側方41.6歳と各部位で明らかな差は認めなかった。また男女差も認めなかった。次に、男性女性の痔瘻発生部位別の最大肛門静止圧を比較すると、男性では、前方127.5mmHg、後方127.7mmHg、側方125.2mmHgと側方でやや低い傾向はあるものの、それぞれの部位で明らかな差は認めなかった。女性においては、前方98.0mmHg、後方84.8mmHg、側方93.6mmHgと男性と比べてすべての部位の最大静止圧は低く、また後方の最大静止圧がやや低い傾向にあるが、明らかな差は認めなかった。【考察】今回、痔瘻の発生部位別の最大肛門静止圧を比較検討する際に、側方の痔瘻において最大肛門静止圧が後方より低いのではないかと考えていたが、結果は各部位とも男女とも最大肛門静止圧に明らかな差は認めなかった。ただ男性と女性の最大肛門静止圧をみると、明らかに女性の方が低く、女性の痔瘻に対して痔瘻根治術を施行する場合は、より術後の機能温存に注意を払い手術を施行する必要があると考える。
「内痔核の治療の現状」内痔核治療研究会からのアンケート依頼を受けて。

今日から4月になりました。新しい元号も「令和」と決まりました。新しい時代へと向かうことになります。「令和」という時代が、私たちにとって良き時代になるよう、私たち自身が取り組んでいかなければならないと思います。
内痔核の治療の現状
話はガラッとかわりますが、内痔核治療法研究会から内痔核の治療に関するアンケートを依頼されました。どのような体位で診察、手術をしているか?肛門鏡検査にはどのような肛門鏡を使用しているか?内痔核の治療方法は?手術方法は?入院日数は何日か?など26項目にわたってのアンケートでした。この結果は、7月21日に東京で開催される第13回内痔核治療法研究会で「日本国内における内痔核治療の現状」でまとめられたものが報告されます。また、この報告については、その内容を皆さんにご報告しようと思います。
渡邉医院の現状
渡邉医院では、診察や手術の時の体位は左側臥位で行っています。肛門鏡は筒型の肛門鏡を主に使っています。入院日数は病気の種類や手術の方法で異なってきます。内痔核に対して痔核根治術をする場合は1泊2日~3泊4日。ジオンによる痔核硬化療法では1泊2日です。ただ患者さんの状況などを考えて日帰り手術を行う場合もあります。病気の状態や手術の方法、そして患者さんの状況などを合わせて入院日数や日帰り手術にするか患者さんと一緒に決めています。また外痔核や皮垂に関しては、術後1時間程度休んでもらって、傷の状態をみてから自宅に帰ってもらっています。
今日は、このアンケートのなかで、平成30年の1月から12月までの1年間での患者さんの数や、手術件数を紹介したいと思います。
平成30年1月1日~12月31日までの渡邉医院の状況
渡邉医院に去年1年間で受診された患者さんの総数は8566人でした。そのうち、男性は4310人、女性は4256人と、渡邉医院では男性と女性の受診者数に差はありませんでした。
世間一般では、肛門科を受診する患者さんは男性のほうが多いと思われているようですが、そうではなく、男女ともほぼ同じという結果でした。
また、「痔核」の手術を受けられた患者さんは、全部で523人で、男性が229人、女性が294人と、手術件数ではやや女性の患者さんに多いかなと思いますが、あまり大きな差は男女間ではありませんでした。また肛門科を受診された患者さんのうち痔核に対して手術をした割合は、全体では6.1%、男性は5.3%、女性では6.9%と、女性にやや痔核に対して手術する割合が高いかなという印象です。
ただ、内痔核に対してどのような手術をしたか、その手術内容を比較すると、男性と女性では大きく差がでました。
これに関しては以前学会でも発表したことがありますが、ジオンという痔核硬化剤での四段階注射法での痔核硬化療法は、男性が123人に対して、女性は47人と男性に多い結果でした。これに反して、痔核根治術は、男性は98人に対して、女性が156人と女性に多い結果でした。また皮垂を含めて外痔核に対しての手術は男性が8人に対して女性は91人と女性に多い結果となりました。やはり、内痔核の性状でジオンによる痔核硬化療法や痔核根治術の適応を決めるのですが、男性ではジオンによる痔核硬化療法が有効な内痔核が多く、女性では、このジオンによる痔核硬化療法が有効ではない内痔核が多く発生するということだと思います。したがって、男性と女性では、内痔核のできる要因、できかたに何かさがあるのか?もしくは解剖学的な違いによって内痔核の性状が異なってくるのか?このことに関してはさらに検討していく必要があると思います。
ちなみに去年1年間で痔瘻の手術は86人、男性73人、女性13人。裂肛の手術は、男性17人、女性が29人でした。
第3回日本臨床肛門病学会を終えて。

もうすぐ4月になります。あちらこちらで桜も開花して、満開の声も聞こえてきます。いよいよお花見のシーズンになります。今日はチョット雨で、桜の花が散らないことを祈ります。皆さんもお花見などいろいろ予定が入っていると思います。また入学式や入社式。新たな旅立ちに向けて心ワクワクされている方も多いと思います。
今日は、先日3月17日に東京の新宿で開催された、第3回日本臨床肛門病学会に参加して感じたことや、今後検討していかなければならないと思うところをお話したいと思います。
学会のテーマは「低位筋間痔瘻の手術」
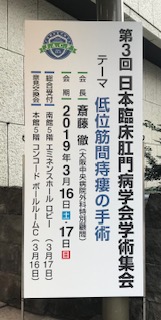 さて、今回の臨床肛門病学会のテーマは「低位筋間痔瘻の手術」でした。
さて、今回の臨床肛門病学会のテーマは「低位筋間痔瘻の手術」でした。
痔瘻は肛門上皮と直腸粘膜との境目にある肛門腺の感染から発生します。Crypt-glandular infection(肛門陰窩肛門腺感染)によって発生して、Anal crypt(肛門陰窩)から侵入した細菌がanal duct(肛門腺管)を通じて内外括約筋間のanal gland(肛門腺)に感染巣を形成することで痔瘻が形成されていきます。したがって、痔瘻を根治させるのには、細菌の侵入口である原発口を確実に処理することが必要です。したがって、痔瘻を根治させるのには、原発口、原発口から原発巣までの瘻管、そして原発巣を切除するか、開放創にする必要があります。
痔瘻の手術のジレンマ

ここで問題になってくるのが、痔瘻が肛門陰窩から始まり、内肛門括約筋を貫いて二次口に到達するので、どうしても痔瘻の手術では括約筋の損傷を伴うことです。したがって、痔瘻の手術においては根治性を高めるか、括約筋の機能を温存するか、のこの二つを天秤にかけて、どう手術をしていくかを判断しなければなりません。原発口、原発巣、瘻管をごっそり大きく切除すれば、痔瘻の手術の根治度は高まり、再発はしません。ですが、括約筋を大きく損傷することは肛門の機能面に関しては大きなダメージを与えてしまいます。反対に機能を重視して、十分に原発口、原発巣、瘻管の処置が出来ていなければ、機能は温存されますが、再発する可能性が高くなってしまいます。この二つのジレンマが痔瘻の手術には付きまとってきます。
この問題に対して、今回の臨床肛門病学会ではさまざまな意見交換がありました。
「切開開放術」・「seton法」
今回の臨床肛門病学会はシンポジウム形式で、前半は「切開開放術」、「seton法」に関するシンポジウムでした。切開開放術もseton法もいずれも方法は違い、できる傷や治り方は違いますが、原発口、瘻管を処理して切除する方法です。切開開放術はやはり低位筋間痔瘻に対しての手術手技の基本となる手術術式です。これをしっかりマスターしていくことが大切です。この手術手技がしっかりできることで、seton法も確実におこなえると考えます。いずれの術式も、しっかりと原発口を確認して、原発巣、そして瘻管を摘出することが重要です。Seton法は特に原発口、原発巣、そして瘻管に確実に輪ゴムがかからなければ治すことができません。確実な診断能力と確実に輪ゴムをかける手技が要求されます。
切開開放術もseton法もいずれも内肛門括約筋の損傷を伴います。できるだけその損傷を最小限にとどめる手術が必要になります。
「括約筋温存手術」
後半は「括約筋温存手術」についてのシンポジウムでした。括約筋温存手術は様々な方法が考えられ、試みられています。基本は内肛門括約筋を貫く瘻管は残して原発巣を処理するという手術です。ただ、この術式ですと、どうしても内肛門括約筋内に瘻管が残ること、原発口が残ることなど、再発の可能性があるのではないかと考えます。これらの術式に関しては、今後の長期生成期がどうなっていくのか?長期にフォローすることで、どの程度の再発率なのかをしっかりと検討していく必要があります。
今後の痔瘻の手術
今回の臨床肛門病学会で感じたことは、痔瘻の手術に関しては、手術の根治性と機能温存という相反する命題をいかに解決していくかが重要な課題となること。そしてそれを満たす手術術式を確立させること。また、その手術が特殊な手術ではなく、標準的な手術となるような術式でなければならないということです。このことを目標に、今後も痔瘻の手術はさらに検討が進めれれていくと思います。
3月の献立を紹介します。

今日は一気に3月のレシピを紹介してきましたが、最後に3月のレシピを使って、早春のメニューとして3月の献立を紹介しますね。
今月の献立のメニューは、鮭のメレンゲ焼き、あさりと豆苗の炒め物、春の天ぷら(筍・若ごぼう・菜の花)、
タケノコの白和え、新玉ねぎのレンジ蒸し、竹の子ちらし、わかめ煮の計7品の献立です。とても豪華な献立になっています。一度作ってみて下さいね。

「竹の子のだし煮」のレシピも紹介しておきます。
「竹の子のだし煮」
竹の子 1本
だし
薄口しょうゆ 少々
塩 適宜
みりん
またはめんつゆ
作り方
1. たけのこは下のほうと穂先と分け、食べやすい大きさに切る。
2. 調味料を入れただし、またはめんつゆで落し蓋をして煮る。そのまま冷ます。
*この煮物を天ぷら・白和え・ちらし寿司に使います。
管理栄養士さんからの一言
たけのこの栄養
たけのこは野菜のなかでもたんぱく質が多く、カリウム・食物繊維も多く含まれています。
ゆでたけのこについている白い粉もチロシンというアミノ酸の1種です。
やる気の素になるといわれています。
ゆでたけのことして1年中出回りますが、生のたけのこはこの時期だけのおいしさです。
ぬかや米のとぎ汁やお米少量と一緒に水からゆで、そのまま冷めるまで置いて使います。
「たけのこの白和え」のレシピを紹介します。

3月最後のレシピは「たけのこの白和え」です。
「白和え」ってどんな料理なのか、チョット調べてみました。「白和え」はキーボードでは「しろあえ」でも「しらあえ」でも「白和え」と変換されますが、読み方は「しらあえ」です。
「白和え」は白い豆腐や白胡麻などでつくった和え衣と、野菜などの具材を混ぜ合わせるところから、白い衣をまとったようになるので「白和え」と言うそうです。ここで「和え衣」って何?ですが、砂糖や塩、酢、しょう油、味噌などの調味料と、風味豊かな食材など具材にからまりやすいものを合わせて作ったものだそうです。
さて、たけのこの旬は、4月から5月。これからが、たけのこのシーズンです。たけのこは「筍」って漢字で書きますよね。竹冠に旬。旬の意味を調べてみると「10日間」、「10日」という意味があるそうです。たけのこは約10日間ほどで「竹」にまで成長してしまうようです。たけのこが美味しく食べれる期間はほんのひと時。10日間までの期間ということで竹冠に「旬」て書くのかなと思います。たけのこは焼いても美味しいですし、天ぷらもいい。またたけのこご飯もいいですよね。
では、レシピの方を紹介しますね。
「たけのこの白和え」

1人分 100kcal、たんぱく質 約7g、食物繊維 約2g
材料(2人分)
豆腐 150g
たけのこ煮 30g
人参 20g
たけのこ煮汁 大さじ1
白みそ 小さじ1
きなこ 小さじ1
作り方
① 豆腐は水切りし、たけのこ煮の煮汁・白みそ・きなこを混ぜて和え衣を作る。
味を見て、塩・しょうゆ・砂糖で調整する。
② 人参は千切りにし、たけのこ煮汁(分量外)をかけ、レンジでやわらかくする。
③ たけのこ煮を千切りにし、すべてを和える。
*豆腐の水切り方法(いろいろな方法があります。その時と食感に合わせて)
・まな板にのせ、上に重しをして、斜めに置いておく。
・キッチンペーパーで包み電子レンジで2分ほどチンする。
・1㎝角に切り、茹でで、ざるにあげる。
管理栄養士さんからの一言
白和え
普通は胡麻をするか練りゴマを使うのですが、比較的ご家庭にありそうな『きなこ』を使用しました。
他にもピーナッツクリームやくるみで作ってもおいしいです。
たんぱく質たっぷりで飲みこみやすい和え物です。
「新玉ねぎのレンジ蒸・わかめ煮」のレシピを紹介します。

今月3月のレシピ第3弾は「新玉ねぎのレンジ蒸」と「わかめ煮」のレシピです。今回は二つのレシピを紹介します。
玉ねぎですが、生の玉ねぎがチョット私は苦手です。生の玉ねぎの辛さが苦手なのかな?とも思うのですが。娘が私が玉ねぎを食べると「お父さん。明日熱出さない?」なんてからかってきます。でも焼いたり煮たり、少し手を加えた玉ねぎは、甘みがあって、とても好きで、美味しくいただいています。たまに行くお店で、玉ねぎ丸ごと焼いて出して下さるお店がありますが、焼いた玉ねぎをお塩で食べたり、アンチョビソースや自家製マヨネーズでいただく。玉ねぎを焼くだけですが、とても美味しいです。焼き方もあるのかな?玉ねぎとお肉を塩コショウで炒めても、ご飯が進みます。
わかめ煮も美味しいですよね、竹の子と一緒に煮たり。季節の香りがします。海藻類は便秘にもいいです。便秘の解消に食物繊維が必要ですが、よく「私は生野菜のサラダを食べているから、食物繊維は十分に摂ってます。」という方がいますが、生野菜。量はあっても、食物繊維の量としてはあまりとれません。海藻類やキノコ類の方が繊維はとることが出来ます。ですから、便秘解消に食物繊維をとるのであれば、「生野菜のサラダ」よりは、「キノコと海藻のサラダ」の方が繊維は摂れます。
では、今回のレシピ「新玉ねぎのレンジ蒸」と「わかめ煮」のレシピを紹介しますね。
「新玉ねぎのレンジ蒸」

材料(2人分)
新玉ねぎ 1個
ベーコン 1枚
めんつゆ 適宜
作り方
① 新玉ねぎは半分に切り、ベーコンは細切りにする。
② フライパンでベーコンと玉ねぎの切り口を炒める。
③ 器に盛りめんつゆを入れレンジで4~5分チンする。
「わかめ煮」

材料
生わかめ 100g
しょうゆ・砂糖・酒 各大さじ1
水 100cc
作り方
①生わかめは軽くゆで、適当な大きさに切る。
②すべての材料を入れ、焦がさないように煮る。
*実ざんしょうや生姜
*アサリのむき身やエノキなどど一緒に炊いてもおいしいです。
「鮭のメレンゲ焼き」のレシピを紹介します。

今回は「鮭のメレンゲ焼き」のレシピを紹介します。
3月になりましたが、先週末は、比叡山は薄っすら雪化粧。まだまだなんとなく寒い日もあります。でも気分はもう春ですよね。4月からの新しい生活に向けて、心ワクワクされている方も多いと思います。
ただ、花粉症の方にはチョット辛い季節ですね。なんとか乗り切ってくださいね。
今回は「鮭のメレンゲ焼き」のレシピを紹介します。私の妻は北海道出身。時々妻の実家から鮭が送られてきます。脂がのっていて、やっぱり北海道の鮭は美味しい!と感じます。以前、北海道の実家に行ったとき、海からたくさんの鮭が川を上ってくる来るところを見に行きました。生への力強さを感じました。
では、「鮭のメレンゲ焼き」のレシピを紹介しますね。
「鮭のメレンゲ焼き」

1人分 200kcal、たんぱく質 約20g
材料(2人分)
生鮭 2切れ
卵白 1個分
塩 少々
みりん 少々
作り方
① 鮭にみりんを塗り、魚焼きグリルで焼く。
② 卵白に塩少量を入れ、しっかり泡立てる。
③ 焼けた①に②をのせてさらにうっすら焦げ目がつくまで焼く。
*ほかにも鯛でもおいしくできます。
*色をきれいに仕上げたいので、焦げないように注意してください。
管理栄養士さんからの一言
メレンゲ焼き
いつもの焼き魚に少し卵白が乗るだけですが、華やかになります。
我が家では桃の花に見立てて、お雛様の時に作ります。
「あさりと豆苗の炒め物」のレシピを紹介します。

3月に入って早1週間がたちました。卒業、そして入学。また新たに社会人として独り立ちするための準備、引っ越しなど、あわただしい時期だと思います。皆さんはどうお過ごしでしょうか?
今日は「あさりと豆苗の炒め物」のレシピを紹介します。
あさりと言えば、直ぐに頭に浮かぶのが、「あさりのお吸い物」や「あさりの酒蒸し」です。「あさりの炊き込みご飯」もいいですよね。少し飲みすぎた次の日なんかに、なんとなく汁物が欲しくなりますが、そんな時にあさりのお吸い物もいいですよね。あさりの炊き込みご飯もあさりのエキスが御飯にしみこみ、美味しいですよね。
さて、「豆苗」って?私はやっぱりなにも知らないんだなと思いました。豆の苗なので、なんかの豆の芽が出たものなのかな?と思いました。調べてみると、「豆苗」はエンドウの若菜で、もともとは大きく成長したエンドウの若い葉と茎を摘んだもののようで、中国料理の高級食材だったようです。最近では、エンドウ豆から発芽した状態のエンドウが根が付いたままや、根をカットした状態で売られているようです。
そういえば、私の家でも、キッチンに根付きの豆苗があったのを思い出しました。一度刈った豆苗がしばらくするとまた新たに芽が伸びてきて再度使うことができます。あれが豆苗だったんだ!後から管理栄養士さんの一言で紹介しますが、豆苗には様々な栄養素が含まれているようで、体によさそうです。
ではレシピを紹介しますね。
「あさりと豆苗の炒め物」

1人分 25kcal、たんぱく質 約4g、鉄 約2g
材料(2人分)
あさり 200g
豆苗 1袋
オリーブオイル 小さじ1
作り方
① あさりは塩抜きしてきれいに洗う。
② 豆苗は下から5㎝くらいのところで切り離し、長さ5㎝に切る。
③ フライパンに①を入れふたをして貝が開いたら②を入れさっと混ぜる。
④ 仕上げにオリーブオイルをかける。
管理栄養士さんからの一言
豆苗豆苗はエンドウ豆の茎葉で、たんぱく質・食物繊維・鉄分が豊富で
ビタミンもβカロテン・ビタミンK・葉酸・ビタミンC・ビタミンEが多く含まれています。
ビタミンACEは免疫力アップに効果があり、風邪予防になります。
鉄分・葉酸・たんぱく質は貧血に効果的です。
価格も安定していつでも買える優秀な野菜の1つです。
生でもさっと加熱してもおいしく食べられます。
「春野菜の天ぷら」のレシピを紹介します。

3月第2弾のレシピは、「春野菜の天ぷら」です。
2月も終わって、春の気配を感じる季節になってきました。この時期に食事を食べに行ったり、飲み屋さんに行ったとき、なんとなく注文したくなるメニューに春野菜の天ぷらがあります。ほかにも「春野菜を使ったパスタ」など、メニューを見たときに、この「春野菜」という言葉に心動かされて頼んでしまいます。
春野菜と聞くと思い出すのが、長野に住んでいる方が、毎年、「タラの芽」を送って下さっていたことです。段ボールにいっぱいのタラの芽。でも季節の旬の野菜。あっという間に食べてしまったのを思い出します。このタラの芽の天ぷらや、ふきのとうの天ぷらなど、少し苦みのある野菜ですが、この苦みがなんとなく春を感じさせてくれます。
今回のレシピの春野菜は、若ごぼう、菜の花、そしてたけのこです。
菜の花は天ぷらだけでなく、お浸しもいいですよね。菜の花もチョット苦みがありますよね。竹の子も天ぷらや、焼くのもいいですよね。そしてたけのこ御飯、山椒の葉を載せ香りづけ。いいですよね。
では「春野菜の天ぷら」のレシピを紹介しますね。
「春野菜の天ぷら」

1人分 250kcal、たんぱく質 約4.5g、食物繊維 2g
材料(2人分)
若ごぼう(茎) 1本
菜の花 2本
たけのこ煮 6切れ
小麦粉 大さじ3
片栗粉 大さじ1
炭酸水 適宜
梅昆布茶 適宜
作り方
① 若ごぼうの茎は5㎝に切り、水にさらしておく。
② 菜の花、たけのこ煮は食べやすい大きさに切る。
③ ボールに小麦粉、片栗粉を入れ炭酸水でトロっとした感じに溶く。
④ ③に水気を切った①②をくぐらせてカラッと揚げる。
⑤ 器に盛り、梅昆布茶を添える。
*ほかにふきのとう、たらの芽、うどなどもおいしいです。
*天ぷら衣に片栗粉や炭酸水を使うことでよりかりっと仕上がります。
管理栄養士さんからの一言
若ごぼう
食物繊維・鉄分が豊富な野菜で、根・茎・葉のすべてが食べられます。
今回は使わなかった根を鯛あら煮に、茎の残りと葉は佃煮にしました。
『春苦み、夏は酸味、秋辛味、冬は油と心して食え』という石塚左玄氏の言葉があります。
春に苦みのある野菜が多く出てくるのは体が欲しているからかもしれません。
「たけのこちらし」のレシピを紹介します。

あっという間に2月は終わり、3月になりました。寒さも少し和らいできて、春の気配を感じることが出来るようになりました。花粉症の方にはチョット憂鬱な季節かもしれませんね。
今度の日曜日、3月3日は雛祭りですね。春を迎える祭りです。私の家でも昔は、雛祭りの前にお雛さんを飾って祝ったものです。最近はチョットご無沙汰しています。
雛祭りは、女子の健やかな成長を祈るお祭りです。でも、その起源は女の子のお祭りというのではなく、男女共通の行事として、厄払いや邪気祓いとして行われていたようです。季節の変わり目に災難や厄から身を守り、よりよい春を迎えることを願うための節句として始まったとされています。雛人形も、家に飾るのではなく、川に流していたということです。随分今とは違ったものだったようです。
さて、雛祭りのレシピと言えば、ちらし寿司や蛤のお吸い物。菱餅やひなあられ。いずれも色とりどりで、チョット華やかなイメージですよね。やっぱり女の子のお祭りかなと思います。
今日は雛祭りを迎えるにあたって、「たけのこちらし」のレシピを3月最初のレシピとして紹介したいと思います。
「たけのこちらし」

1人分 350kcal、たんぱく質 約8.5g、食物繊維 約2g
材料(2人分)
ご飯 330g
たけのこ煮 60g
人参 30g
たまご 1個
酢 大さじ2
砂糖 大さじ1
塩 小さじ1/2
菜の花(ゆで) 適宜
作り方
① 酢・砂糖・塩を器に入れ、電子レンジで温めて合わせ酢を作る。
② 熱いご飯に①を混ぜ、酢飯を作る。
③ 人参は千切りにし、たけのこ煮汁(分量外)をかけ、レンジでやわらかくする。
④ たけのこ煮を千切りにし、穂先は飾り用に切り分ける。
⑤ 卵を溶き錦糸卵を作る。
⑥ ②に③と④を混ぜ、⑤と穂先のたけのこ煮、菜の花を飾る。
管理栄養士さんからの一言
菜の花
春を代表する野菜の1つ。
栄養面でも免疫力を高めるビタミンA(βカロテン)・C・Eがすべて含まれ、
葉酸と鉄分で貧血予防の効果もあります。
『春苦み、夏は酸味、秋辛味、冬は油と合点して食え』という石塚左玄氏の言葉があります。
春になると苦みのある野菜が出てきますが、ちょうど体も欲しているように感じます。