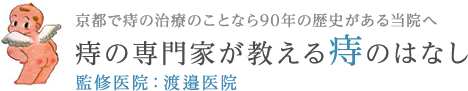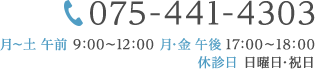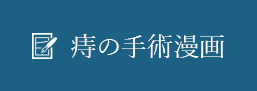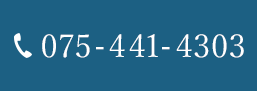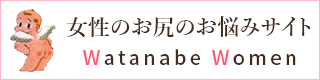談話室のノートの力
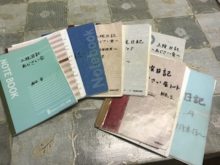
渡邉医院は、外来の待合室の奥と、2階全部が入院施設になっています。19人の患者さんが入院できる19床の有床診療所です。3人部屋の洋室や個室。また畳の部屋もあります。
そんな渡邉医院の2階に入院の患者さんが使う談話室があります。入院患者さん同士が話をしたり、家族の方と話をしたり。また、テレビもあるので入院している間この談話室でくつろがれる方もいます。食事など、皆さんでこの談話室で摂られる方もいます。その談話室に患者さんの思いを自由に書いていただくノートが置いてあります。ノートの表紙に書かれている表題は「あじさい会」です。患者さんがつけた名前です。ペンションや喫茶店などにおいてある、お客さんが自由にいろんなことを書くノートのようなものです。
時々読ませてもらうのですが、いろんなことが書いてあります。手術の前の不安な気持ち、手術の時のこと。また術後の経過など、その時にまつわるいろんな思いが綴られています。
お尻の具合が悪かったけれども、なかなか病院に行けなかったこと。いろんな病院を受診したけどもやっと決心がついて手術を決めたこと。などなど、自分が経験した痔の歴史や治療に至るまでの悩みを書いている患者さんもいます。
また、「麻酔は痛かった!」とか、術後の痛みの具合や、治っていく過程を一日一日書いている方。また次に手術を受ける患者さんへのエールの言葉など様々です。
でも皆さんの書いている内容は、実際に経験されたことが書かれているので、とてもリアルですごくよくわかる内容で、説得力があります。入院して手術を受ける方が、このノートを見て「麻酔が痛いんですよね!」と聞かれると、「そうだね、麻酔は痛いけど、麻酔だからずっと痛い訳ではなく、途中から委託なくなりますよ。」と話したりしています。ネットの情報など、いろんな情報があふれている今の社会の中で、やっぱり経験した人たちの話や書いたものを読んで、正しい情報が前もって入るということはとてもいいことなんだと思います。
最近は1泊2日だったり、3泊4日と入院期間が短くなっています。以前は1週間以上入院したりしていました。その頃は入院期間も長かったので、患者さん同士がなかよくなり、夕方、皆で談話室に集まって、自己紹介をしたり、自分の痔の歴史を語ったり、入院期間を楽しく過ごされていました。やはり同じ病気で戦う「同志」といった感じだったんでしょうか。退院された後も、同じ時期に入院されていた患者さんが集まって親睦会なども開催されていました。時々その会に誘っていただいたこともありました。同じ病気で一緒に治していくというところで入院患者さん同士で連帯感が生まれるのかなあと思います。
やはり実際に経験したことを教えてもらう、伝えていくということはとっても説得力もありますし、安心感もあると思います。談話室にあるノートにはそういった患者さんへのエールの力を持っています。そういった患者さんの思いをアンケートに答えることでも知ることが出来ます。その思いをまとめて、それを次の患者さんに伝えていくことも私のしなければならない仕事だと思います。
痔瘻の再発を考える。

外はまだ暑いですが、なんとなく空気が変わってきたような印象をうけました。暑いけど前みたいに体にまとわりつくような暑さではなくなりました。季節は確実に進んでいます。少し秋を感じました。
痔瘻の再発について
前回、内痔核の再発についてお話しました。今回は痔瘻の再発についてお話したいと思います。
さて、今日来られた患者さんで、「40年前に痔瘻の手術をしたけど、今度は反対側が痔瘻になったかもしれない。」と言って受診された方いました。
診察してみると、以前に痔瘻の手術をされた傷跡がありました。そことは違う場所に炎症を起こしている部分がありました。一見痔瘻の様に見えましたが、違いました。毛嚢炎と言って毛嚢に細菌感染を起こしたものでした。症状としては炎症を起こして痛みがあるため、痔瘻や肛門周囲膿瘍に似ていますが全く違います。
肛門周囲膿瘍・痔瘻
肛門周囲膿瘍は、肛門と直腸との間にある肛門腺が細菌感染を起こして炎症を起こして膿瘍が広がっていく病気です。切開して排膿するのですが、感染を起こしたところと切開部位が違うため、原因となった肛門腺と切開した部分との間に硬い瘻管が出来ます。そして、原因となった部分で炎症が起きると、この瘻管の中を通って膿が出てきます。言ってみれば自分の体が自分を守るために作った瘻管です。ただ、膿が出たり治まったりするのが嫌な症状です。この症状が出たときに痔瘻となります。このように肛門周囲膿瘍を治療する場合、どうしても原因となった部分と切開部分が異なるため、瘻管が出来、膿が出るなどの症状が続く場合は、この瘻管を摘出する痔瘻根治術をしなければなりません。
毛嚢炎・粉瘤の炎症
これに対して毛嚢炎や場合によっては粉瘤が炎症を起こして化膿する場合があります。この場合は抗生剤と消炎鎮痛剤の投与で治ったり、場合によっては切開して排膿しなければならないこともあります。でも肛門周囲膿瘍と違って炎症を起こした部分と切開する部分が同じですので、瘻管はできずに治っていきます。
このように似たような症状ですが、まったく違います。でも患者さんはそれを区別することが難しいと思います。また炎症を起こしている部分を自分で見て確認することも難しいと思います。以前痔瘻になった経験がある人は、「また痔瘻か!」ととても心配されると思います。また今回が初めての症状でも、ネットなどで調べて、「私は痔瘻になってしまった!」と思って心配されてくる患者さんもいらっしゃいます。そんな時はまずは肛門科を受診して診察してもらうといいと思います。
患者さんにとって肛門周囲膿瘍、痔瘻はとても嫌な病気です。まずは肛門周囲膿瘍と言ってとて肛門の周囲に膿が広がって腫れあがりとても痛い症状が出ます。座っても横になっても痛く、身の置き場がありません。また熱が出ることもあります。そして、この症状を摂るには麻酔をして切開して膿を出さなければなりません。
さらにその後痛みが治まったとしても痔瘻になって、膿が出たり治まったするという嫌な症状が続いてしまいます。肛門周囲膿瘍になってすべての人が痔瘻になるわけではありません。70%の人はその後何の症状も出ません。でも痔瘻になったら、これをスッキリ治すにはもう一度痔瘻根治術をしなければなりません。肛門周囲膿瘍に対しての切開排膿術、そして痔瘻に対しての痔瘻根治術、この2回の手術をしなければなりません。やっぱり「また痔瘻になりたくない!」という気持ちはとても良く解ります。
痔瘻は何回もなるの?
今日の患者さんも、「痔瘻って何回もなる病気ですか?」と質問されました。その答えは、「痔瘻は何回も何回もなる病気ではありません。1か所痔瘻になって、そしてしっかり治ったのに、また別のところに痔瘻が出来るということは多くありません。クローン病などの基礎疾患がある場合は繰り返すことがありますが、そうでない場合はまずありません。また同じ部分に繰り返して痔瘻が出来ることもありません。炎症を起こした肛門腺、原因をしっかり取り除いて、しっかり治ってしまえば、原因がなくなったわけですから、そこにまたできることはありません。」です。
ただ同じ部分が同じように炎症を起こして繰り返すこともあります。このことを「痔瘻が再発した。」と言いますが、私はこれは再発ではないと考えています。
手術をして、いったん症状が取れたので、私と患者さんが治ったと思たが、本当はまだちゃんとしっかり治っていなくて、治っていないのでまた症状が出てしまったということだと考えています。この原因としては、炎症を起こした原因、原発口と原発巣がちゃんと摘出できていなかったり、しっかり取り除けていても治っていく過程で、どこか一部直りが悪く傷が治っていく過程で、瘻管を形成してしまった時などです。
私が手術をした患者さんの中にも、「いったん治ったのに、また腫れてきた。」と言って受診される患者さんもいらっしゃいます。診察してみると、根本の原因の部分は治っているが、その途中に瘻管を形成してしまった場合や、やはり十分に原因が取り除けていなかった患者さんもいらっしゃいます。そんなときは、また腫れてしまった原因や治りきらない理由をしっかりお話して、もう一度手術をさせてもらっています。
痔瘻は一回しっかり手術をして、スッキリ治ってしまえばまた痔瘻になることはありません。何かスッキリ治らず、また腫れてくるなどの症状がある場合はその原因があります。何か症状がある場合は、迷わず医師に「スッキリ治っていない。」と伝えて下さい。
内痔核の再発をどう考えるか?

今日は一日雨でした。時折激しい雨脚で、雨による被害が出ているところもあるのではと心配します。九州では被害が出ているようです。被災された方にはお見舞い申し上げます。京都では今は少し小雨になっていますがまだまだ降り続きそうです。
内痔核の再発を考える。
さて、今回は内痔核の治療、特に痔核根治術やジオンによる痔核硬化療法(ALTA療法)を行った後の再発に関して考えてみたいと思います。
内痔核に対して痔核根治術を受けたときなど、「もう二度と手術はしたくない。」と思うのは当然のことです。できるだけ手術はしないで治したい。手術をしたとしてもこの1回だけで済ませたい。誰もがそう思うはずです。私もそう思います。
そこで考えなければならないのが内痔核の再発をどう考えるかです。
内痔核。「おぎゃー!」と生まれたときから内痔核を持っている人はだれ一人いません。便秘や下痢などの排便の状態が悪いことで内痔核はできてきます。
お酒や刺激物がダメだと思っている方います。おそばを食べるときに「七味をかけたいけどお尻に悪いからやめておこう。」とか、お刺身を食べるときに「ワサビをつけたいけどお尻に悪いからやめておこう。」また、辛いものが好きだけでお尻のために我慢する。でも、これらは内痔核の原因にはならないと思います。内痔核が悪くなる一番の原因は、排便時に頑張っている時間が長いことだと考えています。それは、毎日便が出るでということではなく、排便時の頑張る時間が長いと内痔核は悪くなります。そして、これが一番の内痔核の原因だと思います。
どうしても排便の状態が悪くて頑張っている時間が長い。そしてこれを繰り返していくことによって、内痔核が段々悪くなっていきます。したがって、何もなかったところから、排便の状態が悪くて内痔核が出来てしまったことを考えると、手術をして内痔核を根本的に切除しても、また排便の状態が悪いと内痔核が出来てしまいます。さて、これを再発と呼ぶかです。
例えば癌に対して手術をした場合の再発は、どうしても取り除くことが出来なかった癌細胞がまた増殖してきたり、転移先で癌細胞が増殖してきたりする。その再発と内痔核の再発を同じように考えていいのかなあと思います。
治療後の排便状態の改善が重要。
内痔核をしっかり手術等で治療した後、原因となる排便状態をしっかり改善できれば、内痔核の再発はないと思います。ですから、内痔核に対しての治療は手術などをして治した後の治療がとても大切になってくると思います。
よく、内痔核に対して手術をした患者さんが、手術の後や治癒した後にこんな質問をされます。「また内痔核は再発しますか?」と。この手術をした患者さんがまた再発しますか?と聞かれるときの「再発」は、おそらく「また手術をしなければならない内痔核になりますか?」だと思います。
その質問に対して私の答えはこうです。「なにも無かったところから内痔核が出来てしまいました。手術をして内痔核がなくなったとしてもなかったところから出来たことを考えるとまたできる可能性はあります。でも、治ってなにも無くなったところから、いきなり手術をしなければならない内痔核にはなりません。もし内痔核が出来たとしても、第Ⅰ度、第Ⅱ度、第Ⅲ度、第Ⅳ度と順番だって悪くなっていきます。昨日まで何ともなかったのに、いきなり手術をしなければならない第Ⅲ度以上の内痔核にはなりません。
それに、何の症状もなく気が付いたら内痔核が手術をしなければならないほど悪くはなりません。出血や違和感、腫れ、痛み、違和感など必ず内痔核が悪くなる時には症状が出ます、そして内痔核が悪くなる時はその症状が段々強くなってきます。例えば出血した、そして出血の頻度が多くなる、そして出血の量が増えてくる。また腫れてきた、その腫れが段々強くなってきた。違和感がある、その違和感が段々強くなってくる。と言ったように、必ず内痔核が出来て悪くなる時は自分が感じる症状が出て、その症状が強くなってきます。なんの症状もなく、いきなり手術が必要な内痔核になりません。
また内痔核が悪くなるには、必ず原因があります。その一番の原因は便をするとき、頑張っている時間が長いことです。頑張っている時間が長いと内痔核の具合が悪くなっていきます。内痔核が良くなった後は、排便の状態を良くすることが最終的には大切になります。でもまた何か症状が出たときには早めに診せて下さいね。」とお話しています。
肛門の病気には必ず自分が感じる症状がある。
手術だけでなく、内痔核の治療をした後の排便状態の改善。これが一番重要です。そして自分が感じる症状、出血や腫れ等が無いときは内痔核は治ってしまっているということです。
治療は納得してから受けましょう。

診察の流れは、まず問診から始まります。いつからどのような症状があるかを聞きます。でもやはり今の状態を直接診ることが一番だと思います。そして診察をさせてもらって診断する。そして病状を説明して最後に今ある病気に対して一番良い治療法と思われる治療方法の説明をします。
治療に対しての不安や疑問
このままスッと治療に進むことが多いのですが、患者さんの中には治療方法に関してチョット迷われる方がいます。でもこのことはとても大切なことだと思います。
患者さんは自分の持っている病気に対して、そしてその治療方法に様々な不安を抱かれると思います。そしてこのことはとても大切なことだと思います。例えば、「今の状態はこのままにしていても治っていかないのだろうか?」、「本当に今説明してもらった治療方法が一番良い治療方法なのだろうか?」、「他に治療方法はないのだろうか?」と言った病状やその治療方法に対しての不安。また「先生の言っていることはよくわかるが、手術をするのがやはり怖い。直ぐに手術を選択できない。」、「治さなければならないのは分かっているが、やっぱり手術は怖い、したくない。」、「手術に耐えられるだろうか?」、「痛いのは嫌だ!」などの様に手術が必要なのは分かっている、理解できているでも踏み切れない。
また、「手術はしたいが仕事は今は休めない。」、「家族に介護しなければならない人がいるので、手術はしたいが今はできない。」、「手術後いつから仕事ができるのだろう。長く休めない。」等々社会的な理由だったり、または経済的な理由など、様々なことで、治療に踏み切れず悩まれることがあります。そういったように、どうしても提案された治療に何か不安があったり、自分として納得いかないときは、慌てず治療を受けない方がいいと思います。
不安や疑問を解決してから治療を受けましょう。
自分が抱く不安な点、納得がいかない点をしっかりと医師に伝え、それに対する答えを聞くことが一番大切です。納得がいかないまま、不安を抱いたままの治療は決していい方向には進まないと思います。幸いにも肛門の病気、内痔核や痔瘻、裂肛は悪性の病気ではありません。ほっておいて命にかかわってくるような病気ではありません。嫌な症状を取り除くことが目的の治療です。じっくり考える余裕がある病気です。
例えば患者さんの中には、第3度の内痔核(排便時に出血したり脱出して押し込む)をもっている患者さんでも手術をせずに軟膏などで保存的に治療をしている患者さんもいらっしゃいます。「排便時に脱出してくるけど、軟膏をつけていると出血はしなくなって、脱出しても軟膏をつけると直ぐに戻すことが出来る。まだ手術をしなくても大丈夫。」といった具合です。これも一つの選択だと思います。例えば内痔核があって、血栓などが詰まって痛くなった時はその痛みをとる方法はあります。また出血が多い時も手術をしなくてもその出血を抑えてあげる方法はあります。そうゆう患者さんが来られた時は、「痛みが出たり、出血が多いときはそれを抑える方法はあるから、そんな時は直ぐに受診してくださいね。内痔核を手術してしっかり治そうと思った時は言ってもらったら、段取りをとりましょうね。」とお話しています。
納得してから治療を
やはり肛門の病気だけではありませんが、しっかり今ある病気の病状がどうなのか、そしてどのような治療が必要なのか。そしてその治療は本当に今すぐ必要なものなのか。先に延ばしてもかまわないものなのか?など、自分の抱いている不安材料や疑問をしっかり医師に聞くこと。そして自分自身が納得して治そうと思った時にその治療法を受け入れることが大切だと思います。やっぱり自分の思いをしっかり医師にぶつけることが大事です。
そういった気持ちを医師は分かってくれるはずです。
そして医師はそういった不安、疑問にしっかりと答えていかなければならないと思います。
3日間の間には、お腹スッキリさせましょう!

便が出ないととっても苦しい!
今日は、便が詰まってしまった患者さんが数名受診されました。便が詰まって出ない。この状態はとても苦しい状態です。そこまで来ているのに頑張ってもでない。トイレで頑張っていると、目の前が真っ暗になってしまう。貧血みたいになって気が遠くなってしまう。などの症状が出ます。また便が出なくて頑張っているときは血圧も上がってしまいます。200mmHgまで上がることもあり、便が出たとたんに一気に血圧が下がるなどの原因でトイレで倒れてしまうこともあります。
また便が直腸に詰まってしまうと、常に便がだらだらと出てきて下着が汚れてしまうなど、とても悲しい状態になってしまいます。
便が出ないと食欲もなくなり、ご飯も美味しくなくなってしまいます。このことがまた便秘を悪化させたり。
こんな状態になった時はスッキリ便を出してしまわなければなりません。
便はどうして硬くなって出なくなるの?
ここ数日少し暑さが和らいできましたが、暑さの中十分に水分が摂れてなかったり、夏バテして、食事が思うように摂れないなどが原因で便が硬くなって詰まってしまったのかと思います。
水分の量としては、1日、最低2Lの水分が必要です。でも食事の中にも水分は含まれています。ご飯が美味しく三食食べれていると、それだけでも1~1.5Lの水分が摂れます。でも2Lには足らないので、食事以外に1L の水分が必要になります。暑い中、体の外に出ていく水分は多くなります。これが十分に補えなくなると便が硬くなり出し難くなります。また暑さのため夏バテして食事が思うように摂れないと、食事で補える水分だけでなく、便の量も減って、便が出なくなってしまいます。
こんな時は、寒天でできたものとか、トコロテンも便の量を増やし、水分を補ってくれます。こういったものも食欲がないときに摂るのも一つの手かもしれませんね。
便が硬くなってしまうと、なかなか自力では出せません。
ただ、硬い便が直腸に詰まってしまうと、自分ではなかなか出すことができません。硬い便ですといくら頑張っても便がでません。また自分で浣腸しても、硬い便が出口にあると、浣腸の液だけしかでてきません。また硬くなってから下剤をあわてて飲んでも硬くなった便は柔らかくなってくれません。下剤は便が硬くならないようにする薬で、硬くなった便を柔らかくする薬ではありません。
便がそこまで来ているのに出ない。いくら頑張ってもダメ。とても辛いといった時は直ぐに受診することが大事です。
便が硬くなってしまって詰まってしまったらどうするか。
便が硬く詰まった時は、摘便と言って硬くなった便を出したりします。少し痛みがありますが、硬くなった便をそのまま浣腸しても便はスッキリでません。硬い便を取り出したり、また硬い便を崩して柔らかくしてから浣腸をしないと、しっかり便は出てくれません。
直腸に便が残ったまま、次の日に持ち越してしまうと、この便がまた硬くなってしまいます。しっかり便を出し切ることが大事です。出し切った後は緩下剤を内服して便秘を治していく必要があります。
何日間便が出なくても大丈夫なの?
ではどのくらいまでなら大丈夫かですが、食べたものが消化されて便になるまで長くても3日間です。ですから3日間の間には1回はスッキリ便が出ないと出なくなって詰まってしまいます。
具合よく便が出ていて、1日でないときはまだまだ焦らなくていいと思います。「今日は出なかったのでしっかり水分を摂っておこう。」と様子を診てもらっても大丈夫だと思います。これが2日目も出なくて、3日目も出ないともう出ません。3日間でなくて4日目を期待してもダメです。ですから、毎日便が出る人は2日目も出なくて、夕食を迎えたら、その日は緩下剤を飲んだり、いつも飲んでいるよりもたくさんの量を飲んで次の日にスッキリ出してしまう必要があります。少し緩くなってもいいと思います。スッキリ便が出ることでまた便の調子は良くなってきます。
また毎日気持ちよく便が出ていたのに、出てはいるもののスッキリしない。お腹が張って不愉快な日が3~4日続いた時も、一度緩下剤を飲んだり量を増やしてスッキリ出してしまうのがいいと思います。
いったん詰まって硬くなってしまうと、なかなか自力で便を出すことが出来なくなってしまいます。詰まってしまう前に、硬くなってしまう前に緩下剤を飲んでスッキリ出すことが大切だと思います。
「9月の献立」を紹介します。

今日は久しぶりのいい天気ですね。しかも涼しくて爽やかな朝。8月も後残すところ一週間。これで一気に秋とは今ないと思いますが、少しづつ季節が進み、秋の気配もちょっとづつ感じるようになりますね。
今日も入院の患者さんや手術したばかりの患者さんの診察に診療所に来ています。渡邉医院の玄関前の通りには。花が咲いていました。

今日は25日、北野天満宮では天神さんのお祭り、屋台の準備もすすんでます。今日も多くの人が天神さんに行かれることでしょう。

9月のレシピはキノコづくしのレシピを紹介してきました。今日はそのレシピを組み合わせた「9月の献立」を紹介します。えのきと青梗菜の煮びたしのレシピも一緒に紹介しますね。
「9月の献立」

1人分 約600kcal、たんぱく質 35g、食物繊維 13.5g
・舞茸と蓮根と鶏肉の甘辛炒め
・鮭ときのこのレンジ蒸し
・なめこの天ぷら
・えのきと青梗菜の煮びたし
・きのこご飯
えのきと青梗菜の煮びたし

青梗菜 1株
えのき 小1袋
だしの素 少々
薄口しょうゆ 少々
*手羽がら(手羽先の先っぽ)があれば一緒に
(作り方)
- ①青梗菜は1枚ずつはずしよく洗う。1cm幅に切る
②えのきもいしづきを落とし1cm幅で切る。
③ひたひたの水を入れすべての材料を水から入れて軟らかく煮る。
「管理栄養士さんからの一言」
えのき
1年中手に入り、価格も安定していて、日本で1番食べられているきのこです。えのきには糖質・脂質・たんぱく質を体内でエネルギーとして使うために必要な水溶性ビタミンのビタミンB1,ビタミンB2,ナイアシンや骨の形成に必要な脂溶性ビタミンのビタミンDが豊富に含まれ、便通を整え生活習慣病の予防・改善に効果のある食物繊維も豊富です。
「おはぎ」のレシピを紹介します。

今日は6種類の「おはぎ」のレシピを紹介します。
私は基本的にあんこが大好きです。ですから、あんこが使われているものは何でも好きです。あんぱん、お饅頭、あんころ餅、かき氷にあんこ、何でもです。
ですからおはぎの中で一番好きなのはあんこのおはぎです。で、やっぱり粒あんがいいなあと思います。
ところで、「おはぎ」と「ぼたもち」って同じなのかなあと思って調べてみました。
「おはぎ」と「ぼたもち」は、作る季節によって違いがあるそうです。そしてその名前の由来は季節の花の名前に由来しているんだそうです。
「ぼたもち」は春のお彼岸に食べていたもので、小豆を牡丹の花にみたてたところから「ぼたんもち」と呼ばれていたものが「ぼたもち」に変わったと言われているそうです。
では「おはぎ」ですが、こちらは秋のお彼岸に食べられていたそうです。秋の七草のひとつである萩の花と小豆の形がにているので、「おはぎもち」と呼ばれていたいたのが、「おはぎ」になったと言われているそうです。
後、夏に作った時は「夜船」、冬に作った時は「北窓」とも呼ばれているようです。春夏秋冬、季節によって名前が違うんですね!やっぱり日本人は四季を大切にするんですね。
では「おはぎ」6種のレシピを紹介しますね。
「おはぎ」

材料(作りやすい分量)
もち米 2合
白米 1合
塩
★むき枝豆(冷凍でも)100g
★砂糖 大さじ1
★塩 少々
粒あん(市販品でも)
こしあん(市販品でも)
きなこ、砂糖、青のり
白すりごま、黒すりごま
作り方
①炊飯器でもち米と白米を合わせて炊く。
②むき枝豆を温め、★をブレンダーかすり鉢でする。(ずんだあん)
③①を半殺し(粒が残る程度にすりこ木で突いてつぶす)にし、塩水をつけて小さなおにぎり状にする。
④③のうち、小豆あん・ずんだあんで包むものはそのまま。
それ以外は、中に小豆あんを入れる。
⑤それぞれのおはぎに仕上げる。
*小豆あん:あんで包む。
*ずんだあん:ずんだあんで包む。
*きなこ:あん入りご飯にきな粉と砂糖を混ぜたものをまぶす。
*白ごま:あん入りご飯に白すりごまと砂糖を混ぜたものをまぶす。
*黒ごま:あん入りご飯に黒すりごまと砂糖を混ぜたものをまぶす。
*青のり:あん入りご飯に青のりと塩少々を混ぜたものをまぶす。
続・医師とちゃんと話ができていますか?

今回も、「医師とちゃんと話が出来てますか?」につてお話したいと思います。
渡邉医院を受診される患者さんのなかに、「治療を受けたが今一つ良くならない。」とか「手術をすすめられたが、本当に手術が必要なのか?」と話される患者さんがいます。また、「何か治療をしてもらったが、何をしてもらったのかわからない。」という患者さんもいます。中には「診察を受けたらいきなり治療された。」などと話される方もいらっしゃいます。
医師側の問題が大きいと思いますが、まずは自分の症状をしっかり医師に伝え、何が一番悩んでいるかを医師に理解してもらうことも大切だと思います。そして、その悩みに対して、なぜそのような症状が出るのか、自分の病気は何なのかをまずはしっかりきくことが大事です。またその病気や今の症状、悩みを解決する方法が何か。例えば軟膏などの外用薬で治るのか?手術が必要なのか?手術に代わる治療方法はないのか?など、医師にしっかり説明してもらうことが大切だと思います。そして医師もそのことを省いてはいけないと思います。
病気の程度で治療方法は決まる
例えば内痔核だった場合ですが、内痔核は病気の程度で治療が決まります。第Ⅰ度から第Ⅳ度までの四段階に病気の程度が決まり、その病気の程度で治療方法が決まてきます。
第Ⅰ度の場合は、排便などの調整をすることで内痔核が治ることもありますし、軟膏などの外用薬や出血が多い場合などはパオスクレーという痔核硬化剤での痔核硬化療法で治っていきます。
第Ⅱ度になりますと、排便時に内痔核が脱出しててきますが直ぐに自然に戻る程度の内痔核になります。この場合は出てくる(脱出)という症状があるので、どうしても軟膏などの外用薬だけでは良くならないことが多いっです。この場合はパオスクレーによる痔核硬化療法で内痔核が脱出してこなくなります。まだまだ手術にはなりません。
さらに内痔核が悪くなって第Ⅲ度の内痔核、排便時に内痔核が脱出して、押し込まないと戻らない、になると、やはり痔核根治術による手術やジオンという痔核硬化剤での四段階注射法による痔核硬化療法(ALTA療法)が必要になります。
第Ⅳ度になりますと、内痔核が脱出したままになって押し込むこともできなくなってきます。こうなるとスッキリ治すには痔核根治術による手術が必要になってきます。
こういったように内痔核の病状、程度で治療方法が決まってきます。
でもいきなり診察をして手術などの治療をすることはありません。診察しながら何の説明もなく「もう治療をしておきましたよ。」という話にはなりません。診察の後、病状の説明をして、どのような治療方法があるのか、またどんな治療方法が必要なのかを説明します。そして、その治療方法に納得してもらってから、その治療法を患者さんに提供する。この過程が無ければ、患者さんは自分の病気のことを理解することはできませんし、どんな治療法を受けたのかもわからないままになってしまいます。
セカンドオピニオンという選択
また自分の悩んでいる症状と治療方法に何かしっくりしない違和感を感じたときは、直ぐに治療を受けずに、セカンドオピニオンと言って、別の専門の医師に今の自分の症状、病気、そして病気の程度、治療方法を診断してもらうことも大切です。例えば、内痔核の場合は、排便時に内痔核が脱出して、押し込まないと戻らなかったり、脱出したままで戻すこともできない状態の内痔核になりますと痔核根治術などの手術が必要となります。出血だけだったり、脱出してこない内痔核は手術以外にも治療方法があります。排便時などに内痔核が脱出して、自然に戻らず押し込むような第Ⅲ度以上の内痔核の症状がないにも関わらず「手術が必要です。」と言われた場合は、直ぐに手術を決めずにセカンドオピニオンをした方がいいと思います。
でも反対の場合もあります。内痔核などが原因で、肛門の外側に皮膚のシワ、皮垂(スキンタグ)があって、これがとても気になる症状でも、「皮垂は悪い病気ではないので、手術の必要はありません。」と言われることがあるようです。実際に皮垂は悪い病気ではありません。出血や痛みの原因にはなりません。でもその皮垂があることが一番の悩み、そしてそれをしっかり取り除いてしまいたいという患者さんもいらっしゃいます。そういった場合は皮垂を切除する意味は大きいと思います。医師と話をして切除してもらうことも大切だと思います。
納得してから治療を受ける
どうしても患者さんは医師と比較すると病気に関しての情報量が絶対的に違います。医師の言うとおりにしてしまうことがあると思います。でも何か違和感を感じたり、なにか違うんじゃないかなあと感じたときは、直ぐに治療を決めず、納得した上での治療が大切だと思います。
医師としっかり話す。ちゃんと話を聞いてくれる医師に治療を任せることが大切だと思います。
医師とちゃんと話ができていますか?

今日は医師との付き合い方に関して、少しお話したいと思います。
というのも、患者さんと話をしてみると、医師と上手く話が出来ていないのではないかと感じることが時々あります。
医師とちゃんと話ができていますか?
例えば便秘の患者さんが来られて、緩下剤をもらっているが一向に良くならない。便が出ないと言う患者さんがいます。
その患者さんに、便秘の原因や緩下剤の飲み方をお話すると、「こんな話は、初めて聞いた。」という患者さんがいます。医師側が患者さんに緩下剤を出す際にはしっかり便秘の原因や緩下剤の飲み方をお話しなければならないと思います。どうしても「便秘です。」と患者さんが言うと、「では下剤を出しておきますね。」で終わってしまうことがあるのかなあと思います。また患者さんも、医師が出した薬をなんだら必ず良くなると思うところをあるのかなあと思います。
医師が薬を出した時のその意味するところは?
大前提は、便秘に関してのお話をして、緩下剤の飲み方をお話した後のことですが、例えば医師が「便秘に対して緩下剤を出しますね。1日に1回夕食後に内服してみて下さいね。まずは1週間分出しますね。」と言った場合、これは何を意味するかです。
このことの意味するところは、「まずは1日に1回夕食後に内服してどうなるか教えてくださいね。」ということで、「1日1回夕食後に内服したら治りますよ。」ではありません。
例えば便秘で緩下剤を出してもらった場合、1日に1回夕食後に内服してみたら、①具合よく便が出るようになった。②内服したら下痢をした。③内服してもでない、のどれかになります。
①の具合よく出ていれば、医師は「1日1回の量を続けていきましょう。後は水分を摂ったりして、便秘を治していきましょう。」になります。
②の下痢になった場合は、内服する緩下剤の量が多いということになります。「下痢になったということは、量が多かったのですね。では少し量を減らしてみましょう。」になります。
③の内服しても出ないときは、量がまだ足らないということです。「まだ緩下剤の量が少なかったのっで出ないんですね。もう少し増やしてみましょう。」ということになります。
①の場合は具合よく便が出ている間は内服を止めずに、後は便秘を治すこと、例えば水分を十分に摂ったり、便の元になる食物繊維を摂って便秘を治していけばいいです。具合よく便が出ていたのに、段々便が緩くなってきたらそのことを医師に伝えると。「そうですか。段々便が緩くなってきましたか。便秘が治ってきたということです。では少し緩下剤の量を減らしましょう。」になります。
②や③の場合は、量が変わった緩下剤を医師の指示通りに内服して。またその結果が、具合よく出る、下痢になる、まだ出ないのいずれかになります。このことをまた医師に伝える。こういったことを繰り返していくうちに、最適な緩下剤の量や緩下剤の種類が決まってきます。
医師に今の状態をしっかり教えてあげましょう!
どうしてもこういった過程が抜けてしまうことがあります。医師としっかり話をしていくことがとても大事だと思います。また医師もこういた患者さんとのやり取りをしっかりしていく必要があります。
自分の今の状態や困っていることをしっかり医師に伝え、医師にそのことを教えてあげましょう。
「きのこと鮭のレンジ蒸し」のレシピを紹介します。

9月は「きのこづくし」ということで、キノコを使ったレシピを紹介しています。
今日は「きのこと鮭のレンジ蒸し」のレシピを紹介します。
私の妻が北海道の出身で、時々妻の実家から鮭を送ってもらっています。やはり本場の鮭は脂がのっていて美味しいです。
ムニエルにしても美味しいですし、石狩鍋の鮭も鮭からのだしが出てとても美味しいです。
以前、妻の実家に行ったときに、鮭の遡上をみに行ったことがあります。

秋から冬にかけて鮭が産卵のために川を遡上してきます。海から川にかけての河口付近で息絶えてしまっている多くの鮭。川を力ずよく遡上していく鮭。自然は厳しいなあと思いながらも、いつまでもそのダイナミックな鮭の泳ぎに目が釘付けになったことを思い出します。
貴重な経験でした。また機会があれば見に行きたいなあと思います。
さて「きのこと鮭のレンジ蒸し」のレシピを紹介しますね。
「きのこと鮭のレンジ蒸し」
1人分 約150kcal、たんぱく質 20g、食物繊維 4.7g
材料(2人分)
生鮭 2切れ
えのき 小1袋
しめじ 1パック
玉ねぎ 1/2個
生姜(千切り) 1かけ
★ポン酢 大さじ2
★酒 大さじ2
すだち 適宜
作り方
- ①鮭は皮を取り食べやすい大きさに切る。
- ②玉ねぎはスライスし、えのきは1/2の長さに、しめじは子房に分ける。
- ③皿に②と①を並べしょうがをのせ、★をかけてふんわりラップで4分チンする。
- ④スライスしたすだちをのせる。
- 管理栄養士さんからの一言
-
えのき
1年中手に入り、価格も安定していて、日本で1番食べられているきのこです。えのきには糖質・脂質・たんぱく質を体内でエネルギーとして使うために必要な水溶性ビタミンのビタミンB1,ビタミンB2,ナイアシンや骨の形成に必要な脂溶性ビタミンのビタミンDが豊富に含まれ、便通を整え生活習慣病の予防・改善に効果のある食物繊維も豊富です。