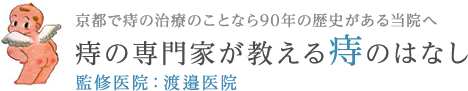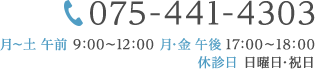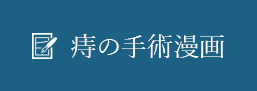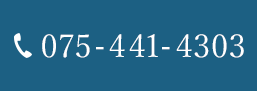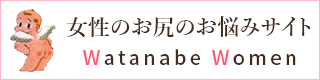「大きな明石焼き」のレシピを紹介します。

12月のレシピは3つのテーマで紹介しています。今回はその中の「お夜食メニュー」と言うことで、その第2弾を紹介します。そのレシピは「大きな明石焼き」です。
レシピの写真をみると一見オムレツみたいですが、大きな明石焼きです。
たこ焼きはよく見かけ、たまに屋台で買って食べたり、たこ焼き屋さん専門のお店の中で食べたり、家で作ったりします。私の家でも子供たちがまだ一緒に住んでいた時は、「今日はタコ焼きにしよう!」と子供たちのリクエストがあったものです。大勢の人数でワイワイ楽しみながら作って食べる。とても美味しいですよね。でも、なかなか明石焼きとなるとあまり食べる機会がありません。家で作ることもありませんし、どう作ったらいいのかわかりません。多分これまで明石焼きを食べたのは本当に数回の数える程度だと思います。
明石焼きについて少し調べてみました。
明石焼きのイメージは、写真の様にお盆のようなものの上に丸い明石焼きが乗っているというイメージです。
明石焼きは兵庫県の明石市で古くから伝わる郷土料理だそうです。明石では明石焼きのことを「玉子焼き」と呼ばれているそうです。ルーツは大正8年に屋台で販売されたのが始まりだそうです。
明石市は人口サンゴを造るのに大量の卵白だけを使うので、余った卵黄を「玉子焼き」として料理に使ったのが始まりだそうです。明石焼きの具は明石の名産のタコが入れられたようです。
明石焼きのメインはやはりあくまで鶏卵。「玉子焼き」なので、小麦粉は繋ぎに少量使うだけだそうです。
また食べ方も、だし汁につけて食べるのに対して、たこ焼きはソースでたべる。ここにも食べ方に大きな違いがありますね。
ではそろそろ「大きな明石焼き」のレシピを紹介しますね。
「大きな明石焼き」

1人分 約250kcal、食塩相当量 1.8g
材料(1人分)
★カットきゃべつ 50g
★卵 1個
★小麦粉 大さじ2
★水 大さじ2
冷凍タコ 30g
塩こしょう
ごま油
ネギ
めんつゆ
作り方
- ①ボールで★を混ぜる。
- ②フライパンにごま油を入れ、解凍したたこを塩こしょうで炒める。
- ③①を入れて両面焼く。
- ④めんつゆをお湯で薄めてつけ汁を作る。
*つけ汁に七味唐辛子を入れても温まります。
「レンジで簡単 クリームパスタ風」のレシピを紹介します。

11月ももう半ばを過ぎました。朝夕だけでなく、日中もグッと冷え込んできました。朝は暖房を入れないと寒いですよね。そしてまた、周りの木々は、一気に紅葉が進んできました。これからは色ずいた木々を見て心癒される時期ですね。
渡邉医院の玄関前のハナミズキも赤く色ずいてきました。
中庭のツバキも薄いピンクで優しく咲いています。
12月のレシピは3つのテーマで作って下さいました。おもてなしメニュー、冬至のメニュー、お夜食メニューの3つです。
今日はまずはお夜食メニューの「レンジで簡単 クリームパスタ風」のレシピを紹介します。
私は受験勉強中はあまり夜食は食べなかっと思います。夜、11時ごろに、そのころ「プロ野球ニュース」というスポーツニュースがあって、家族と一緒にコーヒーや紅茶を飲んでいたのを憶えています。その時ケーキがあったら食べていたかなあ?でもテレビのドラマやCMのような夜食は食べていなかったと思います。私が大学生だったころ、大学の定期試験は約1か月間続きました。そんな大学の時の試験勉強中もあまり間食はしなかったと思います。その代わりインスタントコーヒーの消費がすごかったのを記憶しています。勉強机の横にはポットとインスタントコーヒーが常時置いてありました。
私は試験勉強は夜はしっかり寝る方でした。大学時代の友人はどちらかとゆうと夜型でした。私が寝るときに友人を起こすといった生活が試験中続きました。二人で夕食を食べるときは、試験中は二人の起きている時間に合わせたので、チョット早めの夕食になりました。そのためもあってか、試験勉強中は体重が減った記憶があります。
これからますます寒い季節に入ります。夜勉強をしているときにチョット温かい夜食。気分転換とエネルギー充填にいいですよね。簡単に作れそうなレシピなので是非作ってみて下さいね!
今回はチキンラーメンを使ったレシピ。チキンラーメンもいろんなレシピが出ていますが、そのレシピの一つに今回の「レンジで簡単 クリームパスタ風」も加えて下さいね!
それではレシピを紹介しますね。
「レンジで簡単 クリームパスタ風」
1人分 約280kcal、食塩相当量 1.4g
材料(1人分)
チキンラーメン 1/4袋
冷凍野菜 1/2袋
低脂肪牛乳 200㏄
こしょう 適宜
おにぎり 100g
*今回の冷凍野菜はセブンイレブンの『ベーコンほうれん草』使用
作り方
-
- ①丼にチキンラーメン・冷凍野菜・牛乳を入れ、ふんわりラップをして2分30秒レンジでチンする。
- ②お好みでこしょうをかける。
*おにぎりは中に入れてリゾット風にしてもおいしいです。
- 管理栄養士さんから一言
-
夜食
受験勉強や飲み会の後など、小腹がすく季節です。雑炊やおうどん、サンドイッチもよいですが簡単にできて満足感の出るものを考えてみました。夜に食べるので、エネルギー(カロリー)、塩分も多くならないようにしましょう。
「ALTA療法後の再治療」ー第116回近畿肛門疾患懇談会を終えてー

11月9日に第116回近畿肛門疾患懇談会が大阪で開催されました。できるだけ参加するようにしています。今回もいろんな先生方の発表を聞くことが出来、またそれに対しての他の先生方の活発な発言、討論を通じて、やはり刺激を受けます。また懇談会の後の懇親会では新しく先生と出会うことが出来たり、日常の診療での相談など懇談会の会場ではできない話をざっくばらんに話が出来て、とても参考になりますし、勉強にもなります。
また、以前の相談する立場から、相談される立場になっている。そんな自分に対してもっと勉強しなければと奮起を起こさせてもくれます。そしてそれ以上に楽しい先生ばかりなので、本当に楽しいひと時を過ごすことが出来ます。
「ALTA療法後の再治療」
さて今回のテーマは「ALTA療法後の再治療」でした。
ALTA療法とはジオン注(硫酸アルミニュウム水和物・タンニン酸注射液)という痔核硬化剤を使って四段階注射法と言う方法で痔核硬化療法で脱出してくる内痔核を治療する方法です。手術と違って傷が出来ないので、痛みなく治すことが出来ます。今回はこのALTA療法を行った後に再発した際の治療についての検討でした。
今回の懇談会に参加して私が感じたことについて、今日はお話したいと思います。
ALTA療法の再発とは?
まず私が感じたことは、「ALTA療法の再発と判断する時期はいつなのか?」と言うことです。
発表の中で、出血や脱出など患者さんが何らかの症状を訴え受診された時を再発としたする発表がありました。発表の内容には1か月以内再発症例がありました。ただこれを再発と言うのかどうかです。例えばALTA療法を施行して、出血や脱出などの症状が直ぐにとれ、しかし施行後1か月以内に出血した場合、これは再発なのか?です。この問題はALTA療法後、どのようにALTAが効いてきて内痔核が退縮していくかと関連すると思います。ALTA療法を施行した後、「もう1か月。」ではなく、「まだ1か月。」ではないかと思います。
ALTA療法を施行して直ぐに出血や脱出といった症状がなくなることが多いです。でもこれはまだ治ったわけではありません。症状がとれただけです。ALTA療法施行後、直ぐに症状がとれても1か月ほどたっても出血することはあります。でもこの時点ではまだALTAの効果が出てくる経過の途中ではないかと思います。渡邉医院でもALTA療法施行後1週間後とそこから1か月後に受診していただき、1か月後に出血や脱出などの症状がなければ一応診察は終了としています。でもこの時点で、ALTA療法を施行した部分が触診ではっきりわかることがほとんどです。ですからこの部分が周りと同じように柔らかく乗るまでまだまだ治っていくということです。
1か月たって受診された患者さんでまだ少し出血するという症状がある方はいます。でもその後経過を診ていくうちに出血がしなくなっていきます。ですから出血と言う症状に関しては1か月で再発と判断するのは早いのではないかと思います。
排便時の脱出に関しては、ALTA療法を施行して、1~2週間後に受診して診察する際にまだ脱出してくるといった患者さんがいます。でも次の1か月後の受診の時は脱出してこなくなっています。でも1か月たってもまだ少し脱出するという患者さんもいます。その場合はもう1か月たって受診してもらっています。渡邉医院ではALTA療法を施行して、2か月経っても脱出する場合は、再発ではなく無効例として次の治療に移っています。
このようなことからも、ALTA療法後の再発や無効例と判断する時期を何時にするのかは大切な課題だと思います。
再発を防ぐには。
再発には二つのパターンがあると思います。一つは1年以内の再発と、5~6年以上たってからの再発です。
1年以内の再発に関しては、ALTA療法の適応が正しかったのか?ALTA療法の効きが悪い無効例だったのかなど、ALTA療法の適応をもう一度しっかり検証する必要があります。
また5~6年以上たっての再発ではやはりALTA療法で治癒した後の排便習慣の改善など、内痔核が出来る原因をしっかり治していく必要があると思います。なにも無かったところに排便習慣などが原因で内痔核ができる。ALTA療法で一端治っても、やはり排便習慣のかいぜんがなければ、再度内痔核が発生してきてしまいます。
やはり内痔核自体を治すことと、その原因となる排便習慣の改善のどちらもしっかり行っていく必要があります。
ALTA療法後の治療はどうするか。
ではALTA療法を施行した後再発した場合の治療方法はどうするかですが、今回の懇談会での発表を踏まえて私の考えをお話します。
ALTA療法無効例に対してはやはり痔核根治術が必要です。また、ALTA療法後1年以内の早期に再発した場合も痔核根治術が必要なのかと思います。また再発症例に再度ALTA療法を行った場合、渡邉医院でもALTA療法の再治療が増えるにしたがって再発までの期間が短くなってきます。(ALTA単独療法を施行後10年経過した263例の検討を参考にして下さい)したがって、5~6年以上たっての再発に関してはALTA療法の適応と判断した場合は再度ALTA療法を、しかし次の再発までが1年以内であれば、その時は痔核根治術を考える必要があると思います。
ALTA療法後の痔核根治術は剥離しにくいか?
ALTA療法施行後の手術に関して、剥離しにくく、手術がしにくいのではないかと言う議論もありました。渡邉医院でもALTA療法後に痔核根治術を行うことがあります。でも、今のところ、ALTA療法を施行した後なので、手術がし難かった、剥離しずらかったという経験はなく、通常通りの痔核根治術を行うことができました。
ALTA療法無効例は?
懇談会の中ではALTA療法の無効例の原因は何かですが、一つはALTAと言う痔核硬化剤の患者さんの感受性と言うことが一つの原因になると思います。やはり手術をして切除するのではなく、薬剤による効果で内痔核を退縮させていく治療です。やはりその薬剤と患者さんとの間の感受性も無効となる原因にはなると思います。
もう一つは、内痔核の性状がALTA療法が無効な内痔核であることです。懇談会の中での討論で、「これはALTA療法で十分に治ると思った症例でALTA療法を施行してもまったく効かなかった無効例を経験することがある。」といった意見がありました。やがり内痔核の性状が見た目だけでなく、線維化が進んでいたりする場合はALTA療法が無効になる可能性があるという議論になりました。
ではALTA療法を行う前にどうしたら無効例と判断することができるか?です。これはなかなか難しい問題、課題だと思います。でもなにかこのことを判断するものはないかなと考えてみました。やはり内痔核が排便時に脱出して押し込む第Ⅲ度の内痔核の期間が長いと、その間の炎症もあり、線維化が起きALTA療法は効かない内痔核になるのではないかなと考えます。この仮説を証明するには、患者さんの問診の際に、「排便時に内痔核が脱出して押し込む第Ⅲ度の内痔核になってから何年ぐらい経つか。」ということを聞きその期間とALTA療法の再発期間、無効例を検討する必要があると思います。また脱出してくる内痔核の状態をさらに詳しく検討する必要もあると思います。
少し長くなりましたが、以上が今回の近畿肛門疾患懇談会の報告です。
皮垂(スキンタグ)ってみな同じ?

11月に入って日中はまだ温かさがありますが、朝夕はめっきり寒くなってきました。自宅でも、朝夕は少し暖房を入れています。朝起きて寒いとその日はどんなものを着ていけばいいのかすごく迷う季節です。
またこんな風に寒暖差が激しいと風邪をひいたり、体調を崩されているかたもいらっしゃると思います。体には気を付けて下さいね。
寒さは少しづつ、いや一気にですか?厳しくなってきていますが、紅葉の季節でもあります。これから京都は紅葉目当ての観光客も増えてくるでしょうね。
さて今日は皮垂(スキンタグ)の手術に関して少しお話したいと思います。これまでも何回か皮垂についてやその手術についてはお話してきました。今回は少し違った面からお話したいと思います。
皮垂は一つの病気?
皮垂とは一言で言ってしまうと、肛門にできた皮膚のたるみ、シワのことです。出血や痛みなどの症状は出ませんので、皮垂そのものは病気ではありません。ですから皮垂があってもなにも気にされない方もいます。そういった方にとっては、皮垂は本当にただの皮膚のたるみ、シワでしかありません。こういった場合は治療する意味や目的はありません。
でもその皮垂がどうしても気になる。皮垂があることで、常に不快感がある。また皮垂があることで排便後も強く拭きすぎてしまったりして、皮膚炎になり痒くなったりする症状がでることもあります。このように、皮垂があることで何らかの不快感などの手術がある場合は、その人にとっては病気になります。こういった場合はしっかりと治療する必要があると思います。ただ、その場合は手術をして皮垂を切除するということになります。
皮垂はみな同じ?
では皮垂はみな同じで同じように手術をしたらいいのかです。
この答えは「違う。」です。一言で「皮垂」と言っても「皮垂」が出来る原因はいろいろです。例えば内痔核が原因であったり、裂肛が原因のこともあります。また血栓性外痔核が治っていく過程で皮垂になっていったり。また外痔核そのものが腫れたり治まったりすることでできることもあります。
このように肛門の様々な病気が原因で皮垂はできてきます。ですから一言で皮垂といってもいろんな形態の皮垂があります。内痔核が原因の場合での皮垂は一部肛門上皮内まで連続した皮垂になったり、裂肛の場合は皮膚のシワだけでなく、「見張りイボ」と言われるように、少し硬さのあるいぼ状の皮垂であったり、場合によってはポリープ状になることもあります。できる場所も様々で、内痔核が原因の場合は、内痔核の好発部位である右前、右後ろ、左の3箇所にできることが多いですし、裂肛の場合はその好発部位である前後にできることが多いです。また内痔核と裂肛が合併した場合などそれぞれの後発部位にできることがあります。また血栓性外痔核が原因の場合は肛門のどこにでもおかしくありません。また全周性に内痔核や外痔核が腫れることがあります。こういった場合は皮垂も肛門全周性にできてきます。
このように皮垂はいろんな原因でできてくるので、様々な形態をとってきます。ですから皮垂の切除はそのできた原因や皮垂の形状を見ながら最適な傷で切除する必要があります。
皮垂の原因、形状に合わせて手術をする必要がある。
一律に同じように手術をすればいいというわけにはいきません。もう一つは皮膚のシワが気になり、そのしわを取り除きたいという気持ちが患者さんにはあります。手術後に傷が腫れたりすると、それが治まった時にまた皮垂になってしまう可能性もあります。ですから皮垂の切除に関しては皮垂をただ単に切除すればいいというわけでなく、細心の注意が必要です。それには術後の傷の治りなどをしっかりイメージして最善のデザインを考えて手術する必要があります。
その患者さん一人一人、皮垂は違った形態をとります。その患者さんにあったデザインで手術をする必要があります。
肛門は見た目だけではだめ!
皮垂を切除するときにもう一つ気負付けなければならないことがあります。見た目だけを重視して、皮垂を大きく、そしてすべて切除して、見た目にスッキリさせるという風に手術をしてしまうと困ったことになる可能性があります。
肛門は排便をする際に柔らかく広がることで、気持ちよく便が出ます。ですから手術後に肛門が硬くなったり、突っ張った感じになると、見た目はすっきりしていても排便がスッキリしないなんてことになってしまう可能性があります。
ここでも手術をした後、柔らかく突っ張ることなく傷が治るように手術をすることが重要になってきます。そのためにはやはり、その皮垂のできた原因をしっかり見極め、皮垂の形態をみて、どのように切除することが一番ベストなのかを考え、治った後の肛門の状態をイメージしてデザインし、それに沿って皮垂を切除することが大切になってきます。
こういったことから、皮垂の切除には細心の注意と、治った後の肛門をイメージして手術をすることが重要です。
今進められている医師偏在解消とという名のもとの医師のコントロール

都道府県化された医療制度の下で、国は都道府県に対して病床のコントロールだけではなく、医師偏在解消と言う名の下で、医師のコントロールまで求める事態となっています。病床のコントロールはすでに決められた地域医療構想で今進められています。医師のコントロールに関しては、今国は医師偏在指標を示して、医師少数区域、医師多数区域を決め、医師偏在を解消しようとしています。しかし、今進めている国の政策では、今の現状を変えていくことが出来ないということが明らかです。
なぜこのようなことになってしまうのかを考えたみました。
「医師偏在指標」という指標を国は示しました。しかし、この指標を出すために使ったデータや指標を出すまでの計算式などは一切明らかにしていません。私達が本当にその指標が正しいものか、妥当なものなのかを検証することが出来ません。そういったデータを基にして、机上の計算ではじき出した指標を使って国は政策を進めようとしています。
そして、はじき出された医師少数区域には医師多数区域から医師を確保するというものです。しかし、どういった方法で医師を確保していけばいいのかなどの具体的な方策は示されていません。その方法は国ではなく、各都道府県で考えろという丸投げの状態です。
また、医師少数区域に医師を確保しようとしても、医師だけを確保しても地域には医療を提供することはできません。医師を支え、一緒に地域に医療を提供してくれるスタッフが必要です。医師少数区域には、医師だけでなく、医師以外の医療を提供するために共に働いてくれるスタッフの確保も困難な状況です。
こういったことを考えると、医師偏在を本当に解決するためには、地域をどう活性させていくかが根本的に必要な政策だと思います。しかし、国はこういった根本的な問題に対しての議論を抜きにして、国は医師偏在の理由を医師の「自由」に押し付けています。目先のことだけを考えていても、根本的な問題を解決しなければ、本当の解決策にはなりません。
そもそも、現在医師は十分に足りている。偏在しているのが問題と言った立場に国は立っています。本当に今、医師が足りているのかと言った議論は全くありません。
また、国は424病院の統廃合についても言及し、京都でも4病院がこの対象になりました。ただ、この統廃合を決める項目は手術の数や、がんや脳卒中などの限定された医療で決めたものです。それぞれの医療機関がどのような医療を地域や患者さんに提供しているのか、患者さんがどのような医療を必要としているか、またどんな思いで患者さんがその医療機関を受診しているのかなど全く考慮されていません。そしてこの統廃合の方針が民間の医療機関にも広げられようとしています。
私は肛門科ですが、国の今の姿勢は、お尻が痛いと言って肛門科を受診された患者さんを、肛門の診察をすることもなく、風邪薬を出しているといった印象があります。
本当におかしな状況になっています。
ただただ、国が進めたい政策に都合のいいデータを使って、しかもそのデータなどは私たちには公表せず、そして私たちが検証もできない状況で、机上の計算で解決しようとしてもだめだと思います。
もっと地域の現場に国自らが赴き、地域でどんな医療が提供されているのか。そして地域の医療をそして住民を守るために医療機関がどのような努力をしているのか。そしてその地域で今、何が足らないのか。今、何を支援すれば今の状況が好転していくのか。こういったことを、自らが体験して政策を作り上げていく。そういった姿勢を持たなければ、これから先もなんの解決にならないと思います。
では私達は何をしなければならないかです。国が私たちの地域、現場に来ないのであれば、私たちがしっかりと声を上げて地域の医療の現状を国に届けなければなりません。そして私たちの声をしっかり聴き、それを政策に活かしていく、そういった国にしていかなければならないと思います。
京都に帰ってきて25年を経て、肛門科への思い。

今日は文化の日の振り替え休日。とてもいい天気です。お出かけ日和かなあと思います。
渡邉医院にも今日は庭師さんが入って、剪定を行って下さっています。大分庭の木々は生い茂っていたので、スッキリすると思います。
中庭に山鳩が巣を造りましたが、残念ながら子育てが上手くいかなかったのか親鳥が帰ってこなくなりました。剪定にあたって、子育て中の山鳩の巣をどうしようかと思っていましたが、気兼ねなく剪定してもらうことが出来なあとホットしています。
渡邉医院は90年、私が京都に帰ってきて25年
さて、渡邉医院が開業した正確な年月日は調べたらわかるのかもしれませんが、即答ができません。ただ、私の父が京都で生まれたのが昭和3年。父が京都で生まれたときはもうすでに渡邉医院は開業していたので、そうすると今年で91年を迎えることになります。渡邉医院は肛門科一筋90年と言うことです。この歴史は凄いことだなあと感じます。私も34歳の時に京都に帰ってきて渡邉医院を継承したので、もう25年、四半世紀が経ったことになります。今から思うとあっという間の25年間でした。
今回はなぜこんなことから話が始まったかと言うと、私が京都に帰ってきたのが11月と言うこともあって、以前にインタビューを受けたときの内容を踏まえて、この25年間を振り返ってみようかなあと思ったからです。
渡邉医院の歴史、祖父から父そして私へと3代続いてきました。祖父が渡邉医院を立ち上げ、その思いを父が受け継ぎ今の渡邉医院の基礎を作った。そして私へと繋がれてきました。長い歴史を通じて築き上げた患者さんとの信頼関係、そして肛門科医療へのあくなき探究心、そして患者さんへの思いなど、ちゃんと受け継ぐことが出来ているのか考えてみようと思います。
この間の肛門疾患に関しての変化は?
まず、この間肛門の病気に変化があったかを考えてみました。
基本的には内痔核、痔瘻、裂肛と言った三大肛門疾患で受診される患者さんが多いです。この割合もあまり変わっていないような気がします。それに加えて、最近では「勝手に便が出る」「知らないうちに便が漏れる」といった便失禁でお悩みで、「肛門が緩くなってしまったのでは?」とご相談いただくケースが増えています。
こういった症状は、最近増えてきたわけではないと思います。でもどうしていいのか、誰に相談したらいいのか、また年齢的なことで仕方がないことなのか、また恥ずかしいということもあって、肛門科に受診するきっかけがなかったのかと思います。 でも今は、そうした状況が変わりつつあるのかなと感じています。
肛門科のイメージが変わってきた。
まだまだ肛門科は「受診しにくい」「診察が恥ずかしい」という方がおられると思います。でま最近は肛門科の受診のハードルが段々低くなってきているような印象です。肛門科を受診するのは、内科などの他科を受診するのと変わらないということ、そして診察もイメージされているような恥ずかしいものではないということが、段々患者さんに広がってきているのだと思います。
それを象徴する一つが、ボラギノールのCMかなあと感じています。女子高生がお尻の具合の悪いときはボラギノールと言った内容のCMでした。お尻の病気は年配の男性の病気ではなく、若い女性にも起きて、治療をするんだといった、肛門の病気に対してのイメージを変えたのではないかと思います。このような肛門疾患が極々一般的な病気で恥ずかしがらずに診察を受けましょうといった宣伝、広報が肛門科受診へのハードルを下げていったのかなあとも思います。
患者さんへの心配り。
患者さんへの心配りはどうされていますか?という質問を受けました。
まず答えたのが、患部がどういう状態であれ、「もっと早くに受診しないと駄目ですよ」などとは言わないようにしているということです。
内痔核や痔瘻、裂肛など、肛門の病気は寮生の疾患であることがほとんどです。中にhあ肛門癌や直腸癌で受診される患者さんもいます。でも肛門の病気は基本的には寮生の疾患で、命に関わる病気ではありませんので、患者様が「治そう」と思われた時が受診、そして治療を開始するベストのタイミングだと考えています。
肛門科が身近な存在になりつつあるとは言え、やはり見せにくい部分ですので、なかなか受診しにくい診療科です。そんな中、思いきってお越しになられた方の不安な気持ちに対して十分配慮しなければいけないんだなあと思います。
後、病気の説明や治療方法の説明は解りやすく、そしてできるだけゆっくりと説明することが大切だと考えています。
治療時に大切に考えていること。
また、治療時に大切に考えていることはという質問を受けました。
大切なのは「患者様が何を求めるか?」であって、「私たち医療機関側が何を提供できるか?」ではないと思っています。
例えば内痔核を根治したいということでしたら、入院手術(痔核根治術、ジオン)できちんと治した方が良いでしょうし、今ある痛みを何とかしたい、出血を止めたいということでしたら、外用薬による保存的な治療や日帰りによる痔核硬化療法(パオスクレ―)で対応することが可能です。病状にあわせ、また患者様の希望に合わせて治療を提供することが必要だと思います。
渡邉には19床の入院設備があって、入院手術と日帰り手術の両方に対応可能です。
このことは大切なことだと考えています。こうした環境を活かして、私たち医療機関側の都合で治療方法を制限することなく、最適な方法を複数ご提案して、その中から患者さん自身に一番合うものを選んで治療していくことが大切だと考えています。
また治療方法に関しては、祖父(渡邉医院の創業者)の時代から痔核硬化療法を取り入れるなど、肛門科の治療の歴史とともに歩んできました。でも今の治療方法が決してベストであるとは考えていません。まだまだ治療方法には改良の余地、工夫の余地はあると思っています。
最先端の治療方法を積極的に取り入れる一方で、昔ながらの歴史と実績を持つ治療方法に立ち返り、それぞれをどう組み合わせていくことが良いか、そのベストマッチングを考えるなど、今なお試行錯誤が続いています。
まだまだ進化の途中
まだまだ肛門疾患の治療は発展過程です。
例えば現在、いぼ痔に対する治療方法としてジオンと手術の併用療法が流行っています。ジオンだけでは治りきらず再発することがあり、結果的に根治手術が必要になることがあります。ジオンと手術の併用療法は、根治性を追求すればするほど痔核根治術に近づいていくのが実情です。
こうした状況を見るにつけ、「では、何のためのジオンなのか?」「手術なしで肛門に傷を付けることなく治せるというジオンの最大の利点が失われてしまっているのではないか?」と疑問に思ったり、迷ったりすることがあります。
また手術にしても、毎回終えるごとに「もっと上手くできるのでは?」「もっと患者様の負担が軽減できるのでは?」と考えています。
渡邉医院は90年の歴史があるとは言え、まだまだ治療法は通過点にあり、この先、もっともっと進化させられるはずだと思っています。
手術を受ける際は、必ず緊急時の連絡先を確認しましょう!

いよいよ11月になりました。早いものです。もう今年も後残すところ2か月になってしまいました。テレビでは年賀状の宣伝も始まったようです。
さて、これから京都は秋の紅葉でまた観光地が賑わうのでしょう。渡邉医院の玄関前の通り庭のハナミズキも少し色づき始めています。

皆さんもそれぞれが、「ここが紅葉のおすすめスポット」という場所を持っていると思います。
私は、最近行けていませんが、高台寺の池に映る紅葉がとても幻想的で、引き込まれていくような感情が湧き出てきます。現実とは違った別世界にいるような感覚も覚えます。いつまでも時間を忘れて観ていることができる。そんな気持ちになります。自然が私たちに与える力。計り知れないものがあると思います。
また景色だけでなく、色ずいた葉を一枚見ているだけでも、緑から赤、そして黄色や茶色。その彩には引き込まれています。渡邉医院の玄関前の通り庭にあるハナミズキのの高揚した葉一枚の絵を描いたことがあります。この絵も紹介しますね。
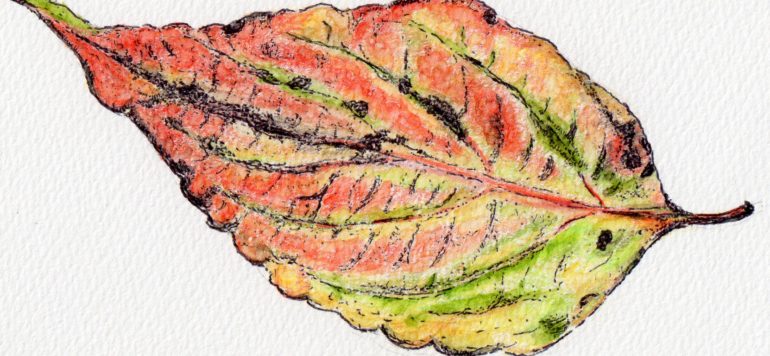 手術を受ける際は、緊急連絡先の確認を!
手術を受ける際は、緊急連絡先の確認を!
さて、今回は手術を受ける際、緊急の際の連絡先を必ず医療機関に聞いておくことの大切さをお話します。
渡邉医院は19床の有床診療所です。入院できるベッドが19個あって入院施設をもった診療所と言うことです。
渡邉医院では、内痔核や痔瘻、そして裂肛などに対して根治術を行う場合は、最低でも1泊2日の入院での手術をお勧めしています。
入院での根治術を勧める理由。
その理由として、やはり術後は痛みや出血など、患者さんにとって不安になる要素があるということです。患者さんにとっても手術は初めての経験であることがほとんどです。術後の症状で大丈夫なこと、大丈夫でないことの判断を患者さん自身で行うことはとても難しいことだと思います。そういった時、心配なことや不安なことがあった場合、入院しているとすぐに聞くことができ、不安を解消することができます。また出血などの場合、止血処置が必要な場合は、直ぐに対応することが出来ます。手術を行った後、24時間以内に起きる出血を早期出血と言います。この早期出血が無ければ、痔瘻や裂肛に対しての根治術の場合は、また麻酔をして止血しなければならない出血はまず起きません。内痔核の場合は、晩期出血と言って、術後7~10日後に内痔核の根部を結紮した部分から止血処置をしなければならない出血があります。でも早期出血が無ければしばらくの間は、止血処置をしなければならない困った出血は起きません。
入院での手術は安心感がある。
こういったように、入院することで、患者さんにとって不安を取り除くことが出来ます。また医師側にとっても、何か緊急を要する場合は直ぐに対応できるということで、患者さんと同様、安心感があります。このような理由で入院での治療をお勧めしています。
日帰り手術や外来での手術を受ける場合。
ただ、患者さんの状況などで、日帰り手術を行うこともあります。また根治術だけでなく、血栓性外痔核に対しての血栓摘出術や肛門周囲膿瘍に対しての肛門周囲膿瘍切開術。また、皮垂の切除術など、外来での手術をすることも少なからずあります。こういった、入院することなく手術を受ける場合に一番大事なことは、術後の出血などがあった場合に、直ぐに医療機関と連絡が取れる体制をとることです。
肛門の手術をして、術後に出血して止血処置をしなければならないことは、そう多くはありません。でも絶対に起きないということも言えません。ですから、術後に何か心配事や不安な時に直ぐに手術を受けた医療機関と連絡がとれる体制をとっておく必要があります。それは出血だけに限りません。手術を受けると、いろんなこと、ちょっとしたことでも不安になることがあります。
それは手術という経験したことのない経験に対して患者さん自身が自分で判断しなければならないというところにあります。でも、患者さんは医師でも看護師でもありません。医師や看護師のこともありますが、それでも肛門の手術は経験がないことが多いです。そういった場合、これは放っておいてもいい症状なのかどうかを判断することはできません。そういった場合にその不安を解消するには手術をした医師や医療機関に聞くしか手立てはありません。ですから手術を受ける場合は何か不測の事態が起きた場合の医療機関との連絡できる体制をとっておかなければなりません。
手術をする医師、医療機関では緊急時の対応体制はとっています。
手術をする医師や医療機関では、出血など、なにかことが起きた場合に直ぐに対応する体制はとっているはずです。
緊急時には迷わず連絡を。
ですから、手術を受ける場合は、緊急時に対応できる連絡先を事前に確認しておく必要があります。また何か緊急なことがあった場合は迷わず連絡して相談してくださいね!
妊娠中も、お尻の治療は可能です。

もう11月になりますね。今年も残すところ後2か月になりました。日中はまだ温かい感じがありますが、朝夕はもう肌寒くなってきました。
町中の木々も少し色づき始めています。渡邉医院の玄関前の通り庭も少し赤く色づき始めてきました。これからは紅葉の季節になってきますね。

これから徐々に寒さが厳しくなってきます。風邪などひかないように気をつけて下さいね。また、そろそろインフルエンザのワクチンも接種しましょうね。

妊娠出産後も肛門の症状がなければ治っているということです。
さて、女性の患者さんの中には、「出産してからお尻の具合が悪くなりました。」とおっしゃる患者さんもいらっしゃいます。そして、妊娠出産をした時に具合が悪くなったあと、ずっと内痔核などの痔を持ち続けていると思っている方もいます。でもそうではありません。その時に悪くなっていても、今現在、出血や違和感、場合によっては排便時の内痔核の脱出などの自分が感じる症状がなければ、もう治っているということです。以前にお話しましたが、肛門の病気は必ず症状が出ます。例えば出血、痛み、腫れ、違和感など自分が感じる嫌な症状が必ず出ます。なんの症状も無いということは、すでに肛門の病気は治っているということです。
妊娠出産で悪くなる肛門の病気は。
女性の方が妊娠出産によって悪くなる病気には大きく二つあります。一つは内痔核です。そしてもう一つは血栓性外痔核です。
一つ目の病気、内痔核。
内痔核の具合の悪くなる原因は、どうしてもお腹の中の赤ちゃんが大きくなってくると、肛門のところにある静脈の流れが悪くなってきます。また便秘になることもあって、排便時に頑張ることによっても内痔核は悪くなってきます。ですから妊娠して、その後便秘になってくるようでしたら、酸化マグネシウムの様に、お腹の中の赤ちゃんに影響のない緩下剤を内服して、具合よく便が出るようにしていく必要があります。
また、出産の際にどうしても強く力むことになります。この時に内痔核が悪化することがあります。ただ妊娠前に内痔核が無かった方は、出産時に内痔核の主張が強くなっても、無事赤ちゃんが生まれると、内痔核の状態がスッと良くなってきます。やはり、妊娠前から内痔核を持っている方は妊娠出産で、その内痔核が悪化してくることがあります。ですから妊娠前に今ある内痔核を治しておいた方がいいと思います。
妊娠中も治療は可能です。
では、妊娠してしまったら、内痔核の治療ができないわけではありません。
妊娠3か月から9か月までの間でしたら、ほとんどどんな治療も可能です。
早期のうちでしたら軟膏などの外用薬での治療。また外用薬では良くならずに、違和感や出血が続いたり、排便時に少し脱出してくる内痔核に対しては、パオスクレーと言ってアーモンドのオイルの中に5%の割合でフェノールが入っている痔核硬化剤を使っての痔核硬化療法をすることも可能です。
また、内痔核に血栓が詰まって脱出したままになり、痛みが強い嵌頓痔核になった場合も、局所麻酔下に痔核根治術をすることもできます。ただ痔核根治術を行う場合は、術後7~10日後に内痔核の根部を結紮した部分から晩期出血と言って止血をしなければならない出血が起きることがあります。ですから術後は慎重に経過を診ていく必要はあります。
でも、このように内痔核に対しての治療は妊娠中でもほとんどのの治療が可能です。
もう一つの病気、血栓性外痔核。
もう一つの血栓性外痔核ですが、やはりお腹の中の赤ちゃんが大きくなってくると、どうしても肛門の静脈の流れが悪くなってきます。また、出産に備えて血が止まりやすいように体がなってきます。このことは血栓ができやすくなるということにもなります。またストレスがかかることで、血小板がくっ付きやすくなって、血栓ができやすくもなります。こういったいろんな条件がそろってしまって、最後は排便の時に強く力んだり、重たいものを持ったりして腹圧がかかった時に血栓が詰まって血栓性外痔核になることがあります。
血栓が詰まって腫れるとやはり痛みが出てきます。ただ、基本的に、血栓が詰まって腫れて痛いということなので、自然に腫れが引いてきて、痛みがとれ、血栓は徐々に溶けて体に吸収されていきます。
少し違いますが、どこかをぶつけて内出血して腫れて痛いと同じです。腫れは段々引いて、痛みは取れますが青い内出血は残ります。でもそれも徐々に薄くなって小さくなって吸収されていきます。
これと同じで痛みはありますが、必ず血栓は溶けて吸収して治っていきます。
血栓性外痔核で痛みが強い場合は手術を。
でも痛みがとても強い場合は、局所麻酔をして血栓を取り除くことで痛みはスッと楽になります。また内痔核の手術と違って、動脈を結紮する部分がないので、内痔核の手術の様に動脈からの1%の出血もありません。
強い痛みをずっとこらえているののも妊婦さんにとってとてもストレスです。お腹の中の赤ちゃんにもお母さんが痛みをこらえてストレスを感じ続けることはよくないのではないかと思います。こんな時は局所麻酔で血栓を取り除いた方がいいと思います。
妊娠出産で必ず肛門の病気になるわけではありません。
妊娠出産で必ず肛門の病気になるわけではありません。もし妊娠前に内痔核などの肛門の病気があるのならば治しておいた方がいいと思います。また、妊娠中に内痔核の具合が悪くなったり、血栓性外痔核になったとしても、なにも治療できないわけではありません。手術を含めて、たいていの治療は可能です。

妊娠前、妊娠中、そして出産後に肛門のことで心配なことや不安なことがあるようでしたら、是非、肛門科を受診して相談してみて下さいね。
術後、出血や痛み以外に患者さんが気になる症状

今日は、朝方は雨が降っていたのでしょうか、地面は濡れ、車も雨粒が付いていました。空はどんより曇っていましたが今は秋晴れ、いい天気です。
今日も、入院の患者さんや手術をしたばかりの患者さんの診察をしに、診療所に行ってきました。渡邉医院の中庭に巣を造った山鳩も、今日もしっかり卵を抱いていました。そろそろ雛が孵るころかなあと思います。

日曜日や祝日に入院の患者さんを診察すると、患者さんは「先生は休みがないんですか?いつ休んでいるのですか?」と聞かれます。休みの日に、患者さんの診察をして元気なところを確認すると、その後は当直の人に任せてゆっくり休んでいます。何かあった時は直ぐ診療所に駆け付けるのですが。患者さんの元気なところ、笑顔を見ることで私も元気になれます。
さて今回は、手術をした後の経過で、患者さんが共通して気になるであろう点について少しお話したいと思います。
患者さんが気にされる多くは、術後の痛みは何時まで続くのか?出血は何時まで続くのか?困った出血が起きないかだと思います。でもこれ以外に気になることについてお話します。
手術をして2日目、術後2日目に患者さんにお話することをお話します。
術後黄色い汁や膿のようなものが出るのは、化膿したから?
手術をした当日は、やはり手術をしたばかりなので、どうしても傷口からの出血が多いです。そのため厚めに綿花を当てて、T字帯で押さえます。でも次の日になると出血はグッと減っていきます。怪我をした時と同じです。怪我をした時は結構血が出ますが、次の日は同じ傷があっても出血しなくなります。これと同じです。
出血が減ってくると、今度は黄色い汁のような、膿のようなものが当てている綿花につくようになってきます。患者さんはこの黄色い汁のような、膿のようなものを見ると、便が通るところなので、「化膿してしまったのでは?」と心配されます。でもこれは化膿したわけではありません。
どうしても傷ができるので、傷口からは浸出液が出てきます。また肛門の手術なので、粘液も増えてきます。また内痔核の場合は、内痔核の根部を糸で結紮して切除するのですが、結紮して切除した後の断端が少し残ります。この部分が根部を結紮しているので、段々壊死して取れてきます。これらが混ざり合って黄色い汁のような、膿のようなものになります。
術後の臭いの原因は?
特に結紮して切除した後の断端が壊死して取れていくのが大きいと思います。また、この壊死して脱落していく期間、少し嫌な臭いがします。この臭いが気になる患者さんもいます。
このように術後、出血が減ってくると、黄色い汁や膿の湯なものが付いたり、臭いが気になってきますが、傷が治っていく経過なので、心配はいりません。
排便後に当てた綿花に汚れが付くのは?
もう一つ、術後便が出るようになると、軟膏を塗った綿花を傷口に当ててもらうのですが、排便後に当てた綿に便などの汚れが付くことが気になってきます。これは手術のために肛門が緩んでしまったからではありません。
この汚れの原因は、内痔核や痔瘻などの手術をする際に肛門管内に傷が出来ます。排便の時、どうしてもこの傷に便が引っかかります。でも引っかかったままになっていると、そので炎症を起こしたりして、いつまでたっても傷が治らなかったり、いつまでたっても痛みが続きます。排便の時に、肛門管内の傷に便が残らないように、ドレナージという傷を肛門の外に作ります。排便後、肛門管内の傷についた便まで洗ったり、拭いたりすることはできません。ドレナージという傷が、排便の際に肛門管内の傷に引っかかった便を外に出るようにしてくれます。そして綿花に塗った軟膏がその汚れを取ってくれます。ですから基本は、1日に2回、朝晩の軟膏塗布でいいのですが、排便があった時は軟膏を付けることで汚れも取ってくれます。
肛門管内の傷が治ると、排便時も便が引っかからなくなるため、こういった汚れもつかなくなります。
こういったことが、術後の傷の痛みや出血以外に患者さんが気になる症状となります。
以前、お話しましたが、術後スッキリ治らないと必ず何らかの症状が出ます。気になる症状がなくなった時、傷は治ったということになります。
術後、気になる症状は医師に相談しましょう!
どうしても肛門の手術は、自分で見ることが出来ません。心配な時 は必ず、医師にきいて、心配事や不安を取り除きましょう。
患者さんの不安を取り除くには。

患者さんが治療を受けるとき、特に手術を受けるとき、麻酔の痛み、手術の際の痛み、そして術後の痛みなど多くの不安を抱えています。漠然とした怖さもあると思います。
病気の説明やそれに対しての治療方法、手術方法などをしっかりとお話しますが、どんなにお話して説明しても、絶対に不安や怖さを取り除くことはできないと思っています。
そんななか、患者さんは自分の病気を治そうと手術を受ける決心をされます。手術を受ける不安や怖さがある以上に、今の病気をしっかり治しておきたいという思いが勝るのだろうなあと思います。手術をして治そうと思う気持ちを私たち医師は真摯に受け止め、その決意にしっかり答えなければならないと思います。
どこから不安は生まれるのか?
ではどこから不安や怖さが生まれてくるのでしょうか?
それは医師の説明を聞いても、それは話だけを聞くことです。また、いくら図に書いて説明してもそれは二次元の紙の上だけのこと。実際にどのように手術が進んでいくのか、そして術後はどのように経過していくのかなど、まったく患者さんは解らないところにあるのだと思います。
頭では理解していても、実際に現実ではどうなるのかが解らない、そしてイメージがわかないところにあるのだと思います。
あらかじめ経験できない、経験が生かせない。
話は変わりますが、例えば知らない場所に初めて出かけるとき、周りに見える景色は初めての景色、どのくらいで到着するのかなど考えると、到着までの時間がすごく長く感じることがあります。2回目に行くと、周りの景色は知っているし、だいたいどのくらいで着くのかも予想できます。始めていくときよりもすごく早く到着するような感じになります。やはり、一度経験したことを2回目以降経験するときは、これまでの経験を生かすことができますし、不安はある程度取り除くことが出来ます。でも手術となると、何度も経験するわけにはいきません。できれば1回の手術で完治させたいです。また手術は何回も経験するものではありませんし、一度経験すると二度としたくないと思う方がほとんどだと思います。
不安を取り除くには、具体的な数字を示してイメージが湧くようにすること。
ではその初めての手術の不安や怖さを少なくさせる方法は何でしょう。
やはりその一つは、麻酔はどうするのか、局所麻酔ならば、最初は麻酔の針をさす痛みがありますが、麻酔したところを麻酔していくので、途中からは麻酔が効いてくるので麻酔をする痛みもとれること。また、手術の方法やどのように手術が進んでいくのか。またどのくらいの時間で終わるのか具体的な数字を伝える、例えば1箇所の内痔核を手術する時間は10分程度、3箇所の場合は約30分とか。また実際に手術をしている時は、今どのくらい進んで、後何分ぐらいで終わるかなど、やはり具体的な数字を伝え、患者さんがイメージできるようにすることも大切だと思います。
また術後の経過も同様に具体的な数字で伝えること。
例えば術後の痛みに関しては、局所麻酔は1時間で切れること。その時肛門が締まってくるので、痛みが出ること。でも1時間たって麻酔が完全に切れたほうが痛みが楽になることを伝える。
そしてその痛みに対しての対象方法はどうするのか。術後1時間後には、痛みがあっても無くても消炎鎮痛剤を内服すること。術後3時間後には消炎鎮痛剤の座薬を挿入すること。その後は痛みがあっても無くても消炎鎮痛剤の内服を夕食後、寝る前、そして次の朝に内服して痛みに対処していくことをお話する。また、排便時の痛みに関しては、96.5%の患者さんが、術後7~10日過ぎるとスッと痛みが取れること。
また術後の出血に関しては、術後1時間後に出血の有無を看護師が確認し、術後3時間後には医師が出血の有無を確認すること。そして3時間後の出血が無ければ大丈夫であること。
また、術後の出血に関しては、内痔核の場合は、術後24時間までに起きる早期出血と、術後約7日目頃に起きる晩期出血の二つの出血が止血処置を必要とする出血であること。そして、晩期出血は約1%であること。
どうしても排便の時は便が傷を擦って出てくるので、出血することがあるがこれは大丈夫であること。でも心配な時は迷わず出血が大丈夫なものなのかそうでないのかを聞いて欲しいということ。患者さんが感じるであろう不安を、その不安が出る前に先手先手で適切にタイミングで話をしていくことが大切だと思います。
患者さんが不安を感じるであろうことを、不安を感じる前に先手先手でお話する。
体験者の話を聞くことも不安を取り除く方法。
また、渡邉医院の談話室に、患者さんが手術など入院中のことや、これまで痔で悩んでいたことを書いたノートが置いてあります。体験者の話を聞くことも患者さんの安心感いつながることがあります。やはり、実際に体験した人の話を聞くことは説得力があります。「早くこのノートを見ておいたらよかった。」という患者さんもいます。ただ、個人個人で術後の経過が違うこともお話しなければならないと思います。
患者さんが必要とするときに正しい情報をタイミングよく伝えること。
やはり、正しい情報を患者さんが必要な時にしっかりと伝えていくことが、患者さんの不安や怖さを取り除く方法になるのだと思います。