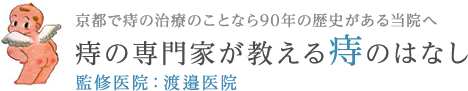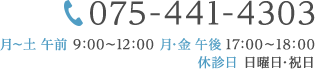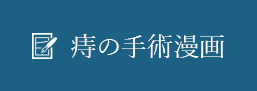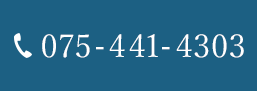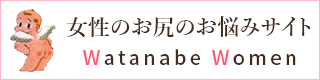「ケークサレ」のレシピを紹介します。

12月も半分が終わりました。今年ももう直ぐ終わってしまいますね。早いものです。
年末に向けて、クリスマスや忘年会などまだまだ行事ごとは続きますね。
ここ数日、少し寒さが和らいでいるような気がします。
渡邉医院の中庭の紅葉は、少し遅いですが赤く色づき、今が見ごろになっています。
玄関前のハナミズキは、残っていた最後の葉も落ちてもう冬です。

山茶花は蕾もまだまだありますが、こちらも見ごろかなあと思います。

さて、今日は「ケークサレ」のレシピを紹介しますね。
今回も「ケークサレ」と聞いて「それって何?」と思いました。チョット調べてみると、フランス料理で、塩味のきいた甘くないケーキと言うことです。
キッシュに似ていて食事のおかずや、お酒ののつまみ、またおやつにもいいようです。見た目はパンケーキです。
ケークサレは「sale(サレ)」=塩、「cake(ケーク)」=ケーキの意味だそうです。チーズや野菜、肉などを具として入れてパウンドケーキ型で焼いた料理です。
お正月にもいいですが、これから迎えるクリスマスの料理の一品でもいいかもしれませんね。クリスマス風にデコレーションしたら豪華になりますよね。
では「ケークサレ」のレシピを紹介します。
「ケークサレ」

1本分 約700kcal、たんぱく質 約30g、食物繊維 約10g
材料(2本分)
ホットケーキミックス 1袋(150g)
おからパウダー 30g
卵 2個
牛乳 100cc
オリーブオイル 大さじ2
ブロッコリー 1/4本
玉ねぎ 1/2個
にんじん 5cm
かぼちゃ 5cm角
ベーコン 80g
チーズ 30g
作り方
- ①牛乳パックを立て半分に切り、口の部分をホッチキスでとめて、深さ3cmの焼型を2つ作る。
- ②具材をすべてコロコロに切る。
- ③ブロッコリー、人参、かぼちゃはゆでるか電子レンジでチンする。
- ④玉ねぎ、ベーコンはフライパンで炒める。
- ⑤ボールにホットケーキミックス、おからパウダー、卵、牛乳、オリーブオイルを混ぜ、③④チーズを混ぜて、①の型に半分ずつ流す。
- ⑥180℃のオーブンで20~30分焼く。
*オーブンがなければフライパンでホットケーキのように焼いても、マグカップに入れて電子レンジでチンして蒸しパンにしてもおいしいです。
追悼・中村 哲医師

12月に入って、訃報が突然報道されました。
それは12月4日、アフガニスタンの地で人道的支援を行ってきたペシャワール会の現地代表、中村哲医師が銃撃され命を落とされたという報道でした。
突然の報道に驚きました。というのも、中村氏には、京都府保険医協会の第66回定期総会で「アフガニスタンに命の水をー国際医療協力の30年―」という講演をしていただいたことがあるからです。
アフガニスタンの住民の命は医療だけでは守れない。飢えや渇きは薬では治せない。こう考えた中村氏は、命を守る水の確保のため、診療所の近くの井戸の再生を始められました。最終的には1600か所になりました。また、「緑の大地計画」を立ち上げ、大河川から水を引く灌漑用水建設を始め、荒廃した大地の再生に取り組まれました。なぜ、アフガニスタンの地でこのような取り組みができたか?ある対談記事にこう語っておられました。
「僕は憲法9条なんて、特に意識したことはなかった。でもね、向こうに行って、9条がバックボーンとして僕らの活動を支えていてくれる、これが我々を守ってきてくれたんだな、という実感がありますよ。体で感じた想いですよ。政府側も反政府側も、タリバンだって我々には手を出さない。むしろ、守ってくれているんです。9条があるから、海外ではこれまで絶対に銃を撃たなかった日本。それが、ほんとうの日本の強味なんですよ。」
そんな中村氏が銃弾に倒れました。
今、日本をアフガニスタンの人々はどうみているのでしょうか。平和憲法を捨て、戦争が出来る国に向かっているとみているのかもしれません。
今回は少し長くなりますが、中村哲医師の追悼の意味で、2013年の京都府保険医協会の第66回定期総会での講演の内容を紹介したいと思います。
この記事は、京都府保険医協会・京都保険医新聞第2880号より転載いたしました。
講師の中村哲氏
医師。ペシャワール会現地代表。PMS(ピース・ジャパン・メディカル・サービス)総院長。1984年パキスタンのミッション病院ハンセン病棟に赴任。その傍ら難民キャンプでアフガン難民の一般診療に携わる。1989年よりアフガニスタン国内へ活動を拡げ診療を開始。2000年からは旱魃が厳しくなるアフガニスタンで飲料水・灌漑用井戸事業を始め、2003年から農村復興のため大がかりな水利事業に携わり現在に至る。
アフガニスタンで30年におよび医療と農業の復興支援活動を続けるペシャワール会。「飢えと渇きは薬では治せない」と1600本の井戸を掘り、2003年からは農業用水路の建設を開始した中村哲医師を講師に、2013年7月28日開催の第66回定期総会で記念講演会を開催した。以下、概要を紹介する。
みなさん、こんにちは。本日は、アフガニスタンで何が起きたのか、今何が起きつつあるのかについて、私の活動を通して紹介したいと思います。その中で1人の医師として黙っておれないこともたくさんあります。そういったことについてもぜひ知っていただきたいと思っています。
アフガニスタンという国
アフガニスタンは日本人にとって世界でもっともわかりにくい国のひとつだと思います。実は30年活動してきた私自身もいまだよくわかりません。
私が医学部を卒業したのが1973年です。それから40年後、まさか自分がアフガニスタンの川の中で重機を自ら運転して作業していることになるなんて、想像できませんでした。人生というのは思うようにならないものだとつくづく思います。
簡単に現地の説明をいたします。日本ではペシャワール会といいますが、現地ではジャララバードという町を拠点に、PMS(PeaceJapanMedicalServices)という団体が活動を続けており、財政を支えているのがペシャワール会です。両団体はそういう関係です。
アフガニスタン、あるいはパキスタンがわかりにくいことの一つに、国境がはっきりしないことがあります。私たちの活動の中心は両国の国境地帯です。もちろん国際法上の国境はありますが、しかし実際の人びとの生活において、どこまでがアフガニスタンでどこまでがパキスタンなのかよくわかりません。事実上国境がないのに国際法上は存在しているといった状況なのです。
ペシャワールは現在戦乱のちまたで、そのためPMS本部をジャララバードに移して活動を続けています。PMSは医療団体で、現在も診療所を運営しておりますが、活動の主体は水路工事です。これについては後でくわしくご説明します。現地には職員百数十人がおりまして、日本のペシャワール会に寄せられる募金に頼って活動が続けられております。
アフガニスタンは山の国です。日本でいうと、長野県や山梨県を大きくしたような国です。国中、山だらけです。面積は日本の1・7倍、人口は2000万人前後です。それぞれ深い谷ごとに違った民族が居住するといってもいいくらい、多くの民族によって成り立っている複合民族国家です。各民族に共通していえるのは、国民の9割以上が農民、または遊牧民で、都市生活者は元来少なかったということです。かつての食糧自給率は96%で、ほぼ自給自足に近い農業国でした。
中央アジアの乾燥した地域で、どうしてそれだけの人びとを養えたのかというと、山々に降り積もる雪のおかげでした。ヒマヤラ山脈を西に行くと、カラコルム山脈、ヒンズークシ山脈という高い山々がありますが、このヒンズークシ山脈がアフガニスタンのほとんどの部分を占めています。6000メートル、7000メートルを超えるこれらの山々に雪が積もり、氷河をつくっています。それが夏に少しずつとけてきて、何万年か、何十万年かわかりませんが、川沿いに豊かな実りを約束します。この水により、人も動物も植物も命を永らえてきた。現地の有名な言葉に、「アフガニスタンでは金はなくても食べていけるが、雪がなくては食べていけない」というものがあります。
もう一つ、アフガニスタンを特徴づけるのは、谷ごとに国があるといっていいくらい、いろんな民族の人たちが住んでいることです。悪くいえば地域の割拠制、良くいえば地域の自治制が非常に濃厚なところです。我々は「国」というと、中央集権的な政府があって、法律一下、国中が治まっているという状態を想像しますが、アフガニスタンはそれぞれの地域が大事なことは自分たちで決める。それのまとめ役としてシンボル的に政府が存在する。
例えば隣の村で侵入してきた勢力に対して戦闘が行われているときに、その隣の村は中立を守っているということだってあるのです。こういった国の在り方というのは明治以前の日本では見られましたが、なかなか現在の日本では分かりにくい点があります。
三つ目の特徴として、国民の100%近くがイスラム教徒であることです。しかも現存するイスラム教徒の中ではもっとも保守的です。保守的だから悪いということではありません。彼らはイスラムの伝統に従い、さまざまな民族が暮らしている中で、かろうじて彼らのまとまりをつくっています。イスラム教を抜きにアフガニスタンを語ることはできません。
どんな町や村に行っても、大きなモスクがあります。モスクが地域の中心になっており、そこでいろんなもめごとが解決されていくのです。共同体の要をなしている伝統的な文化なのです。
現地の文化を受け入れるということ
私たちの活動はハンセン病のコントロール計画から始まりました。しかし、実際努力の大部分は、一見医療とは関係がないと思われるところです。そこにエネルギーを費やしてきました。中でも苦労するのが、患者の気持ち、その地域に暮らしている人たちの気持ちをいかに理解するかということです。
外国人が犯しやすい過ちは、自分が見たことがないもの、見慣れないものに遭遇すると、つい自分たちの物差しで判断してしまうことです。このことで現地とのトラブルが絶えず、志半ばで帰国してしまう外国人が非常に多いのが現実です。
私たちは、現地の習慣を変えるために医療をしているわけではありません。人の命が助かるために仕事をしているわけです。私たちがその地域の文化にかかわる際には、好き嫌いの問題はあろうけれども、いっさい批判的な目で見ない、それをそのまま受け入れることを鉄則にしています。
たとえば、女性の被り物(ブルカ)について、その是非が世界中で議論されていますが、被り物をまとうかどうかはその地域の人が決めていくことであって、外国人がとやかくいうことではありません。
戦争に巻き込まれる
私たちが活動を始めた1984年はアフガン戦争のまっただ中でした。アフガン戦争とは78年12月、当時世界最強の陸軍といわれたソ連軍の精鋭部隊約10万人が大挙してアフガニスタンに侵攻することではじまった戦争です。以後約9年間、アフガニスタンは戦乱の中に置かれ、この戦争で死亡した人は200万人、さらに600万人もの人が難民となって国外に逃れる事態になりました。先ほど申し上げましたが、私たちが活動を始めていた地域はパキスタンですが、アフガニスタンとの国境は事実上は明確なものではありませんので、私たちもこの戦争に巻き込まれていくことになったのです。
私たちは、戦争が下火になった暁には、ハンセン病多発地帯、すなわちそこは他の病気の多発地帯であり、しかも医療施設がほとんどないという地域ですが、そこに診療所をつくり、一般診療を行いながら、ハンセン病も他の感染症の一つとして特別扱いすることなく診るという方針を立てました。その方針のもと少しずつ動き出したわけです。
当時、表向きは国境は閉鎖されていました。しかし先ほども申し上げた通り、アフガニスタンとパキスタンとを隔てる2800キロメートル全体を閉鎖することは絶対できません。我々も山を越えて診療所開設予定地の人びととつきあいを深めていきました。
88年ソ連軍の撤退がはじまると、ただちに診療所開設の準備を始めました。91年から92年にかけて、戻ってくる難民たちを迎えるような形であちこちに診療所を建てていきました。
そうこうするうちに15年が経ちました。先はまだ長いということを悟り、98年ペシャワールの一画にPMS基地病院を建設しました。新たな活動の第一歩です。日本からの補給がある限り、何十年でもがんばろうという体制ができたわけです。
人類史上例をみない大干ばつ
ソ連軍が撤退した後もごたごたが続きましたが、タリバン政権の登場により国は落ち着きを取り戻しはじめました。政治的、宗教的なことは別として、この30年間でアフガニスタンでもっとも治安のよかったのはタリバン政権の時期です。路上に物を置いてもなくなることがないほどです。我々の仕事もこれでやりやすくなると思った。しかしその矢先に襲ってきたのが大干ばつでした。
2000年5月、WHO(世界保健機関)が世界中に訴えた内容は鬼気迫るものがありました。現在進行中の中央アジアにおける大干ばつは、13年の今も進行していますが、これは人類が体験したことのない規模であり、中でももっとも激烈な被害を受けているのがアフガニスタンである。被災者1200万人、国民の半分が被災し、うち600万人が飢餓線上にいる。さらに100万人が餓死線上にいる、というものでした。
01年のアメリカによるアフガニスタンへの空爆前というのは、このような状況だったのです。我々の診療所の周辺でも、見る見るうちに村が消えていきました。昨日まで住んでいた人びとが今日になるともういなくなる。まったくひどい状態でした。しかもそれは今も進行中なのです。なぜこのことが世界中に知られていないのでしょうか。不思議でなりません。ときおり報道されることといえば、タリバンとの和平交渉がどうなるか、あるいは外国兵が何人死に、タリバン兵、市民が何人死んだのか、ということばかりです。人びとが困っている肝心な点についてはほとんど報道されることはありません。
空爆前にもっとも多かった病気は、腸管感染症、とくに赤痢でした。農業ができず、食べ物を手に入れることができなくなり栄養失調になる。それで免疫力が低下する。とくに子どもですが、咽の渇きに耐えきれなくて汚水を飲んでしまう。今日の日本で赤痢で死ぬ人はいませんが、脱水状態になると、アフガニスタンは簡単に死んでしまうのです。
子どもが一番の犠牲者でした。飢えや渇きは薬では治せません。とにかく水を確保しなくてはならない。我々は、まず診療所の周囲の枯れた井戸の再生をはじめました。00年8月から数年間続け、最終的には1600カ所に清潔な飲料水を獲得することができました。これは20数万人の村人が難民化することを食い止めるという大きな仕事に発展しました。
空爆では解決しない問題
そうこうしているうちに、01年9月11日を迎えます。ニューヨークでテロ事件が発生、そのテロ首謀者の属するアルカイダの頭目が当時のタリバン政権にかくまわれているということで、事件の翌日からブッシュ大統領は「アフガンに報復爆撃を行う」「十字軍を引き起こす」と発言しました。私自身、キリスト教徒でありますが、十字軍などと物騒なことは聖書のどこにも書いてありません。しかも報復爆撃などという野蛮な行為は到底認められるものではありません。
アフガン問題とは水と食糧の問題であって、爆弾で解決する問題ではありません。当時カブールに残っていた百数十万人の人びとのほとんどは、もともとのカブール市民ではありません。干ばつで食べられなくなり田舎から逃れてきた国内避難民です。まず彼らに食べ物を届けようと、日本で支援を呼びかけ寄付を募り、1800トンの小麦粉を空爆下で配給しました。
これに従事したのは我々の職員20人です。彼らはまさに決死隊です。当時の日本での報道では「アメリカの空爆はピンポイント攻撃といって、テロリストだけをやっつけて一般市民には迷惑をかけない人道的な爆撃である」と解説されていました。
しかし、実際は無差別爆撃でした。爆撃で亡くなったのはほとんどが逃げ足の遅いお年寄りや女性、子どもでした。そういう空爆下での食糧配給でしたが、幸い無事にやり終えることができ、この配給がなければ餓死したであろうカブール市民10数万人の命を救うことができたのです。PMSの活動は私一人でやっているように思われていますが、実際は同胞のためなら死を顧みないというこのような勇敢な職員たちの手によって進められてきたのです。
映像の力はものすごいものがあります。01年11月になるとタリバン政権がスッと首都から消えます。その後北部同盟というタリバンとはライバル関係にあった勢力がアメリカの後押しで首都に入ってきます。このときに、世界中が映像の力により騙されてしまいます。悪の権化タリバンを追い出し、自由と正義の味方のアメリカ同盟軍である北部同盟を歓呼として迎える市民の姿の映像です。この映像はくり返し世界中に流されました。
これにより、それまでアメリカの戦争に反対していた人たちも、いろいろあったけどこれでよかったのかなあと受け止めたように思います。以後、アフガン問題は人びとの中から忘れ去られていくことになりました。
アフガンにもたらされた「自由」
しかし、実際には何が起きていたのでしょうか。干ばつは治まっていません。今も進行中です。タリバン政権の崩壊により「自由」と「解放」はもたらされました。では何か自由になったのでしょうか。ケシ栽培の自由です。それまで絶滅されていたケシ栽培は、米軍の進駐とともに盛大に復活しました。数年を待たずして、アフガニスタンは世界の麻薬の94%を供給する麻薬立国になってしまったのです。
女性も解放され、自由を得ました。しかしそれは、一家の働き手を爆撃によって失ったあと、生活のために乞食をする自由です。外国兵相手に売春する自由です。貧乏人には餓死する自由が与えられました。英語が流暢で外国人におべっかを使うのが上手なアフガン人が裕福になっていく自由もあります。
99%の人の立場から見るのか、1%の人の立場から見るかでそれは違うかもしれませんが、私のこの見方は正しいと思います。
私たちPMSは水を確保する活動を続けました。しかし、これまでのような飲み水を確保するだけでは十分ではありません。農業ができるようにならなければいけない。
しかし、現地の伝統的な灌漑法では何度我々が再生を試みてもすぐに枯れてしまうのです。地下水利用も限界に来たということです。地表水に頼らざるを得ない、というのがこの時期私たちが至った結論でした。
簡単にアフガニスタンで起きている気候変動について説明しおきましょう。気温が上がり、それまでは少しずつ溶けていっていた山の雪が一気に溶けるようになり、洪水が頻発するようになり、川から農地への取水口が簡単に壊れるようになります。洪水は頻繁に起こるようになったものの、水が必要な時期にはまったくないという状況が生じました。水が取りこめなくて、農地が荒れていく。さらに山間部では雪が大量に溶けるので、地上に水が滞留する時間が少なくなり、地下水が年々減っていきます。そして、乾燥化が進む。この悪循環が進行しています。
「緑の大地計画」のスタート
人間は食べなくてはいけません。地下水源が枯れてきている以上、それより大きな大河川から取水する以外にありません。100の診療所をつくるよりも1本の用水路をつくったほうが人びとを救うのです。そして02年1月に立ち上げた「緑の大地計画」のもと、03年3月に潅漑用水路建設を始めました。最終的に25キロ、3000ヘクタール、10数万人の農民が救われるという成果を達成しました。
初めは重機1台を手に入れるだけで半年以上かかりました。皆がこんなことで水路の建設なんてできるのだろうかと思いました。そして、用水路の維持・管理はさらに難しいものです。それを誰が行うのか。他ならぬ現地の農民たちです。地域の人びと自らの手で維持・管理していかねばなりません。補修しなければならないことがあっても、農民たちは重機を扱う業者を簡単に雇うことはできません。だから、現地の人びととともに、手で修復可能となる工法に基づく水路をつくらなければなりませんでした。
そこで取り入れたのが、日本の技術でした。日本とアフガニスタンは全然違う国のようですが、地理条件については似たところがあります。急流河川が多いということと、水位差が大きいということです。夏に台風が来ると水位は一気に上がるが冬はカラカラになる。ですから、川から水を取り込む技術は似ているのです。そこで、住民の手で維持・管理できなければいけないことを考え合わせて、日本の伝統的な技術に着目しました。取水口については福岡県朝倉市にある山田堰をモデルに、そのコピーをアフガニスタンのあちこちにつくりました。この取水堰のすぐれている点は1年を通して欲しいときに欲しいだけの水をとることができる点です。護岸整備の技術も、コンクリートではなく、蛇籠工といって針金で編んだ籠に石を詰めたものを使い、護岸壁にする工法を採用しました。アフガニスタンでは石材は豊富にあります。現地の農民も石の取り扱いには非常に慣れています。これだったら自分たちで維持・管理ができると考えました。
鉄筋コンクリートを使った三面掩蔽の水路は、水害などで壊れると補修は土木の専門家でしかできません。現地ではそんなことは到底できません。蛇籠のよさは壊れにくいことです。例え壊れても、地元の人でも簡単に補修できます。実際これまでも何度か洪水に遭いましたが、洪水で壊れたところはほとんどありません。それくらい強じんなんです。日本でも見直されている工法です。
もちろん鉄筋コンクリートが全然いらないということではありません。ものすごい土石流が流れてくる、ダラエヌール渓谷では地下に大規模な工事を行いました。
天・地・人
05年から次々と村が復活します。つまり灌漑用水路の効果が現れはじめたのです。改めて水の威力に驚かされました。大勢の人が村に戻り、暮らせるようになっています。
ガンベリ沙漠というとてつもなく大きな沙漠地帯まで7年かけて用水路を完成させました。沙漠では真夏は摂氏53度にまでなります。そんな中での作業です。次々と作業員は倒れていきました。それでもみんな作業をやめようとしませんでした。彼らはほぼ全員難民だったのです。彼らの願いは二つだけです。一つは、三度三度ごはんが食べられること。もう一つは、自分の故郷で家族とともに平和に暮らすことです。この用水路が完成すると、家族を呼び寄せて家族一緒に仲良く暮らすことができる。しかし失敗すれば、また難民生活が待っている。こういった生死の瀬戸際で必死に生きようという思いがエネルギーとなったのです。これは決してきれいな話ではありません。
こうして09年8月4日、ガンベリ沙漠に全線25キロメートル近くの用水路が開通しました。このときみんな「これで生きられる」と口々に言いました。かつての沙漠が現在、アフガニスタンの中でもっとも豊かな地域になりつつあります。
私たちの活動方針は天・地・人に要約することができます。難しいことではありません。その地域の自然条件を読み取り、文化を尊重し、そこで暮らしている人が何を考え、何を欲しているのかを十分読んだ上で、暴力的な方法によらず、その地域の幸せを回復するということです。私たちはこれを固い方針としてきました。
先ほども言いましたが、アフガニスタンの人びとにとってモスクは共同体の要となるところです。人が戻ってきてもモスクがないと村は成り立ちません。しかし、なかなかそれを建てることができない。村の中心となるような大きなモスクには、マドラサと呼ばれる教育施設が付属するのですが、マドラサはイスラム過激派の温床であるという国際的な認識があったため誰も建てたがらなかったのです。反米主義者とレッテルを貼られ攻撃されるからです。そこで我々が建てることになりました。このモスク建設により、村のもめ事その他は丸くおさまるようになりました。
先ほどガンベリ沙漠を横断する水路建設について触れましたが、現在開墾が少しずつ進んでいます。開墾を可能にしたのは、水だけではなく、砂防林の造成です。こんな沙漠に本当に林なんかができるだろうかと思いましたが、成功しました。木の成長がとても早くわずか4、5年で10メートル以上も伸びます。これにより現地が完全に開墾されるのはそう遠いことではないだろうと思っています。かつての不毛な沙漠は今地域でもっとも豊かな場所になりつつあるのです。
こうして私たちは安定灌漑地域を増やしていきました。安定灌漑というのは水が必要なときに必要なだけの量を配ることができる給水システムです。要らないときに水が余り、要るときに足りないという状況がこの何十年間ずっと続き、生産力が落ちていました。そういった地域が次々と復活していき、昨年から取り組んでいる連続堰505メートルが成れば、約1万6500ヘクタール、65万人もの農民が食べられる生活空間を実現することができるのです。
迷信の虜になっているのは我々だ
この約30年を振り返って思うことは、人間と自然との関係。人間はどこに行くのかという問題です。私たちは、技術にしろ政治にしろ、進歩とか改革という言葉に弱い。アフガニスタンについて、今日は戦争とか難民といった話ばかりをしてきましたが、彼らが暗い顔をして生活しているかというとそんなことありません。助っ人として日本からやって来る若者の方がよほど暗い顔をしています。これはいったいどういうことなんでしょうか。幸せというのは金さえあればなんとかつかめる、武器さえあればこの身を守ることができるという迷信の虜に、日本中あるいは世界中がなっているのではないでしょうか。そう考えれば私たちがこの迷信から自由でいられるのは役得であると思っています。
今世界中が曲がり角にあります。私たちは重要なことは何か。何が必要で何が必要でないのか。見極める必要があるのではないでしょうか。これで私の話を終えたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
内痔核の術後、再発した際の再手術は。

12月に入って一気に季節が進んで、寒さの厳しい「冬」本番になってきましたね。12月はクリスマスや忘年会など様々なイベントがある月です。楽しい年末を過ごしたいものです。

さて今回は再発した内痔核に対しての再手術に関して少しお話したいと思います。
渡邉医院に受診される患者さんの中に「これまで何回か痔の手術をしたけれど、また再発してしまった。」と言って来られる方がいます。何回も手術。このことは患者さんにとってはとても辛いことです。できれば一回の手術でスッキリ治って、その後再発しないようにしてあげたいと思っています。
ただ、どうしても排便習慣の改善が出来なかったなどの原因があると、どうしても内痔核が再発してしまうことがあります。最終的には内痔核の治療後に一番大切なことは排便習慣です。手術をした後は、医師はそこをしっかり治していかなけれはならないと感じています。
でも再発した患者さんを目の前にした場合は、やはりもう一度手術等をして根治しなければなりません。では再発した内痔核をどう手術などの外科的治療で治していくか。それを考えていかなければなりません。
再発の二つのパターン
さて、内痔核の手術をした後、再度内痔核が再発して脱出してくる内痔核には二つのパターンがあると私は考えています。
前回手術とは別の部位の内痔核が脱出するパターン
一つは前回手術した部分と別の部分の内痔核が脱出してくる場合です。内痔核の好発部位は決まっています。肛門の3時7時11時の方向、つまり左、右後ろ、右前の3箇所です。これは痔動脈が肛門のこの3箇所に走っているからです。どんどん血液が流れ込んでくる場所でこの3箇所に内痔核はできます。
内痔核の手術適応は、排便時に内痔核が脱出してきて押し込まなければならない第Ⅲ度の内痔核と、常に脱出したままになり押し込むことが出来ない第Ⅳ度の内痔核です。
例えば1回目の手術が肛門の3時の内痔核を手術したとして、残る7時と11時の内痔核が次第に悪化して脱出するようになり、再発する場合です。この場合は厳密には再発ではなく、新たに別の部位の内痔核が悪くなったということです。
この際は、診察した際も「ここは前回の手術では手を付けていなかった内痔核だな。」と解ります。その場合は、初回の手術同様に、手術の方法が決まってきます。第Ⅲ度の内痔核の場合はその内痔核の性状で痔核根治術やジオンによる四段階注射法での痔核硬化療法をするかを選択して手術方法を決めます。ですから目の前にある内痔核をどうするかを考えます。
前回手術した部分と同じ部位の内痔核が再発するパターン
もう一つのパターンは、前回手術した部分と同じ部位が脱出してくる再発パターンです。
この場合は、初回の内痔核が脱出してきた時と同じように、肛門上皮を含めて内痔核が脱出してくるパターンと、内痔核が発生する粘膜部分のみが脱出してくるパターンがあります。また最近では行われなくなりましたが、ホワイトヘッド手術と言う手術をした後の再発は肛門全周に直腸の粘膜が脱出してきたり、一部の直腸の粘膜が脱出してくることがあります。
ですから前回手術をした部位と同じ場所が再発した場合は様々な脱出パターンがあります。そのパターンに対して最適と考える手術をしなければなりません。そこが再発した際の再手術での難しいところです。やはりさまざまな経験が必要となってきます。
同じ部分の再発に対しての手術
初回同様に肛門上皮も含めて内痔核が脱出してくる場合は、その脱出する状態でもう一度痔核根治術が必要であったり、またはジオンによる痔核硬化療法でも治療可能なこともあります。
また内痔核の粘膜部分が脱出してくるパターンではジオンによる痔核硬化療法や脱出してくる部分の大きさにもよりますが輪ゴム結紮法で治療することが可能なこともあります。
またホワイトヘッド手術後に粘膜が脱出してきた場合は、ホワイトヘッド手術で失われた肛門上皮を再形成しなければなりません。例えばSSGなど、皮膚弁を作って新しく肛門上皮を形成する手術が必要になってきます。
このように脱出してくる粘膜の状態、大きさなど考えて、様々な方法を考える必要があります。また一つだけの方法でなく、いくつかの手術方法を組み合わせて最善の治療法をしていく必要があります。
一度手術した肛門であることを忘れてはいけない
ただいずれのパターンの再発に対して手術をする場合は、一度手術をした肛門であることを決して忘れてはいけません。目の前に脱出してくる部分だけをみてそれを単に切除した場合、場合によっては肛門狭窄など、新たな不具合を生んでしまう原因になってしまいます。
必要かつ十分な手術を
どんな手術でも必要でかつ十分な手術を行うことが大切です。「十分」は根治性を求めること、また「必要」は機能を十分に残すということです。根治性を求めながら、機能を損なわないように手術すること。このことはどんな手術を行う場合にも大切なことですが、特に再発した内痔核に対して再手術を行う時には、さらにこのこと考えて手術を行わなければなりません。
患部の診察前に医師が考えていること。

もう12月になりました。一気に冬本番と言った寒さです。今年も後一か月になりました。早いものです。12月クリスマス、忘年会などいろいろ行事が立て込んでいると思いますが、体には気を付けて楽しい年末を過ごして下さいね。
渡邉医院も玄関前の通りには、そして中庭も秋と言うよりは冬を感じるようになりました。

患部の診察の前に医師が考えていること

さて今回は、患者さんが診察室に入ってこられた時から実際に患部を診察するまでに何を見て、何を聞いて病気を判断しているのかを少しお話したいと思います。
男性、女性でも予測する病気は違います。
まずは、診察する患者さんが男性か女性かで病気をある程度絞っていきます。男性に多い病気、女性に多い病気があります。男性の場合は内痔核や痔瘻が多く、また女性の場合は内痔核や裂肛などが多い傾向にあります。問診表には出血の有無、排便時の痛みの有無、また痛みが常に有るか無いか。また排便時に脱出するかしないか?などの項目にまずは目を通します。
排便時に痛みなく出血する場合。
まずは問診表で、排便時に痛みなく出血すると記載してある場合は、一番最初に疑うのは内痔核です。また排便時に何か出てくるかどうかを聞いた欄には①排便しても何も出てこない。②排便時に出てくるが、自然に直ぐに戻る。③排便時に出てきて押し込んでいる。④出たままになっている。の四項目の質問があり、ここから内痔核の程度を予測します。
例えば、排便時に痛みなく出血して、しかも排便時に出てきて押し込むといった場合は、内痔核で、そして病気の程度は第Ⅲ度の内痔核と予測します。こういった予測のもとで実際に患部の診断をしていきます。
排便時に痛みがあって出血する場合。
次に排便時に痛みがあり、出血する場合は裂肛を疑います。また排便時だけでなく、排便後も痛みが持続する場合は、ある程度裂肛の病状が進んでいる状態ではないかと予測します。
ただ、裂肛の場合、出血はなく排便時の痛みだけが症状の場合があります。この場合は、血栓性外痔核の場合も排便時に痛みを感じることがあります。ただ、血栓性外痔核の場合は、肛門に何かできている、いぼのようなものが出来ている、腫れているといった症状があるので、そういったことを基に裂肛なのか血栓性外痔核なのかを予測していきます。ただ、裂肛か血栓性外痔核かは患部を診察することで一目瞭然全です。
腫れて痛みを伴う場合。
次に男性で急に肛門が腫れてきて痛みが出てきたという症状がある場合は、血栓性外痔核と肛門周囲膿瘍を疑います。血栓性外痔核の場合は腫れが治まってくると段々痛みは軽くなってくるので、問診の質問項目のなかで、痛みはあるが段々軽くなってきたという部分にチェックがあれば血栓性外痔核を疑います。反対に痛みがあり、段々痛みが強くなるとか、痛みに変化なく常に痛いなどの場合は肛門周囲膿瘍を強く疑います。
また内痔核に血栓が詰まって急に出たままになって痛みが出る嵌頓痔核のことがあります。この場合はこれまでに排便時に出てきて自然に戻ったり、押し込んでいたりしなかったかをみるとある程度判断することが出来ます。
また、血栓性外痔核や肛門周囲膿瘍の場合は出血するといった症状がありません。一方嵌頓痔核の場合は内痔核からの出血する症状があります。こんなところからも予測していきます。ただ、血栓性外痔核も血栓が破けた場合は出血することもあります。でもこの際は常に出血していて下着に常に血が付くといった症状があるのに対して、内痔核の場合は排便時の出血が症状となります。また肛門周囲膿瘍でも自壊すると出血しますが、この際は膿も一緒に出てきます。こういったことから病気を判断していきます。また肛門周囲膿瘍の場合は発熱を伴うこともあります。
女性の患者さんを診る場合。
女性の患者さんで排便時に痛みと出血を伴う場合は、まずは裂肛を強く疑います。裂肛はやはり女性で、しかも若い患者さんに多い傾向があります。
また女性の患者さんで、排便時になにか出てきて押し込んでいるといった症状がある場合は、内痔核や裂肛が原因でできる肛門ポリープがでてくることがあったり、直腸の粘膜がでてくる直腸脱の場合もあります。内痔核の場合は排便時に痛みなく出血するといった症状があるのに対して、裂肛が原因での肛門ポリープが出てくる場合は、排便時の痛みといった症状があります。こういったところで内痔核の脱出なのか、裂肛が原因での肛門ポリープが出てきているのかを予測します。また直腸脱に関してはやはり高齢者の女性に多い傾向があります。高齢の女性で排便時に何か出てきたり、立っていても出てくるなどの症状ある場合は直腸脱を疑います。内痔核が脱出してくるのか直腸の粘膜が出てくるのかは、肛門の状態をみるとある程度解ります。内痔核の場合は肛門がしっかり締まっているのに対して直腸脱の場合は肛門の締まり具合が悪い印象があるのと、直腸脱の場合は、肛門の表面に粘液が付着していることが多いです。確定診断には浣腸をして頑張ってもらった後の肛門の状態を診たり、筒型の肛門鏡を挿入して、腹圧をかけて怒責しながら肛門鏡を抜いてくることで内痔核が出てくるのか、直腸の粘膜が出てくるのかを診断することが出来ます。
診察室に入る際の歩き方、椅子の座り方。
後は、診察室に入ってくる際の歩き方、椅子に座るときの座り具合、座っているときの姿勢などでもある程度診断がつくことがあります。椅子に座る際に体がどちらに傾いているか。例えば右に傾いていれば左が痛いんだなあとか、座ることもできない場合もあります。こんな場合は肛門周囲膿瘍や嵌頓痔核を疑います。こういったように、患者さんの椅子の座り方、いすに座れるかどうかなどでもある程度病気を予測することができます。

とりとめもない話でしたが、実際に患部を診察する前に、問診表や患者さんの表情。また診察室に入ってくる際の歩き方。また椅子に座る際の具合、座っているときの患者さんの姿勢など、実際に患部の診察をする前に医師はいろんなことを予測して、病気は何だろうと予測してすでに診断が始まっているのです。
雲の表情

秋の雲。いろんな表情をします。夏の雲は入道雲。もくもくと空高く広がっていきます。秋の雲は夏の雲と違って、いろんな表情をするんだなあと思います。
なかなか空を見上げることはありません。でもたまに空を見上げる。そこに浮かんでいる雲を見ていると、なんとなく心癒されるような。気持ちが優しくなるような気持がします。澄み渡った青い空に浮かぶ雲。そして風に流されて、どんどんその姿は移り変わっていきます。その雲の流れ、その変化は時間を忘れてづっと見続けることもできるなあと思います。
母は以前「曇って面白いね!いろんな表情をして。見ていて全然飽きないわ。」と。本当にそう思います。
今日の午後の空と雲の写真を何枚か撮影してみました。

薄く刷毛で掃いたような雲に羊の毛のような雲。まだ空は青いです。

夕日が当たり雲にも影が。青、黄色、そして灰色のグラデーションがきれいです。

ほんの数分の間に青空が少なくなり、橙色と灰色から紫色の雲に変化。

雲の形も刷毛で掃いたような雲からモコモコとした雲に。青から紫色、そして橙色から黄色へと美しいグラデーション。黒く影となった木々。いい感じです。

随分日も暮れてきて。青はなくなり灰色から紫色へ。

同じ場所で、ほんの数分の間にこんなにも雲の形や色が変わっていく。とても面白いです。
毎日、仕事などいろんなことに追われている生活を日々送っています。たまにはのんびりと空を見上げ、そこに浮かぶ雲の流れ、変化、雲が作り出す表情をのんびり眺める時間をつくるのもいいかなあと思います。これからはチョット寒くなってきますが。時々こういったように空を眺めて、ホッとしたひと時。心和み癒される時間をつくりたいなあと思います。
今日はチョット短めで、いつもと違った内容で・・・
便が詰まる。とっても辛い!!

11月も残すところあと1週間。この連休は多くの方々が紅葉を観に出かけているんだろうなあと思います。今日ば少し寒さも和らいでお出かけ日和だと思います。渡邉医院の木々たちも、色ずき始めています。玄関前の手水鉢には赤く色ずいたハナミズキの葉が浮かんでいました。

ここ最近、私自身、紅葉を観に行かなくなったなあと思います。久しぶりに出かけてみてみようかなあと思います。
寒くなって便秘になる人が。
さて、10月ごろから、季節の変わり目が影響しているのか、便が硬くなって出にくくなってしまう患者さんが見受けられます。
暑かった時は、汗もかき体の外に出ていく水分は多かったはずですが、反対に暑さに対して、しっかり水分が摂れていて、暑かった夏場は調子よくでていたのでしょう。涼しくなって、また寒さが段々厳しくなって、寒い時期は乾燥しているので、自分が感じる以上に水分が体の外に出ていきます。でもそれに対して摂る方の水分が少なくなって便が硬くなって出にくくなってしまうのかなあと思います。寒い時期もしっかりと水分を摂る必要があります。
寒い時期も十分に水分を。
今日も、休日ですが、入院の患者さんや手術をしたばかりの患者さんの診察をしに診療所に行きました。その時、電話がかかってきました。「便が硬くて出なくなってしまいました。そこまで来ているのですがでません。肛門は開いたままになっていて、便が勝手に出てきてしまいます。肛門もとても痛いです。診察してもらえませんか?」という内容の電話でした。「直ぐに来てください。」とお答えして診療所に来てもらうことにしました。
便は硬くなってしまうと出なくなってしまいます。
便が硬く詰まってしまうと、いくら頑張っても出なくなってしまいます。浣腸しても浣腸の液しか出てこなくて便は出ません。硬くなってからあわてて下剤を飲んでも、硬くなった便を柔らかくしてくれる下剤はありません。下剤は硬くなった便を柔らかくする薬ではありません。硬くならないように柔らかくする薬です。ですから便が硬くならないように、慢性の便秘症の方は具合よく便が出ていても毎日しっかり内服する必要があります。
便が詰まると、勝手に便が出てしまう。
また、直腸にある便を出そうとして、肛門は緩んだ状態になっています。ですから、直腸に詰まった便がだらだら自分の意志とは関係なく出てきてしまったり、硬い便の奥にある柔らかい、また下痢状の便が24時間だらだら出てきます。自分の意志とは関係なく便が出てしまうので、患者さんは、肛門が緩んでしまったのだと勘違いしてしまいます。実際は、便を出すために肛門が緩んでくれているのですが。
直腸に便が詰まると、肛門はめちゃくちゃ痛い!
また、直腸には便があってはいけないところです。直腸と肛門とで便を出すところです。ですから、硬い便が直腸に詰まったままになっていると、それだけで肛門がとても痛くなってしまいます。またでないので頑張ることで肛門全体が腫れあがってしまうこともあります。こういった症状も、直腸にある便をスッキリ出してしまうことで痛みはとれ楽になります。
便が詰まった時はどうするか。
では直腸に詰まってしまった時どうするかです。
直腸に硬い便が詰まったままで浣腸しても、便は出ず、浣腸の液だけが出てきてしまいます。ですから少し辛いのですが、直腸に詰まった硬い便を指で崩して柔らかくしたり、摘便と言って指で便を出してあげなければなりません。硬くなった便を指である程度出して、硬くなった便を崩して柔らかくしてから浣腸をします。そうすることでスッキリ便が出てくれます。ただ、直腸に便が残ったまま家に帰ってしまうと、その残った便がまた硬くなって出なくなってしまいいます。ですから便が詰まって診療所に来てもらった患者さんは、直腸にある便がスッキリ出きってしまうまでは帰らずにいてもらっています。
スッキリ出た後は緩下剤で便秘を治そう。
スッキリ便が出た後は、便が硬くならないように緩下剤を内服してもらいます。渡邉医院ではまず酸化マグネシウムから始めています。
便が詰まって全くでなくなってしまうと、とても辛いです。頑張っても頑張っても便が出ないと目の前が真っ暗になったり、トイレで貧血を起こしたりします。また頑張ることで肛門も痛くなりますし、そもそも直腸に硬い便が詰まっているだけでも肛門はとても痛いです。慢性の便秘の方は日ごろから緩下剤を飲んで具合よく便が出るようにしながら、便秘を治していく必要があります。
3日間の間にはスッキリ出そう。
食べたものが消化され、吸収され、便になるまで早くて12時間、ゆっくりで3日間です。ですから3日経っても便が出ないようでしたら4日目を期待しても出ません。便が出ないようでしたら早めに医療機関を受診して便を出してもらったり、便秘の治療をしていきましょう。
便が詰まってしまうことは、本当に辛いことです。
「12月の献立」を紹介します。

11月の第3木曜日は、ボジョレーヌーボーの解禁日でした。例年ならテレビなどでお祭り騒ぎの様に報道されたりしていましたが、今年はボジョレーヌーボーの報道は見なかったように思います。あまりテレビを見ないこともあるかもしれませんが・・・(笑)
今年の日本の天候。台風などで大荒れの天候だったように思います。様々なところで甚大な被害が出て、今もなお避難生活を送られている方々も多くいらっしゃいます。また復興もまだまだ進んでいないように思います。早く、日常の今まで通りの生活に戻られることを願うばかりです。
フランスのボジョレー地方もワイン生産者泣かせの大荒れの天候だったそうです。悪天候の中で、葡萄の生産量は2018年の半分、過去5年間の平均よりも25%も落ち込んでしまったそうです。
ただこういった悪条件の中、「期待できるビンテージ」と言うことで、味の評価は前向きだそうです。
機会があったら、飲んでみて下さいね。
さて、12月の献立を紹介しますね。きっとボジョレーヌーボー、赤ワインが合うんじゃないかと思います。
12月の献立は、「ロールキャベツでおもてなし」ということで、ロールキャベツを中心に、ブロッコリーのペペロンチーノ、3種のきのこソテー、キャロットライス、マッシュポテトの5品です。
「12月の献立」

1人分 約500kcal、たんぱく質 20g食物繊維 12g
「キャロットライス」

材料
ご飯 1合
人参 1/2本
ハーブソルト 適宜
作り方
①人参は少しやわらかくなるまでチンして、すりおろす。
②ご飯に1とハーブソルトを混ぜて、小さなおにぎりにする。
「マッシュポテト」
材料
じゃがいも 2個
牛乳 100㏄
ハーブソルト 適宜
胡椒
作り方
- ①じゃがいもはチンしてやわらかくし、
- つぶして牛乳とハーブソルトで味を整える。
- (いもの水分で牛乳は調整する)
「冬至うどん」と「ゆず風味の巣ごもり」のレシピを紹介します。

11月ももう1週間で終わります。明日明後日と連休です。きっと京都の紅葉の名所は観光客でいっぱいになるでしょうね!紅葉の見ごろも今週と来週かなあと思います。皆さんもこの連休、どこか紅葉狩りに行かれますか?
渡邉医院の玄関前のハナミズキの葉もすべて赤く色づき、落ち葉は真っ赤です。

中庭の紅葉は少し茶色ががかった赤。これからもっと色づいてくるのかなあと思います。
今回は12月のレシピのテーマの一つ、冬至メニューを紹介します。レシピは二つ、「冬至うどん」と「ゆず風味の巣ごもり」です。
「巣ごもり」って何と言うことで調べてみました。巣ごもりは卵料理の一つで、細切りにした野菜の中に卵を割り落し、加熱したものを鳥の巣に見立てた料理だそうです。今回のレシピは小松菜と油揚げのを細かく切った中に温泉卵を落としたものです。
また、今回は管理栄養士さんから冬至に関してのコメントもいただきました。その内容を紹介しますね。
冬至はかぼちゃとゆず湯
冬至は一年で一番昼が短く、日照時間は夏至と5時間も違うそうです。昔の人の体調を崩さない知恵がかぼちゃとゆず湯のようです。
かぼちゃにはβカロチンやビタミンB群が豊富に含まれています。
βカロチンは体の中でビタミンAに変換されて、皮膚や粘膜を丈夫にする働きがあったり、視力の維持や癌の予防、免疫力の強化、そしてアンチエイジングなど、健康を保つのに重要な働きをする栄養素です。
ビタミンB群は、疲労回復のために必要な栄養素です。体内に摂取した炭水化物や脂肪などを代謝して効率よくエネルギーとして利用できないときに疲労感が出てくるそうです。このエネルギー代謝が円滑に行われるために重要な役割を果たすのがビタミン。特にビタミンB群が深く関わるそうです。
かぼちゃにはこの二つの栄養素が含まれています。昔の人の知恵は凄いですね。
また、日本では、冬至の日に運が回復することを願って、「運盛り」として「ん」が2つ入っている「冬至の七種」と呼ばれる食べ物を供える縁起担ぎの風習があります。
関西中心に、冬至には七種を食べる風習があるようです。「ん」という文字が2回つく食材を食べるのですが、「ん=運」が重なるという意味で、縁起担ぎの食材です。例えば次のような食材があります。
なんきん、れんこん、にんじん、ぎんなん、きんかん、かんてん、うんどん。
そして、今回の「ゆず風味の巣ごもり」には「おんせん卵」と「ん」が2回使われています。
さて、これらの食材「ん」が2回使われているだけでなく、様々な栄養素が含まれています。
れんこんにはビタミンCがレモンの1.5倍、人参にはカロテンをはじめとしたビタミンが、ぎんなん・きんかんには咳止めの効果が、かんてんには食物繊維が豊富に含まれ、風邪予防や免疫力向上、便秘・動脈硬化・高血圧改善の効果も期待できる食材です。
さらに、運をたくさん取り込むという意味のほかに「一陽来復」の意味もあります。「一陽来復」とは、冬至は太陽の力が一番弱まる日、そしてその日を境に再び力が蘇ってくる日と言う意味があります。冬が終わり春が来るように悪いことが終わってよいことに向かう願いも込められているそうです。
それでは明日の力を蘇らせるためにも冬至メニュー作ってみて下さいね。では、レシピを紹介しますね。
「冬至メニュー」
1人分 約500kcal、たんぱく質 30g、食物繊維 10g
「冬至うどん」

材料(2人分)
う(ん)どん 2玉
なんきん 1/8個
れんこん 小1節
にんじん 5cm
豚肉 80g
干し椎茸 1枚
だし汁
味噌
*作り方
だし汁に硬いものから順に入れ、具材が柔らかくなったら、
うどん・みそを入れ一煮たちさせる。
「ゆず風味の巣ごもり」

材料(2人分)
小松菜 1/2把
油揚げ 小1枚
温泉卵 2個
★ゆずのしぼり汁 1個分
★めんつゆ 小さじ2
*作り方
- ①小松菜はゆで、3cmに切る。
- ②油揚げは焼いて短冊に切る。
- ③★で和えて器に盛り、温泉卵をのせる。
「ブロッコリーのペペロンチーノ」のレシピを紹介します。

今日は、グッと冷え込みましたね!秋を通り過ぎ、一気に冬になった感じです。今週末の連休は、きっと紅葉で心癒す観光客が多く京都を訪れることだと思います。ここ数年、私自身あまり紅葉を観に行かなくなったなあと思います。日々の通勤の道並み、そして診療所の木々たちの紅葉を観るだけでも心癒されます。
今日は叔母が京都に来てくれて、母と一緒に三人で夕食を食べ、楽しいひと時を過ごしました。
これから冬に向かって加速度がついていくのでしょうね。着る服も考えなければ。
さて、今回は「ブロッコリーのペペロンチーノ」と「3種のきのこのソテ」のレシピを紹介しますね。キノコは便の量を増やしてくれます。便秘の人にももってこいの食材です。作ってみて下さいね!
「ブロッコリーのペペロンチーノ」

全量170kcalたんぱく質10g食物繊維10g
材料(作りやすい分量)
ブロッコリー 1本
★水 大さじ3
★塩 小さじ1/4
◇にんにく(みじん)1かけ
◇鷹の爪 1本
◇オリーブ油 大さじ1
塩こしょう
作り方
- ①ブロッコリーは子房に分け、茎は皮をむいて食べやすい大きさに切る。
- ②フライパンに①と★を入れ、ふたをして蒸し煮にする。皿に取り出す。
- ③同じフライパンに◇を入れ弱火でゆっくり香りを出す。
- ④③に②を戻して混ぜる。塩こしょうで味を整える。
「3種のきのこのソテ」

全量 約60kcal、たんぱく質10g、食物繊維11g
作り方
- ①しめじ、エリンギ、舞茸(など何でも)各1袋を食べやすい大きさにする。
- ②フライパンに①を入れふたをして蒸し焼きにする。
- ③ふたを取り水分を飛ばして香ばしい焼き目をつける。
- ④オリーブ油、ハーブソルトをかける。
「ロールキャベツ」のレシピを紹介します。

今回は、「ロールキャベツ」のレシピを紹介しますね。
11月も半ばになりました。良い天気の日が続いています。秋の空、そして空に浮かぶ雲、いろんな表情をしています。夏の入道雲と違って、羊の毛の様にモコモコしている雲。
刷毛でサッと描いたような雲。
また朝焼けや夕焼け。
いろんな表情をしていて、見ていてとても楽しいです。なかなか空を見上げることはありませんが、たまには空を見上げて、青い空や雲が見せる表情を眺めてみて下さいね。私に母が、こんなことを言っていました。「曇って面白いね。その時その時いろんな表情をしていて。」と。
さて、今日はロールキャベツのレシピを紹介します。ロールキャベツの味付けって、その家その家でいろんな味付けがあると思います。渡邉家は、コンソメトマトシチューにロールキャベツが入っていました。家の様にコンソメ、トマト、ホワイトシチュー、カレー、和風、そして中華風などいろんなアレンジができる料理ですよね。いろんな味付けを楽しむのもいいかなあと思います。今回紹介するレシピの味付けは、ブラウンシチューです。
野菜もいっぱい取れて、肛門科的には便秘にもいいかなあと思います。
ではレシピを紹介しますね。
「ロールキャベツ」

1個 約230kcal、たんぱく質 13g、食物繊維 5g
材料(6個)
きゃべつ 小1個
★合い挽き肉 300g
★玉ねぎ(みじん)大1個
★人参(みじん) 1本
★えのき(みじん) 1袋
★卵 1個
★塩こしょう
水 約1ℓ
ブラウンシチューのルー 1/2箱
作り方
- ①きゃべつは1枚ずつ葉の付け根を芯から切り離し蛇口の水をあててはがす。
- ②①を袋に入れしんなりするまでレンジでチンする(約8分)。
- ③②の硬い芯をそぎ、みじん切りにして★とボールで混ぜる。
- ④きゃべつの芯が手前になるよう3枚少しずらして並べ、真ん中に③を1/6置く。肉だねを包むように手前から一巻き、左側のきゃべつを織り込んで葉先まで巻き、右側のきゃべつを肉だねの中に押し込む。
- ⑤鍋に④を巻き終わりを下に隙間なく並べ、水を入れて20~30分煮る。
- ⑥ルーを溶かして10分煮る。
*⑤の前に焼き目をつけるとさらに香りがよくなります。
*ひき肉は豚でも鶏でも、さば缶やツナに変えてもおいしいです。
*味付けはコンソメ、トマト、ホワイトシチュー、カレー、和風、中華風など
アレンジできます。