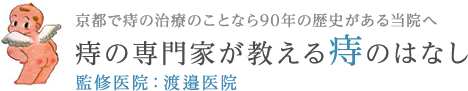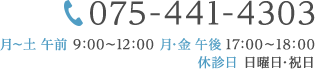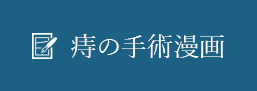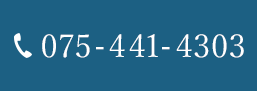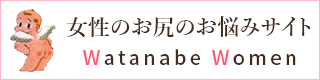肛門の診察Part3 視診・触診

さて、今回は指診、触診についてお話します。
指で触って診察する。直接患者さんの身体を触っての診察になります。いきなり指を肛門に入れると、患者さんは、びっくりされますし、痛みを伴うことがあります。
潤滑油となる軟膏をつけながら、そして肛門の緊張をとりながらゆっくりと指を肛門に挿入していくことが大事です。
ただ肛門の診察をする際に、いきなり肛門に指を入れるわけではありません。肛門の周囲の状態はどうか、硬い部分や触ると痛い部分がないか。そういったことをまず確認します。
肛門周囲膿瘍の場合ですが、肛門の表面に発赤や腫脹があると、視診でも診断できます。でも、膿瘍が肛門の奥の方の深い部分に広がっていく場合は、患者さんは肛門の痛みを訴えられますが、表面的には発赤や腫脹なの何の変化が無いことがあります。このような場合、肛門の周囲を押さえるように診察していくと、硬く触れる部分があったり、押さえることで患者さんが痛みを訴えられることがあります。また、ゆっくり指を肛門に挿入していくと、表面的にはわからなかった膿瘍を触ることができます。その時は膿瘍を硬く触れたり、硬いがブヨブヨした腫脹として触ることができ、その部分を押さえると患者さんは痛みを感じます。こういったことで、肛門周囲膿瘍の広がりを判断することができます。
痔瘻の場合でも、肛門の周囲を注意深く触ると、瘻管の走行がわかります。膿のでる部分を痔瘻の二次口と言いますが、二次口から肛門の中に続く瘻管を触ることができます。まっすぐな瘻管なのか、曲がっているのかなどを確認することができます。
さらに、肛門の周囲を触ることで、括約筋の硬さや厚さなどもある程度わかります。慢性の便秘で、いつも頑張っている患者さんの場合は、この括約筋が厚く硬い印象があります。
このように、肛門の周囲を触診するだけでもいろいろなことがわかります。
さて、表面の触診が終わったら、今度はゆっくり指を肛門に挿入していきます。勢いよくぐっと挿入すると痛みを伴います。ゆっくりと患者さんの痛みが出ないように挿入していきます。ただ、裂肛の場合は、排便時の痛みが原因で、肛門の内肛門括約筋の緊張が強くなっています。裂肛の場合は痛みをどうしても伴います。ただ、肛門に指を挿入することで、ある程度、内肛門括約筋の緊張がとれるので、痛みがありますが、ゆっくりゆっくり指を挿入することで、裂肛による痛みを緩和することができます。言ってみれば柔軟体操のような感じです。このように裂肛の患者さんは、内肛門括約筋の緊張が強いため、肛門のしまりが強く感じます。またある程度慢性の裂肛になると、裂肛を硬く指で感じることもできます。
痔瘻の場合は、痔瘻の原因となる原発口を、硬さや、へこみで指で感じることができます。
ところで、肛門の病気で一番多い内痔核ですが、初期の内痔核はなかなか触診だけではわからないことが多いです。第Ⅱ度、第Ⅲ度の内痔核になりますと、内痔核を指で隆起した塊として感じることができることがあります。ただ内痔核は触診だけでは十分に診察することができません。肛門鏡での観察や、怒責診といって、排便するときのように、グッと頑張ってもらった後の肛門の状態などを見ていく必要があります。
後は、私の指では、肛門の出口から約10cm奥までとどくようで、届く範囲に、直腸癌やポリープがないかなどもわかります。直腸癌の約70%大抵が私の指が届く範囲の直腸にできます。また指を肛門から抜いた時に、指に血が付着していないか?付着していたらどんな性状の血がついているかなども診断の助けになります。
また、直腸は通常便が残っていてはいけない場所です。直腸に便が残っているということは、排便の状態が悪いということです。直腸に指を入れたとき、硬い便が残っている場合は、慢性の便秘があるのではないかと推測できます。また直腸に便が詰まっているだけでも肛門に強い痛みが出ることもあります。直腸に硬い便が」詰まっている状態では、摘便といって、指で便を出すこともあります。
このように、触診ではいろんな病気やその状態を知ることができます。
次回はなかなか触診では診断がしにくい内痔核の診断をどうするのか?肛門の診察に使う肛門鏡での診察についてお話します。
肛門の診察Part2 視診

今回は、視診についてお話しします。
肛門の状態を診る時、いろんなことが見えてきます。
まずは、肛門にできる皮膚のシワです。皮垂、スキンタグといいます。
皮垂はいろんな肛門の病気によって二次的にできる皮膚のシワです。内痔核が原因であったり、外痔核や血栓性外痔核の血栓が吸収された後にできたり。また裂肛が原因でもできてきます。
ここで、少し皮垂についてお話しします。皮垂の定義及び原因は、血栓性外痔核や嵌頓痔核が保存的治療によって治癒した後や、痔核手術後の治癒過程で発生した線維組織の増殖であったり、あるいは繰り返しおこる肛門皮膚の炎症などで肛門縁の皮膚に結合織の増殖をともなう繊維性のシワとされています。分類ではGoligherは皮垂を特発性と二次性とにわけ、特発性は明らかな原因のないものであり、二次性は出産、内外痔核・裂肛・などに関連しておこるものとしています。また、病理学的特徴では、肉眼所見では、外痔核領域にみられる肛門皮膚の線維性肥厚であり、組織所見では肛門皮膚の上皮の肥厚および上皮下の間質にみられる強い線維化を特徴とするとしています。
さて皮垂のある部位で、その奥に隠されている肛門の病気を推測することが出来ます。
例えば、皮垂が、内痔核ができやすい肛門の右前、右後ろ、左にあれば、今現在、皮垂の奥に内痔核があったり、以前、内痔核があったことをあらわします。また皮垂が裂肛のできやすい、肛門の前後にあれば、今現在裂肛があるか、以前裂肛になったことがあることを意味します。このように皮垂の部位によって、今ある肛門の病気や以前なったことのある病気を推測することが出来ます。
次に、視診で明らかにわかるものに、血栓性外痔核、陥頓痔核、肛門周囲膿瘍、そして肛囲皮膚炎などがあります。また肛門にできた尖圭コンジロームや疣贅、粉瘤なども視診でわかります。
血栓性外痔核は肛門の外側に血栓(血豆)が詰まって腫れて痛い病気です。血栓性外痔核のほとんどは、視診でわかりますが、肛門の少し中の肛門上皮の部分に血栓が詰まるタイプの血栓性外痔核もあり、この場合は視診だけでは解りません。
内痔核だけでは、視診だけでは解りませんが、陥頓痔核は、排便時に脱出してくる内痔核に血栓が詰まって外に出たままになっている状態の内痔核です。これも血栓が詰まって脱出したままになっている状態の内痔核を視診でわかります。また強い痛みも伴います。
肛門周囲膿瘍は、血栓性外痔核と異なり、肛門が腫れあがり発赤や腫脹を認めます。肛門周囲膿瘍も視診でわかります。ただ、肛門周囲膿瘍の中には、肛門の表面に膿瘍が広がるタイプでなく、肛門の奥の方の深い部分に広がるタイプの肛門周囲膿瘍があります。この場合は、痛みは強いのですが、視診では明らかな腫脹は認めません。この場合は指診が重要な診断方法になります。
この様に、問診と視診でずいぶん患者さんの持っている肛門の病気を絞り込んでいくことが出来ます。次回は、指診についてお話ししたいと思います。
肛門の診察Part1 問診

肛門の病気を治す際に一番大切なことは、患者さんの病気を正確に診断する事です。しっかり診断をつけることで、次の治療へと進むことができます。
さて、肛門の病気を診断は、患者さんの訴えを聞く問診、肛門の状態を目でみる視診、そして指で肛門の状態を見る指診の三つが大切です。そして肛門や直腸の一部を観察する際に肛門鏡を使います。いずれも大切な診察です。今回は、その中でまずは初めて患者さんとあって、行う問診についてお話ししたいと思います。
問診では、患者さんが今一番気になる事、心配なことを聞いて、その患者さんの訴える症状から病気を推察していく大切な診察です。肛門の病気での訴えで多いのが、出血や痛みです。
1)出血について
出血では、まずは出血の状態がどのようなものかを聞きます。例えば、排便時に痛みなく出血するのか、痛みが伴っての出血か。また、出血の仕方が拭いた時に着く程度の出血なのか、またはポタポタ落ちるような出血なのか。出血が下痢状に頻回に出血するのか。下着に血が付いている。などなど出血だけでもいろんな状態があります。
排便時に痛くなく出血する場合は、内痔核(いぼ痔)のことが多いです。出血の程度はさまざまで、排便後拭いた時に血が付いたり、ポタポタ血が落ちたり、場合によってはシャーっと音がして出血したりします。でも痛みは伴いません。
これに対して排便時に痛みが伴う場合は、裂肛(切れ痔)のことが多いです。出血に関しては、これも傷のつき具合でいろいろな程度がありますが、裂肛の場合は、痛みが伴います。
また、下着に血が付いている場合は、血栓性外痔核が破けて出血したり、痔瘻などが原因で、痔瘻では出血と膿が下着についていることがあります。また内痔核が脱出したままになっている場合も、出血や粘液で下着が汚れる場合があります。
さらに、肛門に皮膚炎があって、これが原因で下着に血が付くこともあります。
出血で、下痢状の出血が頻回に出たり、血の塊が頻回に出る時は、直腸や大腸の病気で出血している可能性もあります。この場合は、大腸内視鏡検査など、大腸の検査が必要だと思います。
出血が今回が初めてなのか、以前からあって、出血が頻回になったり、出血の量が増えてきたのかも治療の選択に重要です。
2)痛みについて。
痛みでは、排便時に痛みがあったり、排便後に痛みがしばらく持続する場合は裂肛のことが多いです。
排便に関係なく常に痛みがある場合は、血栓性外痔核や肛門周囲膿瘍の可能性が高いです。また内痔核に血栓が詰まって脱出したままになった状態になった陥頓痔核などがあります。血栓性外痔核は血栓が詰まって腫れて痛むのですが、時間と共に腫れが引き、痛みは徐々に軽減してきます。これに対して肛門周囲膿瘍は、炎症が広がり膿が広がっていくので、痛みはどんどん強くなっていきます。
陥頓痔核では、痛みが出る前に、痛みなく排便時に内痔核が脱出して押し込むなどの内痔核の症状があり、そこに血栓が詰まって、痛くなります。
この様に、痛みの状態、痛みの経過でも肛門の病気が推察できます。
3)その他の症状
その他に、内痔核では、排便後に便が残ったような違和感があり、頑張りたくなったり、肛門に痛みはないが、何か挟まったような違和感があるなどの症状がでます。
また痔瘻では、肛門から膿が出る、下着に膿が付いているなどの症状が出ます。
肛門の皮膚炎では肛門が痒くなる。いつもジクジクした感じ痔がするなどの不快感があります。
この様に、患者さんの症状を聞くだけでもある程度の肛門の病気が診断され、病気を絞ることが出来ます。
また、これまでに肛門の病気になったことがあるか?また、肛門の手術をしたことがあるかなども、治療に関して大切な点だと思います。
最後になりますが、今一番気になる症状をしっかり医師に伝えることが大事だと思います。
次回は視診についてお話しします。
内痔核に対して輪ゴム結紮法は万能な治療方法か?

輪ゴム結紮法はどんな内痔核(いぼ痔)でも治すことができる万能の治療方法でしょうか?
その答えは「違う!」です。
輪ゴム結紮法による治療は、万能ではありません。適応を間違えて輪ゴム結紮法を行うと、内痔核が治らないばかりか、輪ゴムをかけた外側の部分が腫れあがり、痛みが強くなったり、輪ゴムが脱落した後に潰瘍を形成して、そこが裂肛(切れ痔)様になって、排便時の痛みがあったり、その痛みが原因で、肛門の緊張がつよくなり、慢性の裂肛となり、裂肛に対しての手術等が必要になってきます。
輪ゴム結紮法の適応となる内痔核は限定されています。治療しなければならない内痔核が輪ゴム結紮による治療が最適なのかをしっかり診断しなければなりません。
まず、輪ゴム結紮法の適応となる肛門の病気は内痔核です。
肛門の外側から約2~3㎝ほど皮膚の部分があります。この部分を肛門上皮と言います。その奥が直腸です。内痔核はこの約2~3㎝奥の直腸になった部分にできます。この内痔核の程度は四段階に分かれています。
まずは、排便時に出血したり違和感はあるものの、排便時に内痔核が脱出してこない(出てこない)程度の内痔核を第Ⅰ度の内痔核です。
次に排便時に脱出してくるが、自然に戻る程度の内痔核を第Ⅱ度の内痔核といいます。
さらに悪化すると、排便時に脱出して、自然には戻らず押し込まなければならない程度の内痔核を第Ⅲ度の内痔核。
一番具合が悪いのが第Ⅳ度の内痔核で、常に内痔核が脱出していて押し込むことができない程度の内痔核です。
内痔核だけですと、この間痛みはありません。内痔核以外のことが加わると痛みが出てきます。例えば裂肛(切れ痔)が合併したり、血栓(血豆)が詰まったりすると痛みが出てきます。
輪ゴム結紮の適応は第Ⅱ度以上の内痔核になります。排便時に内痔核が外に出てくるという症状があって初めて輪ゴム結紮の適応になります。でも先ほどお話したように、第Ⅱ度以上の内痔核すべてが輪ゴム結紮で治るわけではありません。
内痔核と言っても様々な性状を持っています。直腸の粘膜の部分だけにできる内痔核。肛門上皮の部分にできる痔核を外痔核と言いますが、内痔核だけでなく、肛門上皮の部分の腫脹がある外痔核を伴った内痔核。その外痔核部分が少ないものもあれば、外痔核部分が大きい内痔核もあります。
ただただ第Ⅱ度以上の内痔核といっても患者さん一人一人、内痔核の性状は全く違います。
輪ゴム結紮法の適応となるのは、粘膜の部分主張が主な内痔核です。肛門上皮の部分、外痔核部分が多い内痔核に対しては、適応となりません。もし、こういった内痔核に輪ゴム結紮法を行うと、肛門上皮の部分に輪ゴムがかかり、輪ゴムをかけた瞬間から強い痛みが出てきます。それでも痛みを我慢して治る場合もありますが、場合によっては、輪ゴムをかけた外側が腫れあがったり、輪ゴムが脱落(取れる)した際に、肛門上皮に潰瘍ができ、深い裂肛(切れ痔)様になり、排便時の痛みが続き、そのことが原因で、肛門の緊張が強くなって、裂肛の手術を行わなければならなくなることもあります。
ですから、輪ゴム結紮法を行う場合は、本当に患者さんの内痔核が輪ゴム結紮の適応となるかどうかをしっかりと診断し、判断しなければなりません。したがって、内痔核の状態、性状の的確に見極める診断が必要です。
安易に輪ゴム結紮法を行うと様々なトラブルを招く可能性があります。また、輪ゴム結紮法も内痔核の根元に輪ゴムをかけるので、輪ゴムが脱落した際に、内痔核の根部の動脈からの出血がおき、出血を止める止血術が必要となる可能性もあります。
輪ゴム結紮法の適応をしっかり見極め、適切に輪ゴム結紮法を行う必要があります。
輪ゴム結紮法について紹介していますので、そちらも参考にしてください。
適切な診断と適切な治療方法の選択が重要。

肛門の病気を治す際に、一番重要なことは、適切に肛門の病気が」診断できているかです。適切な診断なしでは、治療することはできません。適切な診断があってこそ、次の治療へとつないでいくことができます。
例えば内痔核(いぼ痔)についてお話しします。
患者さんの症状としての訴えは、「排便時に出血した。」「排便時に、いぼ痔が出てきて押し込んでいる。」「いぼ痔が出たままになっている。」「排便後も便が残ったような違和感がある。」「なにかいつも肛門にものが挟まったような違和感がある。」「痛みがある。」「肛門がいつもジクジクしたかんじがある。」「出血はしないが、粘液のようなものがでてくる。」などなど様々な症状を訴えられます。
内痔核の診断において、大きく二点について注目します。
まず一つ目は、排便時の出血です。内痔核は痛みの感じない部分にできます。したがって出血も排便時に痛みなく出血を認めます。出血の量は、拭いたらつく程度の出血から、排便時に飛び散るような出血など、内痔核の程度で出血の具合は変わってきます。でも、裂肛(切れ痔)などの内痔核以外の病気がなく、内痔核だけの場合は、排便時に痛みなく出血します。
もう一つは、排便時に内痔核が脱出する(出てくる)かどうかということです。
出血だけの場合は、出血の程度がよっぽどひどい場合を除いては、手術による治療にはなりません。手術をするかどうかを決める目安が、排便時に内痔核が脱出してくるかどうか。また脱出した内痔核が、自然に戻るのか、押し込まなければ戻らないのか、さらに押し込むことができないのか。この排便時の内痔核の脱出の有無、程度が手術をするかどうかを決める、重要なポインとになってきます。
排便時に内痔核が脱出してこなければ(第Ⅰ度の内痔核)、手術による治療の必要はありません。軟膏や座薬などの外用薬による治療や、出血が多かったり、外用薬で症状がとれなかったりした場合は、パオスクレーという痔核硬化剤による痔核硬化療法で治療します。
排便時に内痔核が脱出するも自然に戻る程度の内痔核(第Ⅱ度の内痔核)の場合は、外用薬だけでは十分に症状がとれません。この場合は、痔核硬化療法や内痔核の性状によっては、輪ゴム結紮法を行います。
排便時に内痔核が脱出して、押し込まなければならない程度の内痔核(第Ⅲ度の内痔核)の場合は、痔核根治術やジオンという痔核硬化剤を使っての四段階注射法での痔核硬化療法を行います。内痔核の大きさや、性状によっては輪ゴム結紮法で治すこともできます。
脱出したままになっている内痔核(第Ⅳ度の内痔核)の場合も第Ⅲ度の内痔核と同様に、痔核根治術、四段階注射法による痔核硬化療法、場合によっては輪ゴム結紮法などで治療していきます。
手術が必要な内痔核に対してどんな内痔核でも治療できるオールマイティーな治療方法は痔核根治術です。
ジオンによる四段階注射法による痔核硬化療法や輪ゴム結紮法はいずれも万能な治療方法ではありません。適応を間違えると、内痔核が治らないばかりか、症状が悪化してしまうことがあります。
しっかり内痔核の状態、性状を診断して、その内痔核に対してどのような治療法が最適な治療法なのかを決めていかなければなりません。
そのためには、内痔核に対してのさまざまな治療法を修得していなければなりませんし、最低限、どんな内痔核も治療できるオールマイティーな手術法である痔核根治術はできるようにならなければなりません。
「きんぴらごぼうトースト」のレシピを紹介します。

今日は、本当に暑かったですね。もう夏という感じです。寒かったり急に暑くなったり、体調の管理が大変ですね。
ゴールデンウイーク。ずいぶん前のような気がして、私にとって5月は、結構長く感じます。皆さんはどうでしょうか。
さて今回は、「きんぴらごぼうトースト」のレシピを紹介します。
「きんぴらごぼう」というと、ご飯と一緒に食べると美味しいですよね。私は、鷹の爪を入れて、ちょっとピリ辛のきんぴらごぼうが好きです。
私の家では、きんぴらごぼうが余ったとき、きんぴらごぼうを具に、春巻きを作って食べたりしています。きんぴらごぼうの春巻きも美味しく、ご飯がすすみますよ。
さて今回は、きんぴらごぼうはパンとあうということで、「きんぴらごぼうトースト」です。
簡単にできそうなので、試してみて下さいね。
「きんぴらごぼうトースト」
|
材料(1人分) 1人分 349kcal 食物繊維3.1g 食パン(5枚切り) 1枚
「管理栄養士さんからの一言。」 ご飯のお供は、パンのお供!? ご飯のお供と言えば、きんぴらごぼうやじゃこ、明太子などがありますが、これらはパンとの相性も抜群です!
|
|
|
今日は、母の日でした。

今日は、「母の日」でした。皆さんは、どうお過ごしでしたか?
私は、入院の患者さんの診察が終わって、花を買って母のいる実家へ。
一緒に食事をした後、母が昔書いたエッセイを見せてくれました。私が30歳のころに書いたエッセイです。
今日の「母の日」に、母からもらったプレゼントでした。
「スミレの便り」
忘れられない日。それは息子が高校一年の秋、左膝に障害を持つ様になった日。
杖を手に通学するのを送り迎えして二学期を終え、新しい年を迎えた診療日、
「一生、その足を背負っていくのだな」
と医者の言葉に黙ってしまった息子は、家に帰るなり、
「使えない足なら、切ってしまえ」
と、火のついているストーブをけり倒し、自室にこもってしまった。
スポーツ、スポーツ、スポーツの子が。
雪の舞う休日、嵐山にボートを漕ぎに連れ出したのは父親。父子のボート漕ぎは、
それからの我家の休日行事となった。
日射しも少しずつやわらいで来た日、
「お母さん、プレゼント」
嵐山の川上の岩影に、一株咲いていたスミレを、舟を寄せて取って来たとか。
その夜、夕食のかたづけをする母の背に、
「僕、ぐれないからね。心配しなくていいよ」
その息子も今年三十歳。春浅い日に、東京から静岡の裾野市に転勤となり、就任地の様子を知らせる電話が入った。
カーテンを開けると目の前に富士山。宿舎から職場まで歩いて四、五分。
道の両側は畑が広がって、と田舎の景色がえがかれる。
「元気でね」
と、離しかけた受話器のむこうから、
「お母さん、スミレが咲いていたよ。」

「アジの南蛮漬け」のレシピを紹介します。

ゴールデンウイークも終わって、日常の生活、仕事に戻って疲れは出ていませんか?楽しいゴールデンウイークでしたか?
今回は「アジの南蛮漬け」のレシピを紹介します。
アジと聞いてすぐに頭に浮かんだのは、アジフライでした。サクッと揚がったアジフライ。ご飯が進みますよね。
今回の「アジの南蛮漬け」に使うお酢にはクエン酸という成分が含まれています。このクエン酸という成分は、疲労の素を分解し、疲れが溜まるのを防いでくれるそうです。
ゴールデンウイークが終わっての1週間の疲れ、これから暑くなるようですが、暑さにばてないように、「アジの南蛮漬け」をためしてみて下さいね。
「アジの南蛮漬け」
|
材料(4人分)1人分 173kcal 食物繊維1.3g アジ(三枚おろし) 2尾
管理栄養士さんからの一言 ○●疲れの素に効く!お酢のパワー●○ お酢のクエン酸という成分は、疲労の素を分解し、 |
|
|
|
|
ゴールデンウイークも後半ですね。

早いもので、ゴールデンウイークも今日を入れてあと2日。後半になってきました。まずまずのお天気。今日は特に行楽日和ですね。皆さんはどうお過ごしですか?
私は、入院な患者さんもいらっしゃるので、ゴールデンウイーク中も診療所に来ています。
さて、アイキャッチ画像と言って、投稿の記事の題名と一緒に載っている写真ですが、今使っている花の写真は最近母と一緒に京都の北区にある植物園に行ったときに撮ってきた写真を使っています。
何年かぶりに植物園に行ったのですが、とてもよかったです。母はもうすぐ84歳で、入場は無料。私も200円で入園できます。
4月8日に行ったときは、まだ少し桜の花が残っていたのと、チューリップが満開でした。様々な種類のちチューリップが色とりどりに咲いていました。
母も楽しかったようで、もう一度行こうということで、 4月29日にも行ってきました。前回は時間が遅かったこともあって、温室に入れなかったので、この時はまず温室に行ってきました。少し暑かったですが、珍しい花などが咲いていました。この青い花も温室に咲いていました。淡い青色。優しさを感じました。
まだバラ園のバラは少しだけ咲いていましたが、たくさんの蕾がついていました。そろそろ咲いているころではないかと思います。白色のモッコウバラは、ほぼ満開でした。
母は、小さな子供が好きで、子供たちに会うたびに声をかけて、楽しそうに、そして嬉しそうに、本当に素敵な笑顔を浮かべていました。
私もそんな母の笑顔が大好きです。いつまでも母の素敵な笑顔を見続けられる社会になって欲しい、そんな社会にしていかなければならないと思います。そして全ての人たちが、心の底から思いっきり笑えて、素敵な笑顔になれる社会にしていかなければと感じました。
母が教えてくれた素敵な言葉。
「一人で見る夢は夢でしかない。みんなで見る夢は現実になる。」
その言葉がふと、思い浮かびました。
ゴールデンウイーク。楽しいひと時をお過ごしくださいね。
「サツマイモのチーズケーキ」のレシピを紹介します。

今回は、久しぶりにスイーツのレシピを紹介します。
サツマイモのスイーツというと、今、一番最初に頭に浮かんだのが、スウィートポテトです。
以前、デパートの催事場で開催された大北海道展で、1個500gもある巨大なスウィートポテトをかって食べたことがあります。美味しかったですよ。
二番目に浮かんだのは、石焼き芋です。寒い時期、「石焼~芋~」と軽トラックで売りに来ますよね。ホクホクのアツアツの石焼き芋。美味しいですよね。
サツマイモも便秘に良いです。皮と実の間に便を良くする成分があるので、皮ごと調理して食べるのが便秘には良いです。
さて今回は「サツマイモのチーズケーキ」のレシピを紹介します。
「サツマイモのチーズケーキ」
|
材料(パウンド型1台分)1台 968kcal 食物繊維5.3g サツマイモ 中1本(300g) |
|
下準備 ●パウンド型にオーブンシートを敷いておく。 作り方 ① サツマイモは厚めに皮をむいて5ミリ幅にスライスする。水にさらしてアク抜きをしたら、電子レンジ(600W)で5分程加熱し、なめらかになるまでつぶす。 |
★冷蔵庫で一晩冷やすと、しっとりとして美味しいです♪